
せたがや学生ボランティアフォーラムにインタビュー! ―「子ども」分科会―
ボランティアを志す大学生や高校生が一堂に会し、つくり、つながる「せたがや学生ボランティアフォーラム」が6月30日(日)に開催されます。
今回はこの「せたがや学生ボランティアフォーラム」の中で、学生が企画をしている「シンポジウム」と「6つの分科会」に取材をさせていただきました!それぞれの魅力とワクワクする熱い想いをねつせた!がお届けします!
ねつせた!メンバーの「人ト」がお話を聞かせてもらったのは、「子ども」分科会の担当を務める千葉大学2年の 河野 葵 さん。分科会のテーマである”子どもの『声』を拾い、大人の『手』を集める~子ども社会と繋げるために~”にはどんな想いが詰まっているのでしょうか…??
「ボランティア入門」分科会はこちら
「災害ボランティア」分科会はこちら
「ボランティアの可能性」分科会はこちら
「子ども」 ”子どもの「声」を拾い、大人の「手」を集める ~子どもを社会と繋げるために~”
「子ども」でもない、「大人」でもない。私たち「学生」だからこそ持てる視点があるのではないでしょうか!
子どもの意見に寄り添い、同じベクトルから社会の問題を見ることによって、子どもが直面しているバリアを見つめます。そのために、子どもの視点、支援する側の視点という2つの観点から考えを深めあいます。社会が抱える問題として子どもを見つめることによって、子どもが社会から孤立されることなく秘められた可能性をいかに引き出せるか、みんなで考え創作しましょう!
人ト この分科会ができた経緯を教えてください。
葵さん できた理由としては、そもそもニーズがあったからです。もともと世の中に子どもに関するボランティアが多くあるので。
あと、世田谷には子どもを支援する施設やNPOが充実しているので、それを活かせるのではないかなと思ったのも発案の経緯の1つです。
人ト 世田谷に、「子どもを支援する施設などが多い」というのは私自身もねつせた!で活動する中で感じられたのですが、やはりほかの地域よりも多いですか?
葵さん 自分で実感できているというわけではないのですが…でも、そもそもまず自分のまちのこういった支援を知る機会が少ないじゃないですか。なので自分のまちの活動を知る機会にもなればいいなと思います。
人ト 情報も広めていきたい!という気持ちもあるのですね!
葵さん そうですね、教育とか子どもの支援に力を入れているということもこの分科会を発足したという1つの理由ですね。
人ト どうして葵さんは「子ども」の分科会に携わろうと思ったのですか?
葵さん もともと教育や教育格差に興味があったからです。教育とか子どもとかって、自分自身もまだ子どもですし、教育を受けている身としては身近だと思っていて、身近だからこそ疑問に思うこともあったりするんですよね。
その時に、ボランティアを1つの手段として課題解決につなげていけるんじゃないかなと思っています。
人ト 葵さんは今までに子どもと関わるボランティアをされてきたんですか?
葵さん 「おりがみ」という学生団体に所属しています。その団体は6つのチームに分かれていて、その6つの視点の中の一つに「教育」があって、私はそこで活動をしています。
やっていることとしては、子どもの成長を助けること。
子どもを助けるというよりかは、子どもの成長を見守るという感じですかね。
具体的な活動としては、千葉県の中高生を対象に「おもてなし隊」という千葉でおもてなしをする方法を中高生と一緒に立案して、それを実行するということをしています。
人ト 一方的に大学生側が全部やるというのではなくて、中高生と「一緒にやっていく」のが大事なんですね。
葵さん そうですね、それが私たち大学生の良さだと思っているんです。
今回の分科会との共通項にもなりますが、学生って大人と子どもの中間だと思うんです。
その良さをいかに活かすか、「学生だからこそできること」、「大学生だからこそできること」を見つけて、それを活動に反映させていこうと努力しています。
人ト 正直、企画を考える中で難しさを感じる場面はありますか?
葵さん 感じるんですけど、でも今のこの未熟な自分だからこそ、子どもを引っ張ってあげるのではなくて、「一緒にいこう」「一緒に悩もう」っていう提案ができたらベストかな…と思って頑張っています!
人ト 特にすごい知識持ってるわけではないけど、ちょっとだけ歳上っていう存在ですよね!
チラシの文中に「子どもが直面しているバリア」とあるのですが、具体的に葵さんはどんなことが想像されますか?
葵さん 今挙げているのは、貧困とか不登校を挙げています。
人ト そういったものを「子ども」と一緒に考えたいな、ということですか?
葵さん はい、その問題を分科会の中ではワークを通して「子どもの視点」と「大人の視点」を得られたり、それぞれの視点からその問題を視るということができたらと思っています。
そこから「じゃあ学生には何ができるか」というのを最終的に提示できたらと思って、設計しています。
人ト 分科会にどんな人が来てくれたらうれしいですか?
葵さん ターゲットとしては、「なんとなく子どもに興味がある」「子どもの問題に関心がある」という方にも気軽に来てほしいですし、すでに活動をされている方にもこの視点は大事だと思うので、どちらの人も補える分科会になったらいいなと思っています。
そして来てくれた人たちが、課題に対して私たち学生が関わるメリットや、「じゃあ実際に何ができるか」を最終的に持って帰って、さらにこれから子どもボランティアに参加するという1歩になればなという風に思っています。
人ト 最後に来てくれる人に伝えたいメッセージをお願いします!
葵さん 学術的なスキルや知識は必要ないので、気軽に来てほしいなと思ってます!
自分で言うのも何ですが、すごく楽しいし、いい雰囲気で分科会を進められそうなので期待していてください!
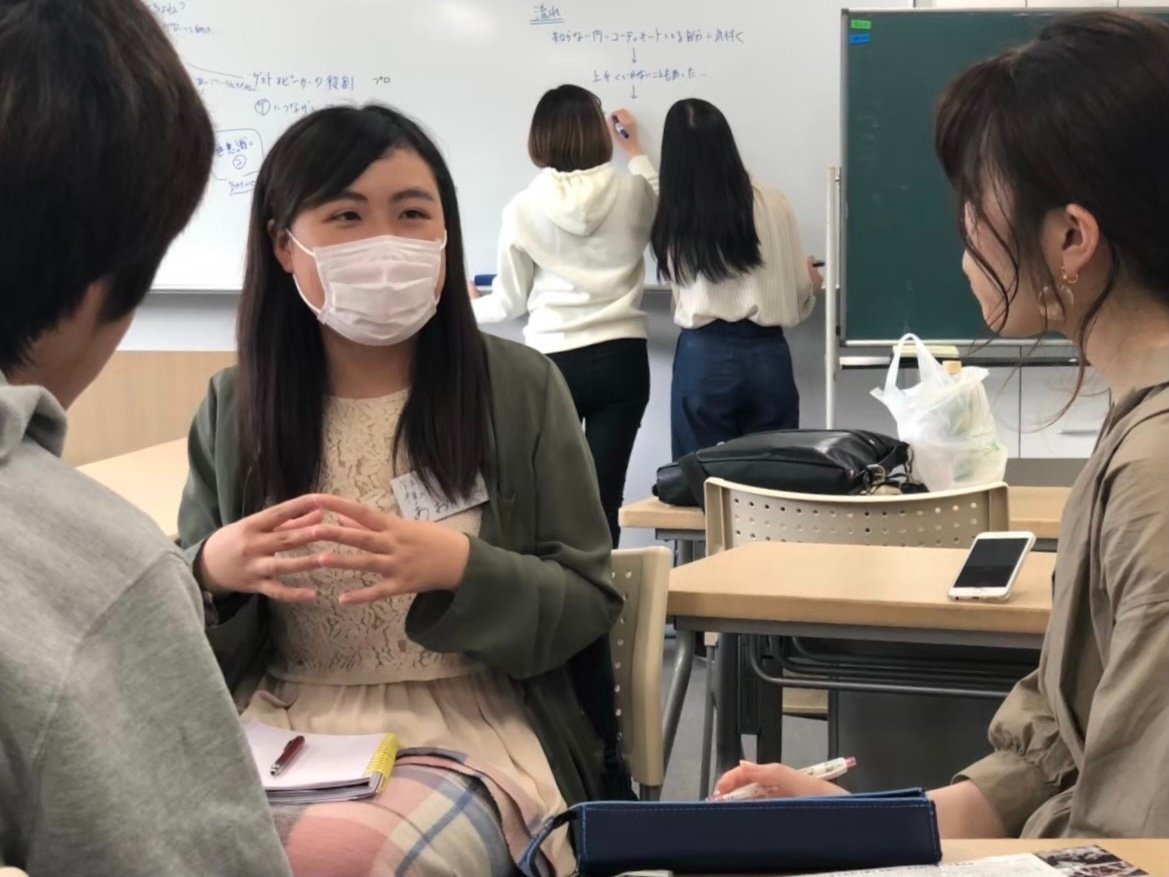
インタビューを終えて
葵さんをはじめ、「子ども」分科会が大切にしている「子ども」と「大人」の2つの目線。子どもと大人の狭間にいるような学生の私たち。だからこそ見えてくる不安や生み出せる可能性があって、それがもしかしたら誰かの力になるのかもしれない、そんな風にこの取材を通して感じることができました。
ぜひこの「子ども」分科会で「一緒に」考えてみませんか??
(人ト)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
