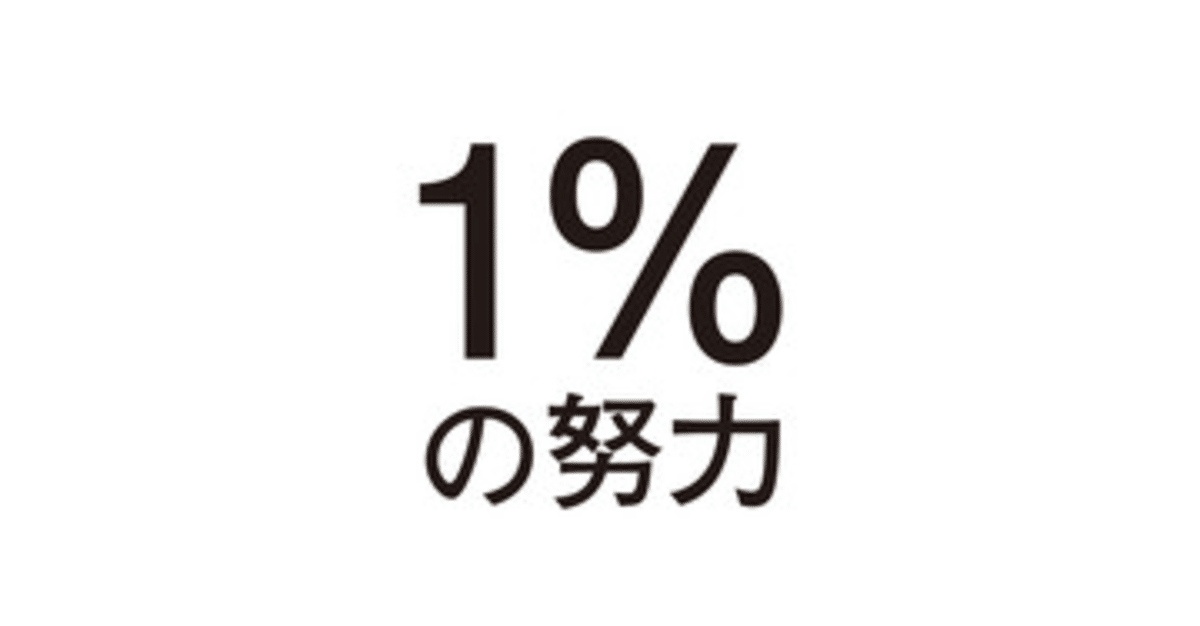
徹頭徹尾、弱者に向けた弱者の為の「生きる力」教本! ひろゆき著「1%の努力」を橘玲の著作を基に紐解く
多くの自己啓発本についてあらかじめ前提としておくべき認識
現在、数多くの自己啓発本が出版されている。社会の底が抜けたことで、とにかく勝ち抜けたいと思う人たちがそれだけ多いのだろう。中でも注目を浴びるのはやはり成功をおさめたひとの本や、インフルエンサーと呼ばれる主にSNSでの影響力を持っているひとの本などである。
内容も様々で、ビジネスでバリバリ稼いでいくひとのための本もあれば、変な生き方しているひとの、レールから外れた生き方の勧めみたいなものまである。ぼくはこういった自己啓発本を読むのが趣味なので、気になるひとの出した本は読むことにしている。
しかし、その本を読んだからといって自分がそのひとのようになれるとは微塵も思っていないし、実際、誰であれそのひとみたいにはなることはできない。その辺りの理由はこちらの記事で詳しく書いた。
知能や努力できる資質すら不平等な世界
まず、この本でひろゆきは「『頑張ればなんとかなる』と思っている人は、甘い」と喝破する。これは努力すら平等ではないという残酷な現実がベースとなっている発言だ。
分子遺伝学、脳科学、統計解析など、最新科学が解き明かしたあまり耳障りのよくない話を橘玲がまとめた『もっと言ってはいけない』という著作がある。この中で人間の知能や能力の遺伝についてエビデンスを提示した上で、実に嫌な事実が取り上げられている。
親が背が高いとその子供も背が高くなるというのはなんとなく感覚的に理解されているひとも多いと思う。これが遺伝というもので、外見的性質は約50%の確率で遺伝するといわれている。だから背が高い親からは約半分の確率で背が高い子供が生まれるというわけだ。
ただ、知能に関しては遺伝すると考えるひとはあまりいない。そう考えないのは生まれで差別しないといった倫理観が大きく働いていたり、最近では、それは本人の努力次第でいかにでも覆せるという「自己責任論」とも結びついているからだろう。しかしながら、実は知能も遺伝するどころか、外見的素質より遥かに高い確率で遺伝するということが最新の科学では判明している。具体的には、環境や努力でどうにかなるのは約11歳までで、30、40代と中年に差し掛かると、親からの知能の遺伝率はなんと驚くべき80%になるという。
しかし、これは長く生きていると実感しないだろうか。子供の頃は簡単に勉強できたのに、歳をとってきてから物覚えが悪くなってきたとか。それは本来の遺伝的知能レベルに戻ってきているだけなのだ。なので同じ努力をしても歳をとるにつれ、結果が伴わないことも多い。そもそも努力を継続するという事すら危うくなってくる。本人の気合いや根性ではどうにもならないことも多い。後天的な教育が持つのはせいぜい二十歳頃までといわれているので、新卒一括採用でつまずくと知能指数のあまり良くない親から生まれた子供の挽回は中々難しくなる。氷河期世代の問題はそこにある。また、若いひとが言っていることを中年以降が真似しようとしても、体力以前に知能が落ちていて真似する事すらできなくなっていたりするのだ。
スマホと財布を置いて出かけ、家族を頼らず1週間生きられるか?
このように世の中には遺伝や生まれた世代によって努力ではどうにもならない壁が残酷なまでに存在する。しかし、見方を変えて違うところにちょっとだけの努力を注いでいけば、弱者でも楽しく生きていくことができる。それを説いているのがこの『1%の努力』なのだ。
ひろゆきみたいになる本ではなく、数多くの弱者を観察してきたひろゆきが、そういった人たちでもどうすれば楽に生きることができるか、ひろゆき自身の経験も踏まえた上でそういったものが徹頭徹尾書かれている。
冒頭でこのような文章がある。
「努力が大事だ」と思っている人に、ぜひ、やってみてほしいことがある。スマホと財布を家に置いて、外に出てみよう。そして、1週間、過ごしてみる。ただし、家族に頼るのはNGだ。1週間後、キレイな服で、お腹も満たされて、何事もなかったかのように帰ってくることはできるだろうか。それができる人は、この本を読む必要はない。
これはまさに地頭の良さがあるかどうかを問う質問だ。いざレールから外れた時に自力で解決できるならこの本を必要とする弱者ではないということである。
エッグスタンドは必要かどうか?
本書はひろゆきが幼少期に育った赤羽時代の話からはじまるが、そこには大きな桐ヶ丘団地があった。家賃が破格的に安いその団地には貧困層が住んでおり、生活保護を受けているひと、借金に追われているひと、今で言うニート、子供部屋おじさん、引きこもり、母子家庭などが当たり前に周りにいる環境だったそうだ。
そういう環境で育ってきたひろゆきにとって、大人になってから「卵のためだけ」にしか使えないエッグスタンドの存在や、それを当たり前のように語る人にカルチャーショックを受けたという。
別に卵を置くのなんてどんな皿でもいい。問題なのは、世の中にはそんなものを買う「余裕」がある家が存在するという事だ。しかし、逆に言えば「そもそもエッグスタンドなんて、いらなくないか?」と考えることもできる。そしてそれこそが人生の様々なできごとを内省する際に役に立つ考え方なのだ。
例えば、なんかオシャレだからとか、流行っているからと、つい無駄なものを買ってしまってはいないだろうか。資本主義社会では巧みな広告戦略が展開され、それこそぼくを含めた頭の悪い人たちにいかに物を買わせるかの騙し合いが行われているといってもいい。しかし、「それらはエッグスタンドではないか?」と考えてみると、冷静に自分には必要のないものだと理解することができる。
また、SNSなどにより誰かと比較される機会が格段に増えた。華やかでリッチな人たちの生活と今の自分の生活をつい比べてはいないだろうか?だがこれも同様に、ファーストクラスでの移動や庭付きの大きな家もセレブなパーティーもブランド物も「所詮はエッグスタンドだ」と考えれば、無駄に劣等感を抱くこともない。そういう時にこの言葉に立ち戻って考えてみてほしいとひろゆきは語る。
弱者の論理
橘玲の本のデータに戻るが、人種でも知能指数に差が現れる。アジア系が一番高く、黒人が一番下にくる。だから多人種国家で単純な知能テストで難関大学の合格者を決めてしまうとアジア系だらけになるので、アメリカなどでは人種による枠が決められていたりする。
男女間においては知能指数に差はないが分布が大きく異なる。男性は下も上も多く、女性は中央値が一番多い。つまり男はバカか天才が多い傾向にあり、女はふつうのひとが多い傾向にある。
犯罪率が男の方が高いのもそういうところからであるし、実は知能に関して言えば女より男の方が弱者数は多いのである。ただ高い知能も多いのでそれに隠されて弱者男性は見えにくいだけなのだ。
このように知能指数も人種や性別でばらつきがある。なので機会が平等であれテストが平等であれ、こぼれ落ちるひとは必ず決まってしまう。境界線をどこで引くのが正しいのかわからない。だからこそ、民主国家は国民であればどんな人間であれ、基本的人権と尊厳が保障されているのだ。
ひろゆきは言う。「人は権利を守る生き物だ」と。都内の一等地にボロボロの都営団地が残されており、そこに生活しているひとたちは格安の家賃で生活している。あれを既得権益だと批判するひとがいるが、追い出されると、たちまち生活ができなくなってしまう人たちも多い。だから彼らは「一生この団地に住むぞ」という覚悟がある。覚悟を決めたひとはしぶとく生きていける。
弱者は権利を破壊する側ではない。基本的人権を盾に、受けられる権利は全て享受すべきなのだ。その権利を守りながら、既得権益を壊そうとする動きがあれば、逃げられるようにしておくことが重要である。弱者には弱者の生存方法がある。この本はそういう類の考え方や知恵を授けてくれるものだ。
もちろん、チャレンジや努力するのも自由だ。問題は自分で選択することが重要なのである。本当はそんなにチャレンジするのが好きじゃない、むしろ苦痛を感じているのにチャレンジすることがあまりに美化されていて、それに流されていないか。自分が本当に望む生き方は違うのではないか。そんなことも考えさせてもくれる。
自己啓発本というと、基本的にチャレンジすることや努力するための考え方が書かれているので、この本は異色でそれだけでも面白いし、弱者のための生き方本なので再現性がかなり高い。また、ひろゆきが不遇な氷河期世代として生まれ(ぼく自身も氷河期世代だ笑)、数々のこぼれ落ちていく弱者を見てきた、または友人の経験談などがあるので、なにより説得力があるのだ。
「そういうことになってしまった」と、その状態を受け入れるしかない
実際、「あなたが努力してもどうにもならないですよ」とか身も蓋もない話は受けが悪い。多分このレビューもそんなに読まれないだろう。でも自分が弱者に落ちた時には役に立つ考え方なので、今はそうではないひとでも頭の片隅に入れておくといいと思う。
ぼくの中では、ひろゆきが赤羽の団地時代の友人とニコニコ超会議で再会して話すエピソードが印象的だった。
話を聞いてみると、うつ病になっているようで、やる気が湧かないから家でずっとごろごろしているそうだ。新しいことをしようという考えにいたらない。いつものルーティンワークはできても、それ以外の行動をしようとすると、心理的にコストが高くなる。ちょっと外に出たり、人に電話をかけるだけでも体力を使う。パソコンに詳しくないうちにそんな状態になったら、パソコンの操作の習得から、プロバイダとの契約まで、1つ1つの行動のハードルが高くなってしまう。〈中略〉「そういうことになってしまった」と、その状態を受け入れるしかない。
ぼくもこの一年で様々なことがあり、ひとつのタスクこなすだけでも疲れてしまうような精神疾患弱者に転落したから、このひろゆきの友人の気持ちがわかる。ひとはいとも簡単に突然そうなるということを身をもって知った。
しかし、原因はなんであれ、「そういうことになってしまった」と、その状態を受け入れるしかないのだ。そしてぼくも弱者の論理で様々な権利を獲得していった。この本はそんなぼくのやってきた事を後押ししてくれたし、新しい知見も与えてくれた。
不安定な時代だからこそ、身につけておきたい知恵だと思う。ひろゆきの著作はこれまで何冊も読んでいるが一番心に響いた。良書。
もし面白く感じたのなら100円でもサポートしていただけると、今後の励みになります!
