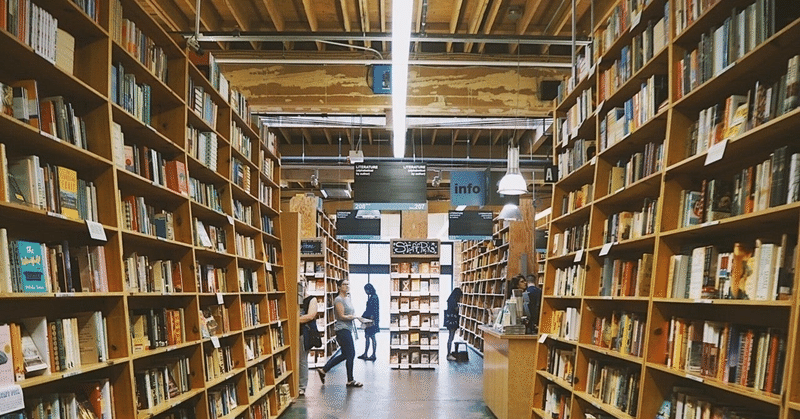
サッカー本ベストイレブンを選んでみよう
1.自分でベストイレブンを作ってみよう
僕はサッカーと読書が好きだ。これらの趣味は僕にとっては両親の次に付き合いが長い。必然としてサッカーに関する本、いわば「サッカー本」も好きになる。自分の好みや興味は当然あるので一切読まないサッカー本も多いが、それでもそれなりの数は読んできたつもりだ。
以前、ベナTさんが自身の読んだサッカー本でベストイレブンを組んだ記事を発表していた。今回の記事は「じゃあそれを自分もやってみよう!」という企画である。
2.選考基準
11冊選ぶ際には以下の4点を判断材料にした。結局自分の尺度だし、他人に細かい感覚が理解されるわけではないが記しておく。
(1)読んだ当時のインパクト
今読んでおもしろいかは関係ない。読んだ当時、鮮烈な印象が残っていたらその感覚を大事にしたつもりだ。おもしろいと思うかどうかは自分の年齢によって変わるので、どうしても選んだ時のマイブームに左右される可能性があるからだ。
(2)他ジャンルと戦える強度がある
他ジャンルの本と競争させても読者をうならせられる質だと僕が思う本は優先して選出した。言い換えれば「サッカーに興味がない人でも面白いを言わせられる」本だ。
(3)歴史的意義
今になって振り返るとすごく貴重な本であったり、その後のサッカー本の流れを作ったりなど、サッカー史あるいはサッカー本の歴史の中で大きな意味を持ちそうかも基準にしている。ただしあくまで僕の好みでの目線であることを留意してほしい。
(4)おもしろいかどうか
単純明快。(1)~(3)の基準で迷ったら自分がおもしろいと思ったほうを選んだ。
3.ベストイレブンはこれだ!
ではここからベストイレブンを発表していく。ポジションやフォーメーションはまったく考えておらず、単純に自分が読んだ順に並べているだけだ。みなさんが読んだことある本はどれだけあるだろうか。
チュックダン!(河崎三行)
かつて日本にどんな大会にも出ることができないのに最強を欲しいままにしたサッカークラブがあった。それが在日朝鮮人で構成された在日朝鮮蹴球団である。現在東京で活動するFCコリアの前身だ。
在日朝鮮蹴球団の発足から消滅までを追った本である。決して歴史に名前が刻まれない彼らは何のために走り続けたのか、なぜ最強と呼ばれたのかがひも解かれる。
僕が小学生のころ読んで衝撃を受けた本のひとつだ。「在日朝鮮人」という存在をはじめて認識したし、日本人が誰一人いないサッカークラブが日本にあったことにも驚いた。
秘められた歴史を掘り下げる本は、今でもずっと僕の好みなのだが、そのきっかけを作った一冊である。また、サッカーを通して社会や世界と繋がり、学ぶことができる面白さを感じさせてくれ、サッカーの奥深さに幼いながら魅了された。
河崎さんは非常に寡作で、本も記事もほとんど出てこない。しかし稀に世に出る文章はどれも素晴らしいものである。彼の書いた『蹴る女』もぜひ読んでほしい。
【追加でもう一冊】木村元彦『無冠、されど至強』
日本サッカー史(後藤健生)
サッカー日本代表が活動をはじめた1917年から2006年ドイツW杯までの日本代表の歴史が書かれている。あらゆる資料をもとにした緻密な記述がうりだ。
歴史が大好きだった小学生の僕は興奮しながら読んだ。自分が愛してやまない日本のサッカーにはこんな長い歴史があり、その上に自分はいまJリーグや代表戦を楽しんでいるのかと。僕が生まれる前に活躍していた日本のサッカー選手を名前だけやたら知っているのはこの本のおかげである。
僕は将来的に日本のサッカー史は、1993年を境に断絶する可能性があるとみている。Jリーグが開幕した1993年以降は知名度も関心もあがり、資料も豊富だし、歴史をまとめた記事や本もまだ世にでやすい。しかし1993年以前はサッカーへの関心がみな低く、その時代を振り返った記事や本に需要がない。そのため後世に1993年以前の日本サッカー史がこれ以上詳しく残ることも、残そうとする活動が出てくることも困難だと思っている。
だからこそこの本の意義が際立つ。おそらく現代ならこの本の企画は需要薄とみなされて出版できなかった可能性がある。また、今のサッカーメディアの中堅以下の書き手に歴史を体系的に叙述できる人はいるのだろうか。改めて考えると、これは後藤さんにしかできない仕事であった。
【追加でもう一冊】下園昌記『ジャポネス・ガランチード』
※僕が読んだものは初版版(2002年W杯まで)ですが、のちに改訂版がでたのでそちらのリンクを貼りました。
股旅フットボール(宇都宮徹壱)
僕が中学生時代に読書感想文の宿題で最高評価をもらった思い出の一冊である。おかげで僕は国語の評定が最高点だったかもしれない。
地域リーグに所属しておりJリーグを目指すと宣言していたクラブたちを
取材した本だ。僕は地元のコンサドーレ札幌を応援していた。コンサドーレはJFLとJリーグしか参加したことがないので、地域リーグまで僕の視界には入っていなかった。そんな僕の視野を広げてくれたのがこの本だ。
この本で取り上げられているクラブの一部を挙げてみる。グルージャ盛岡、V・ファーレン長崎、ファジアーノ岡山、ツエーゲン金沢、カマタマーレ讃岐、FC岐阜、FC町田ゼルビア。共通点があることに気がついただろうか。そう、現在はJリーグにいるクラブである。
つまりこの本は今読むと、いくつかのJクラブがJリーグに入るまでの前史を書いたものなのだ。Jリーグに入る前と後ではクラブに関わる人数がかなり違う。そのため、Jリーグにはいる前の歴史をたどるには証言者も資料も圧倒的に足りない。また、Jリーグに上がるまでにはいろんな困難やトラブルもあり、その思い出を後世に残したくないクラブもあるだろう。
出版された当時は「誰も知らない地域リーグの過酷さ、夢とリアル」を伝える本だったが、現在は「Jクラブの秘められた前史を伝承する歴史書」に変貌したのだ。だからこの本は今読んでもまったく古びない。
宇都宮さんの本は、当時を切り取ったものが多いのに今読んでも色あせた感じがまったくしない。だからこそサッカーメディアの一線で活躍し続けられるし、本も出版できるのだと思う。「昔読んでも、今読んでもおもしろい」は偉大な書き手であることを証明する。
【追加でもう一冊】宇都宮徹壱『フットボール風土記』
監督ザッケローニの本質(片野道郎、アントニオ・フィンコ)
2010年に日本代表の監督に就任したザッケローニ。彼の監督生活のはじまりから日本代表監督就任直前のユベントス監督時代までを、多くの関係者の証言とともにたどった本である。
カルチョが大好きな僕はザッケローニの就任を興奮でむかえた。しかし彼に関する知識をあまり持ち合わせていなかった。この本はザッケローニがどんな仕事を積み重ね、どんな人物で、どんなサッカーを志し続けているのかが濃厚に詰まっている。
シーズン毎にザッケローニの仕事ぶりを詳しく記述していることはもちろん素晴らしいが、何より彼に対する証言を寄せた人々がすごい。家族や腹心のコーチをはじめ、指導した選手、雇った会長やSD、しのぎを削った先輩監督、そして最後はザッケローニ本人に、一コメントではなく詳細な証言を全員から引き出している。
一人の監督の生き様を読むことははじめてだった。僕が「サッカー監督」という生き物に深く興味を持つようになり、現在もその興味が続いているのはこの本のおかげである。
今振り返ると、監督の自伝や評伝はこの後も出版されている。しかしこの本のように各クラブの仕事ぶりを詳細に解説し、多くの関係者のインタビューを載せた構成の監督本は見たことない。制作が難しいのかもしれないが、非常にもったいない。
片野さんは、日本人最高のサッカージャーナリストの一人だと僕はずっと思っている。どんなサッカー本だろうと彼が関わった本は必ず手に取る。願わくばこの『監督ザッケローニの本質』のように監督にスポットを当てたドキュメンタリーのような本をもう一度手がけてほしい。
【追加でもう一冊】片野道郎『モウリーニョの流儀』
英国のダービーマッチ(ダグラス・ビーティ)
「ダービー」は、世界中のサッカーを彩るには欠かせないお祭り、いや、闘争である。この本は、著者が実際にイギリス8都市をめぐり、その都市のダービーについて多面的な角度から取材したものだ。
本では、実際にダービーを観戦しにいったレポートだけではなく、クラブや都市の歴史にも踏み込んでダービーを表現している。
ダービーのおもしろさを考えたらキリがない。一つあげるとするならばサッカーというジャンルを越えて、都市の文化や歴史と密接につながるところが僕は魅力に感じる。加えて、本来は都市の歴史に由来する因縁だったものが、ダービーの歴史を積み重ねるにつれ、都市の対立の歴史がクラブ同士の対立の歴史に乗っ取られていくところも興味深い。
僕はサッカーがサッカーの枠にとどまらず、様々なジャンルと密接に関わりを持つものであることに幼いころから虜になっていた。この本は改めて「サッカーってこういうとこが最高なんだよな……!」と思わせてくれる。
あまりの面白さに「これはサッカーの本ではなく、イギリスの文化と歴史を学べる本だ」と図書館司書を説得してこの本を高校の図書館に入れてもらったのはいい思い出だ。
【追加でもう一冊】アンディ・ミラン『ダービー!!』
通訳日記(矢野大輔)
ザッケローニが日本代表監督をしていた際の通訳である著者が監督就任から退任までつけていた日記を公開するという形で出版された本である。元々Numberで連載されていたのだが、連載がはじまったときは衝撃だった。同じ感覚を持った人はきっといたのではないだろうか。
別にスキャンダラスなことが書かれているわけではないし、誰かを悪者にした告白本でもない。しかし、ザッケローニが何を語り、どの選手とどんな対話をし、どんな選手に期待をかけ、何を悩んだかが赤裸々に書かれている。誰もスケープゴートにしていないからこそ生々しさが増している。
何も扇動せず日記をただ公開だけなのにどんな暴露よりも重い「暴露本」になっている。これを公開した著者の勇気もすごいが、手がけた文藝春秋のすごさも強調したい。文藝春秋はもう一冊怪物的なスポーツ本をのちに出版する。落合博満を書いた『嫌われた監督』だ。こちらが出たとき僕は「本というのは著者と編集者の合作だ」と思い、その先駆的存在である『通訳日記』を再び思い出した。
著者はこの本を発表後、サッカー界からは姿を消し、現在は別の業界にいると数年前のインタビューで読んだ。ザッケローニからも監督になってほしいと言われていた彼がなぜサッカー業界から消えたのか。因果があるかはわからないが、その事実につい僕は『通訳日記』が世に出た重さを考えてしまうのである。
【追加でもう一冊】ローラン・ジャウィ、リオネル・ロッソ『ハリルホジッチ勝利のスパイラル』
砕かれたハリルホジッチ・プラン(五百蔵容)
2018年4月、ロシアW杯を前に日本サッカー協会は衝撃の決断を下した。ハリルホジッチ日本代表監督の解任である。この本は、日本代表でのハリルホジッチの仕事ぶりを振り返り、ロシアでどのような戦い方をしてどれほど通じるものだったのか推測した上で「日本サッカーにおけるハリルホジッチとは何だったのか」を一冊にまとめたものだ。
内容はおもしろい。おもしろいがリアルタイムで見てた人間にはおもしろいかもしれないが、このハリルホジッチ時代を知らない人間が読んでもぽかーんとするかもしれない。ではなぜベストイレブンに僕が選んだのか。
それは第6章の「「ボールゲーム」としてのサッカーを解釈する」が出色の出来だからだ。戦術を分析したり解説したサッカー本は、以前から数多く出てきた。もちろん分かりやすい本もある。しかしこの章では「そもそもサッカーとはどういうゲームなのか」という根底の部分を丁寧に定義していくのだ。
「サッカーって何?どんな特徴があって、その特徴のせいでこんな場面が出てきたり、あんな戦術が生まれるんだよ」
こういった原点のところから解説して戦術分析につなげた本を僕ははじめて読んだ。僕自身「サッカーとはどんなゲームか」をしっかり考えたことがなかったこともあり、あらゆる戦術本の中で一番衝撃が大きかった本である。
五百蔵さんは他の本や記事でも「そもそもこれって何?」という根底の部分から論考を進めたり、過去の采配や昔の戦術などをひも解いいた上での今のサッカーをその歴史の流れの文脈において解説している。この歴史の文脈を大切にするアプローチも非常に僕は好みだ。
【追加でもう一冊】五百蔵容『森保ストラテジー』
東欧サッカークロニクル(長束恭行)
東ヨーロッパを中心とした諸国のサッカー事情を著者が取材した記事をまとめた本である。いわば東欧をテーマとした短編集だ。長束さんはクロアチアを中心とした旧ユーゴスラビア諸国のサッカーに非常に詳しい書き手である。
僕が「短編集」と称したように一冊のまとまりは実は薄く「東欧」というくくりでしか束ねられていない。著者の今までの仕事をまとめたポートフォリオにも思える。しかしこの本には他のサッカー本の追随を許さない圧倒的面白さを誇る箇所があり、それが今回僕がベストイレブンに選出した理由である。
それが著者がヨーロッパ中にその凶悪ぶりで名をはせるディナモ・ザグレブのサポーターグループ「BBB」に同行して、CL予選を戦うべく沿ドニエストルへ遠征したエピソードである。
沿ドニエストルはモルドバの一地域でありながら、モルドバからの独立を目指し、本国の支配の及ばない「沿ドニエストル共和国」という未承認国家が存在している謎の地域だ。
普段、足を踏み入れることもない正体不明の地域。そこに向かうはヨーロッパ屈指の荒くれ者サポーターの集団。そこに同行する一人の日本人。何かが起こらないわけがない。こんなにわくわくするシチュエーションはないだろう。
このエピソードを読んで僕は真っ先に浮かんだ本が、高野秀行『謎の独立国家ソマリランド』である。高野さんは、あらゆる本で日本人が誰もいかないような地域に行ったり、考えもしない切り口で世界中を描写する。長束さんは、高野さんのような視点の文章を「サッカー」の文脈で完成させた。これは日本で出版されるサッカー本では類を見ない。
『東欧サッカークロニクル』を読んで確信した。間違いない。長束恭行は、「サッカー界の高野秀行」だったのだ。
※なお高野秀行さんご自身もサッカーに関心があることをSNSでちょいちょいほのめかしている。
【追加でもう一冊】長束恭行『もえるバトレニ』
監督の異常な愛情(ひぐらしひなつ)
著者が番記者として関わった監督あるいは対戦相手の監督を5人取り上げて、彼らの監督手腕や生き様にせまった本だ。
この本が珍しかったのは取り上げられている監督がトップクラスの成績をおさめた人たちではないことだ。もちろんJクラブの監督になれる時点で一流ではあるのだが、基本サッカー監督を扱う本の多くは、育成年代の指導者を除くと1部リーグでの優勝経験がある監督を主役とする。いわばいぶし銀のプロクラブ監督が主役になるのはめったにないのだ。
そんな5人のいぶし銀を集めた本書は、著者による監督たちへの入れ込み具合と言葉を引き出す力に支えられている。著者の文章は彼らへの愛にあふれている。監督としての技術やあり方、人としての生き方の本質を突いた言葉の数々が読者のサッカー観はもちろん、人生観にも影響を与えるに違いない。
ビッグクラブを率いる能力と中小クラブを率いる能力は別物ではないかと僕は思っている。ビッグクラブに向いた監督もいれば、中小クラブに向いた監督もいる。時にはどちらを率いても結果を出す超人もいる。
そして世界にはビッグクラブよりも中小クラブの方が多い。だとすれば中小クラブの監督の悲喜こもごもや生き様は、実は多くの人の共感を呼ぶのではないだろうか。ターゲット層が小さいことから実現は難しいだろうが多様なタイプの監督が多くの本で取り上げられてほしい。
【追加でもう一冊】ひぐらしひなつ『サッカー監督の決断と采配』
サッカー戦術の歴史(ジョナサン・ウィルソン)
僕が紹介するまでもなく文句の言いようがない名著、大著である。サッカーというスポーツが誕生してから2007年ごろまでのサッカー戦術の歴史を記述したものだ。
あらゆる歴史を学んでいると「歴史は繰り返す」という言葉が頭に何度も浮かんでくる。それは決してまったく同じ出来事が起こるという意味ではない。出来事や結果は違えども、同じような考え方や物事の構造が現れることをいう。
サッカーの戦術でも「歴史は繰り返す」が存在することをこの本は証明している。もちろんサッカーは日々進歩しており、プレースピードや強度はどんどん上がっている。それなのに戦術の思考や構造は実は何度もリバイバルされているのだ。
この本は、戦術を勉強する上ではもちろん重要な一冊だ。だがそれ以上に、サッカーにおいて歴史の背景や文脈に沿って考えることがいかに重要かを証明してくれた。別に戦術だけの話ではない。クラブの歴史だってそうだ。誰かに歴史を学ぶことは強要できない。しかし歴史を知らなければ、なぜ今があるのかは永遠と分からないし、自分たちにとって本当に大事なものはきっと見えない。
【追加でもう一冊】マイケル・コックス『プレミアリーグサッカー戦術進化論』
ディス・イズ・ザ・デイ(津村記久子)
日本にある架空のサッカー2部リーグに属する各クラブのサポーターの最終節を切り取ったオムニバス小説である。サッカーのサポだけでなく、なにかを応援する、推している人たちも共感すること間違いない。
この本は色々とびっくりする要素が多かった。そもそもサッカーを題材にした小説が珍しい。スポーツを題材にした小説を書く大物作家である堂場瞬一さんや池井戸潤さんもサッカーは一切題材にしたことがない。
そしてサッカーのサポーター(ファン)を題材にしたことも驚きである。サポーターに焦点を当てたサッカー本は何冊か日本でも出版されるが、日本を舞台にした小説がなかったのではないか。それも朝日新聞の連載小説である。いったい何があった。
野沢尚『龍時』や村上龍『悪魔のパス天使ゴール』といった選手を題材した名サッカー小説はある。日本代表監督探しをモチーフにした本城雅人『誉れ高き勇敢なブルーよ』もなかなか良作だ。しかしまさか芥川賞作家がサポーターを題材に小説をかかれる時代になるとは。日本のサッカー文化が新たなステージに登ったことを感じさせた。
【追加でもう一冊】乗代雄介『旅する練習』
4.おわりに
以上、ベストイレブンを選んで書き散らしてみた。振り返ると僕の思い出をかなり反映させたラインナップになった。日本に出回るサッカー本のすべてを読んでいるわけではないので漏れはいくらでもあるはずだ。特に選手本はめったに読まないので、案の定選出されることがなかった。反対に監督がらみの本はよく読むので選ばれやすくなったかもしれない。
冒頭に紹介したベナTさんの記事と読み比べてみると非常におもしろい。それぞれがサッカーのどういうところに興味や関心を抱き続けているのか、共通点と相違点がはっきりわかる。読書は自分を映す鏡なのだ。
この記事が誰かの読書欲をかきたてたり、選書の参考になればこんなにうれしいことはない。また、サッカー本じゃなくてもかまわない。みなさんも読んだ本で思い思いのベストイレブンを作っていただけたら幸いだ。
本の購入費に使わせていただきます。読書で得た知識や気づきをまたnoteに還元していきます!サポートよろしくお願いいたします。
