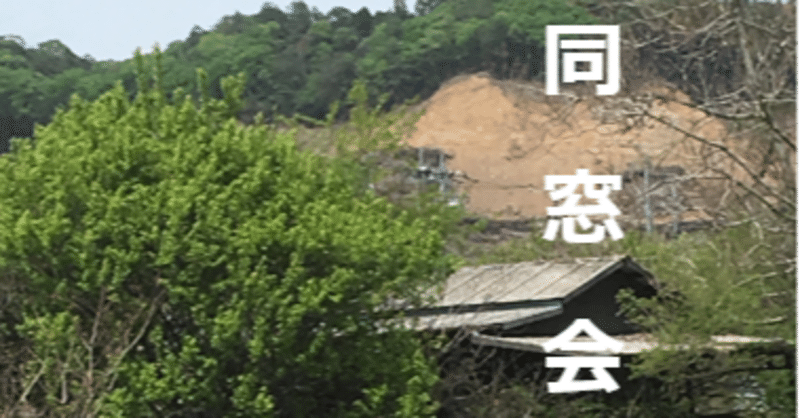
同窓会
神山由美子は、今中学校の同窓会に向かうために故郷へと向かう夜行列車に乗っている。彼女は車内で窓で服をチェックしたり、手鏡でメイクを何度もし直したりした。そしてその間中ずっと久しぶりに会う同級生にどう声をかけようかとずっと考えていた。
由美子が最後に中学校の同窓会に出たのは高校三年の時である。それから彼女は大学に進学するために東京に上京したが、それ以降同窓会に出ることはなかった。
東京の自宅にも毎年同窓会の案内状は来ていたが由美子は毎回封も開けずそのままゴミ箱に捨てていた。彼女はすっかり東京に染まって田舎を猿みたいな連中しかいないと軽蔑する様になっていたからだった。だから田舎には決して帰らず、ときたまTVで田舎のニュースが流れるとすぐチャンネルを変える有様だった。当然訛り放題の友達も軽蔑する様になり、手紙の類がきても完全に無視していた。一時期港区に実家を持った会社の社長の息子と付き合ってた頃などは出身地さえごまかしていた程だ。
そんな由美子が何故それほど軽蔑している同窓会に出ようと思ったのか。一言で言えば彼女が歳をとったと言うことだろう。美人であった彼女はたくさんの男達を取っ替え引っ替え遊んでいたが、やがて由美子が歳を取ると男達は一斉に彼女から離れていった。プライドの高い彼女には友達は少なく、やがてその友達も続々と結婚し独身は彼女一人だけになってしまい、それと同時に友達とも疎遠になっていった。職場で彼女は若い女性社員にバカにされ、一度などトイレの前で「あのクソババアなにあの格好!時代間違えてるよね!」とか思いっきり陰口を叩かれた事もある。30半ばになり、友達もなく、若い女にはバカにされ、孤独に打ちのめされたそんな時、同窓会の案内状が届いたのであった。
郵便物の中から案内状を見つけたとき、由美子はいつものように捨てようかと思った。しかし手書きで書かれた自分への宛名を見た瞬間、急に懐かしいものがこみ上げてきたのだった。差出人には猿ヶ丘中学校卒業生一同と書かれている。彼女は封を開けて中の手紙を読み終えた瞬間、声を上げてその場で泣き伏した。
手紙にはこう書いてあった。
ゆみっぺへ
東京での生活どうですか。みんな連絡がないから心配してます。こっちは相変わらず元気にやってます。だけど村がとなりの犬猿市に統合されちゃってから村は寂れていく一方で、私たちの猿ヶ丘中学校も新入生が一人になったそうで再来年には廃校になってしまいそうです。人が減ったせいで電線の工事も疎かになり、インターネットもスマホもろくに使えなくなりました。なんだか原始時代にでも戻ったみたいです。
で、暗い話はとりあえず置いといて、ジャジャーン!今年も同窓会やる事になりました!地元にいる子はみんな参加するよ。あと先生も来るって!あの人いっつも今年でワシも最後だな、来年は天国から参加するよって言ってるの。ホントバカよね。それで場所なんだけど今年はホテルが借りられなかったから猿山君のあのでっかい家でやる事になったの。ちなみに猿山君まだ独身よ。彼、中学時代は猿みたいにうるさくてひ弱そうだったけど、今は全然違うよ。なんかすごくワイルドになってるの。猿山君もゆみっぺに会いたがってるよ。というわけで出れるようだったら私の電話番号に連絡してね。
追伸:無理して同窓会に参加しなくてもいいけど電話してくれたらありがたいです。みんなゆみっぺこと心配してます。だって私達ずっと友達でしょ!
幹事:吉野えり(エリッペだよ〜)
由美子は今までの事を田舎のみんなに謝りたいと思った。猿扱いしたりした自分が許せなくなってきた。なんてことだろう。自分が手紙ひとつ送っていなかったのに、毎年同窓会の案内状を送ってくれていたなんて!
彼女はすぐ吉野えりに電話をかけたが、相手はすぐに出た。由美子は電話口の声ですぐ吉野だとわかった。彼女の声は中学時代と全く変わっていなかったのだ。
「ゆみっぺだべか?いやお久しぶりだべ!ずっと連絡なかっだがらみんなすんぱいすてたんだよ。元気だべか?」
「……」
「ゆみっぺ……どすたんだべか?」
「えりっぺぇ……!」
由美子は吉野の名前を叫ぶとそのまま泣き出してしまった。涙は次から次へと溢れ出し止まらなくなった。何か話そうにも嗚咽が止まらず言葉にならなかった。
「ゆみっぺ……なんかいろいろ辛いことがあったんだべな。こんどがえっでぎだらみんなでなぐさめであんげるからいづでもがえってきていいんだぞ。こっぢはむがしより全然かわんねえべさ。いやむがしよりもむがしらしくになってるべ!」
吉野は由美子が落ち込んでいるときいつも慰めてくれた。由美子は吉野の吉野の昔と変わらぬ優しさに感謝し、また涙が溢れてきた。
「えりっぺありがどう。どうぞうがいにはぜっだいでるだべさ!みんなによろじぐな!」
そして電車はようやく田舎の駅に着いた。本当に変わっていない、相変わらず寂れた駅だった。バスターミナルの向こうには商店街があり、店が何件か開いていた。そして奥にはおそらく毎年送別会を開催してきて、今年もそこで開催するはずだった小さな寂れたホテルがあった。由美子は十年以上昔にここから東京へと向かったのだった。あの頃は早くこんなど田舎から出たくてしょうがなかった。東京に出る時はここでみんなに見送られながら、地元に残った友人達を憐み蔑んだものだ。だが、今になってみるとここだけが、自分の居場所だったと思う。この寂れすぎた故郷だけが自分を優しく包んでくれる気がしたのだ。
運よくバスが現れた。このバスで一時間以上乗った先が彼女の故郷の村だった。バスもあの頃と変わっていない。相変わらず一時間に一本のダイヤだし、バスそのものも彼女が高校に行くときに乗っていた頃のままだ。吉野の言ったように本当に昔そのままだった。多分村も昔のままなのだろう。みんなは恐らく昔と全く変わっていないのだろう。年は歳月の分だけ取っているだろうが。変わったのは私だけかもしれない。
みんな都会ですっかり変わってしまった私を、友達だとすんなり受け入れてくれるだろうか。彼女はふと猿山のことを思い出した。猿山は由美子の初恋の相手であった。地主の一人息子で、痩せた体で猿みたいに柿なんか投げつけて遊んでいた少年だった。猿山君は今の私を見てどう思うのだろうか。
バスは町を通り過ぎ、今は田んぼの真ん中をあぜ道をノロノロと走っていた。由美子はバスに揺られながら外を見ていた。なにもかもが懐かしく思えた。高校時代にはあれほど嫌がったこの田舎の何にもない風景が。今は無性に愛おしい。彼女がそう感慨に耽っていると、バスが止まり、開いたドアから肥料工場のフンの匂いとともに新たな乗客が乗ってきた。
由美子は新しく乗ってきた乗客を見て思わず目を見開いた。乗客は小学生ぐらいの女の子の二人連れであったが、その女の子が小学校時代の自分と吉野そっくりだったのである。「このバズにのんれば駅前だべ。駅前にはマグドナルドあるだべ!」と手前の女の子が言うと後ろの子が「ほ、ホントだべが、オラバズはずめてだから怖えだべ!」と言って身をかがませる。由美子は女の子達のおしゃべりを聞いてアッ!と声を上げた。子供の頃の自分と吉野にそっくりの女の子二人は、彼女と吉野が小学生時代にやったちょっとした冒険をそっくりそのまま再現しているのであった。女の子達は由美子の1列前の席に座った。座るなり由美子そっくりの子がこう言う。「でもホントに駅前に着くんだべか?オラバズはずめてだから怖えだべ!山奥なんかにつれでいがれたりなんかしないべか?」すると吉野そっくりの子が自信満々にこう言ったのだ。「大丈夫だべさ!オラ、おとうといっかいバズさ乗っだごどあるがら安心だべ!」
しかし由美子はその結末を知っている。逆方向のバス停に乗った彼女達は駅前に着くことが出来ず、結局は元の村に戻されてしまったのだ。由美子そっくりの女の子が話しだす。「駅前にいぐどマグドナルドがあるだべ!だっだら東京にはなにがあるんだべ?よりっぺすってるか?」「しらねえけんどおとうは東京はおっかねえどごだがら大人になるまで行っちゃなんねえって言ってだべ。いや大人になっでもいっぢゃいげねえ場所だっていっでだ。ゆみっぺはいぎだいか?」由美子そっくりの少女はうーんと唸りながら考えてからこう言った。「でも東京てドラマみでえなとこだべ。キラキラすてきれいだんべな。危ねえとこかもすんねえけんどこんなウンコくせえとこよかマシだべ!」
由美子はその結末も知っている。しかし無邪気に笑うこの少女に何も言うことは出来なかった。
〈完〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
