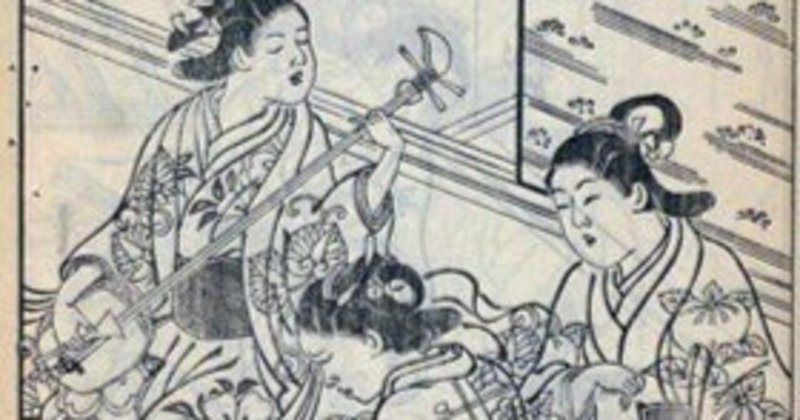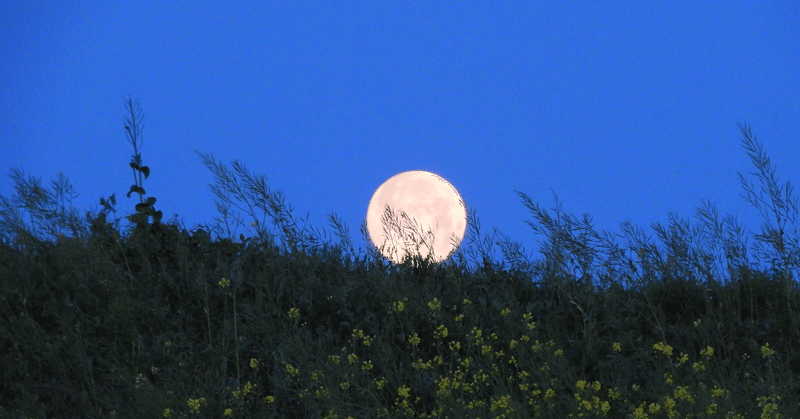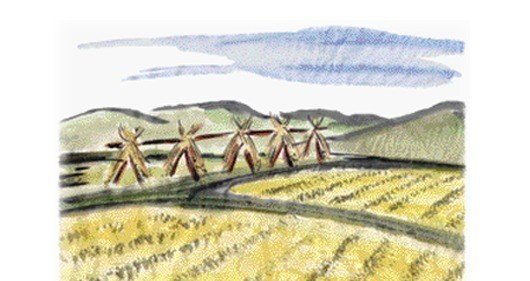
- 運営しているクリエイター
#巫女
気仙沼:補陀寺の旭神子
旭神子開山の補陀寺補陀寺は、寺伝によると寛平2年(890年)、
天台宗の補陀寺と号して赤坂小沢田に開かれたと伝えられている。
保安4(1123年)、名取の老女(旭神子)が、名取郡に熊野三所権現を勧請し、奥州を巡礼して三十三ヶ所の観音堂を建立、補陀落寺を三十番札所と定めたという。
『その後、廃絶したのを葛西家臣で細浦館主熊谷直元公が文亀元(1501年)正法寺九世虚窓良巴禅師を招いて細浦に曹洞宗補陀
【伝説】岩沼の斎宮『おすずひめ』物語
宮城県南にある岩沼市に「斎宮伝説」が伝わります。
名取老女伝承の守家の遠祖が、藤原叙用で斎藤姓(斎宮(※1)の管理監督の役職)を、名乗る由縁があると考えれば、岩沼の斎宮伝承は、豊穣をつかさどる「ケ」の巫女が存在していたことと繋がります。
地元に伝わる「おすずひめ」物語について。
おすずひめ (岩沼物語より)ある時、村に、おすずという一人の女性がやってきて、屋敷で女中仕事がないか、と探していた。