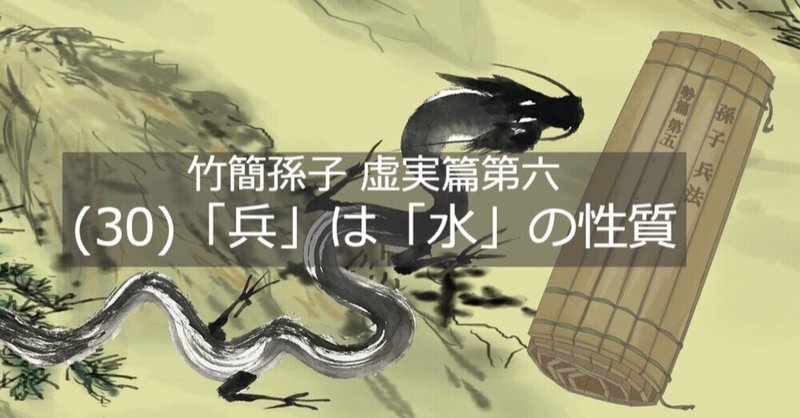
(30)「兵」は「水」の性質-竹簡孫子 虚実篇第六
虚実篇は、4段論法で理論が展開します。
一つ目が、人を致して致されず、つまり「佚」と「労」の関係
二つ目が、「無形」の説明
三つ目が、「無形」を使った戦い方
四つ目は、勢篇の理論に戻り、「正奇」の戦法の組み合わせによって「虚実」を作り出すこと、つまりそれは、無限の組み合わせがあり、掴みどころがなく、また再現性がないということを述べます。
【書き下し文】
夫(そ)れ兵の形は水に象(かたど)る。水の行(こう)は高きを避けて下きに走る。兵の勝は実は避けて虚を撃つ。
故に水は地に因りて行を制し、兵は敵に因りて勝を制す。兵に成勢(せいせい)无(な)く、恒形(こうけい)无し。能く敵に与(したが)いて化(か)するは、之れを神と謂う。
【現代訳】
そもそも軍隊の形や戦況の様子は、水のようなものです。水の流れは、高いところを避けて低いところに向かって流れます。同じように勝利する軍隊の動きも、戦力や備えの充実している場所を避けて、手薄な場所を攻撃しようとします。水は地形に沿って流れますが、軍隊の方は、敵の動きに応じて、(虚実によって)勝利を決定づけるのです。
軍隊には常に定まった勢いがあるわけではなく、常にこれで良いという体勢(形)もありません。敵軍の出方、戦況に応じて自在に変化する、これこそが神業的な用兵と言えます。
陰陽五行の(木火土金水)には、常に勝つものもなく、四季には、いつまでも留まる季節もありません。日の長さにも、長短の変化があり、月にも、満ち欠けの変化があるではないか・・・

まず最初に軍隊の性質を「水」に例えます。
水が高きを避けて低きに流れるように、軍隊も、充実した敵を避けて、分散し手薄な敵を攻撃すると。
その流れが自然であり、この世界の道理です。これに反することはありません。反した場合は痛いしっぺ返しを喰らうことになります。
つまり敵の虚実、状態や体勢に応じて自軍が動くということです。相手に応じながら変化するということです。変化するものは勢い、そして軍隊の体勢です。

勢いには定まったものなどなく、敵との関係で発揮される勢いの強弱が決まります。相手が強ければ勢いは弱まります。

また、軍隊の形も一定ではありません。一箇所に集まって戦力を集中する場合もあれば、「無形」となって秘匿し、自由に形を変える場合もあります。
この軍の形も相手に応じて変化します。
このように相手に応じて、人知れず、気配も感じさせず変化することを「神」といっております。
能く敵に与(したが)いて化(か)するは、之れを神と謂う。

さてそれでは、敵軍の「変化」をどのように捉えれば良いのでしょうか。
ここで重要なことは、この世にあるすべては変化するという事です。
結文は、我が軍が無限に変化をするのではなく、どんなに元気に溢れ、戦力のある敵軍でも、さまざまな自然法則のように変化する事を言っています。つまり、チャンスがあるという事です。
【書き下し文】
五行に恒勝(こうしょう)无(な)し、四時(しいじ)に常位(じょうい)无し、日に短長有り、月に死生有り。
【現代訳】
陰陽五行の(木火土金水)には、常に勝つものもなく、四季には、いつまでも留まる季節もありません。日の長さにも、長短の変化があり、月にも、満ち欠けの変化があるではないか・・・

陰陽五行の「木→火→土→金→水」は、どれかが常に勝つということはありません。全てに対して無敵の強さを発揮するものないということです。ですから必ず敵の形、状況によって応じる方法があります。
また季節の変化のように、気の量は上下します。夜になれば疲れて休みます。長期間従軍すれば、気力は衰え、望郷の念に駆られてしまいます。
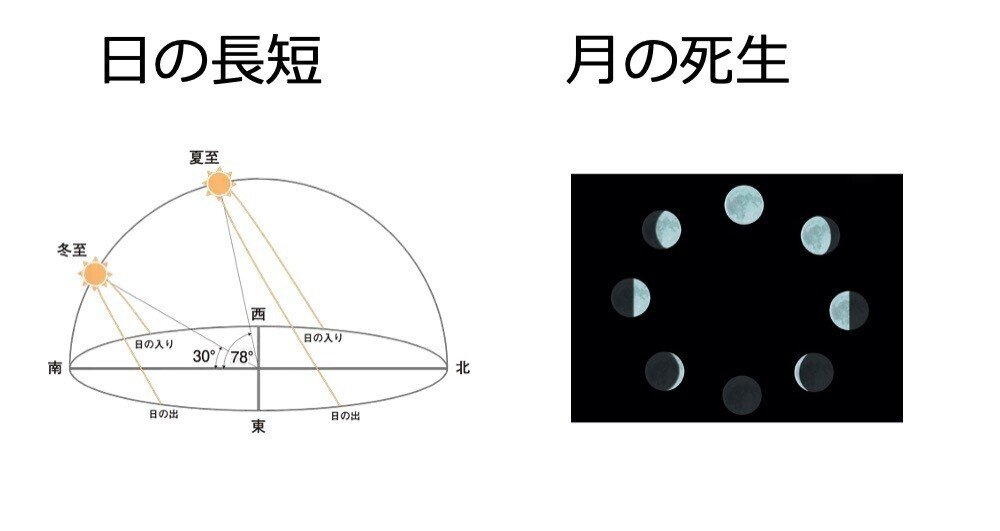
日照時間が変化するように、月の満ち欠けがあるように、自然の動き、地形、軍隊においてもコンディションは変化します。
常に変化して止まない、良い時と悪い時は循環し、自分の力で止めることも変化させることもできません。その動きに応じるという訳です。
※本文は、計篇の五事の「天」の変化に応じること、「順」について述べている箇所でもあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
