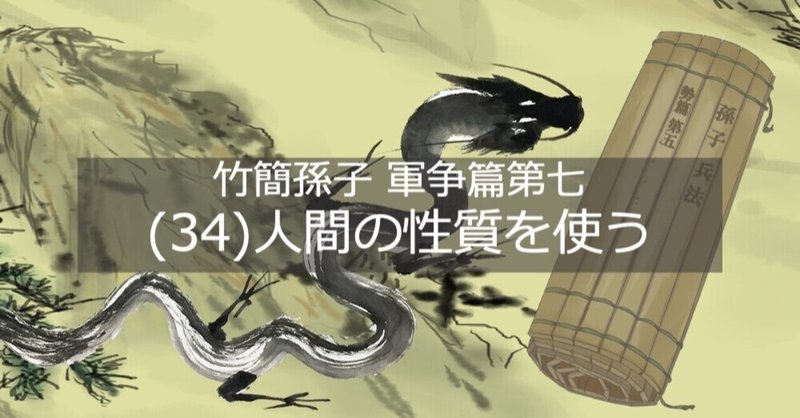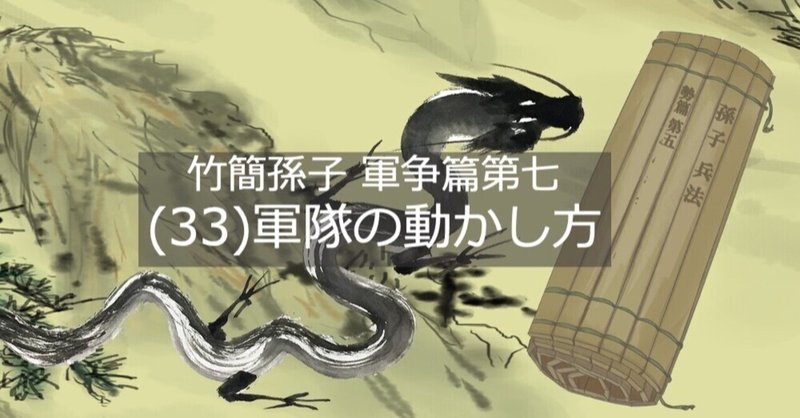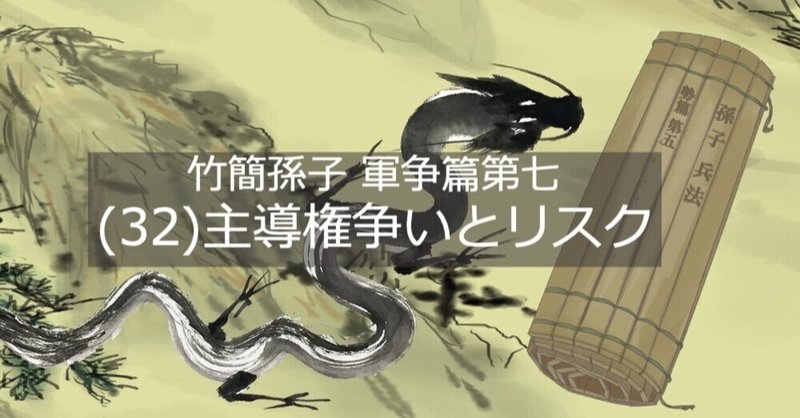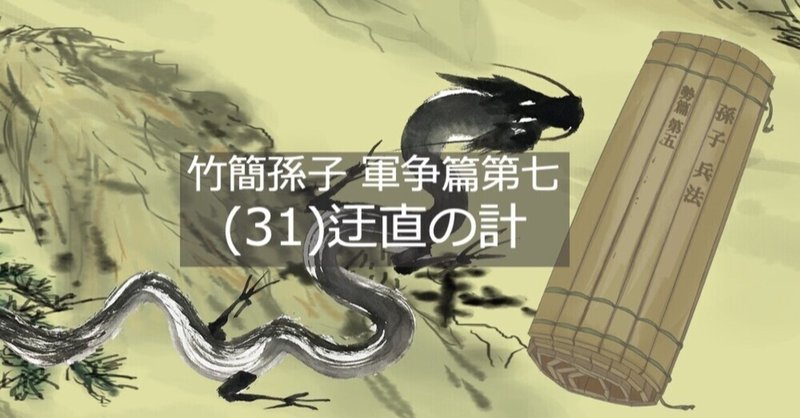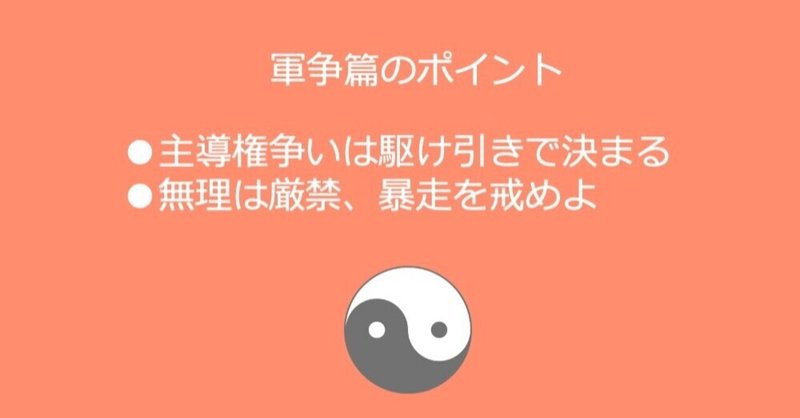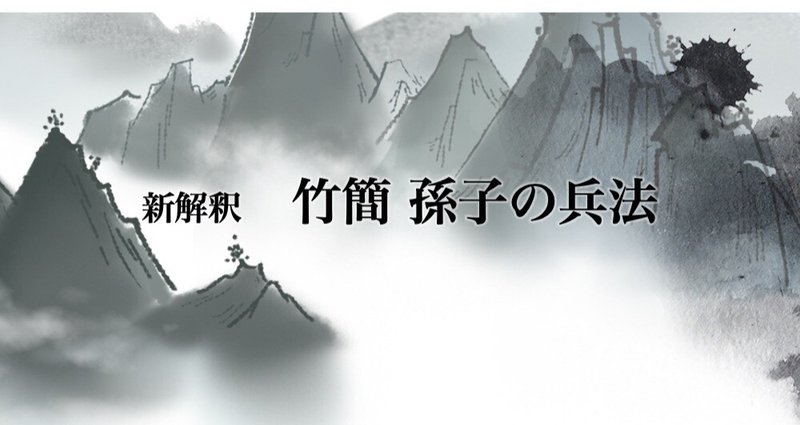
世界最古の兵法書「孫子の兵法」。その孫子の兵法の中でも最も古い「竹簡孫子」を研究しているマガジンです。孫子の兵法理論である「正奇」や「虚実」「形勢」などの追概念は「陰陽理論」が適…
- 運営しているクリエイター
#軍争篇
(35)集団を動かす時の注意点-竹簡孫子 軍争篇第七
軍争篇の篇末は、昔から多くの研究者の間で議論されています。軍争篇にあるのは間違いで、九変篇の冒頭にあるべきではないかと。事実、現行孫子では九変篇に組み入れられている。
この件に関して、私の見解を述べると、「竹簡孫子」の構成である軍争篇の篇末にある方が、意味が通じるので、軍争篇に入れる方が正しいという立場に立ちたいと思います。
なぜそう言えるのかというと、軍争篇は、主導権争いに勝ための軍隊の動か