
【機能性食品を取り巻く環境③】フードファディズム
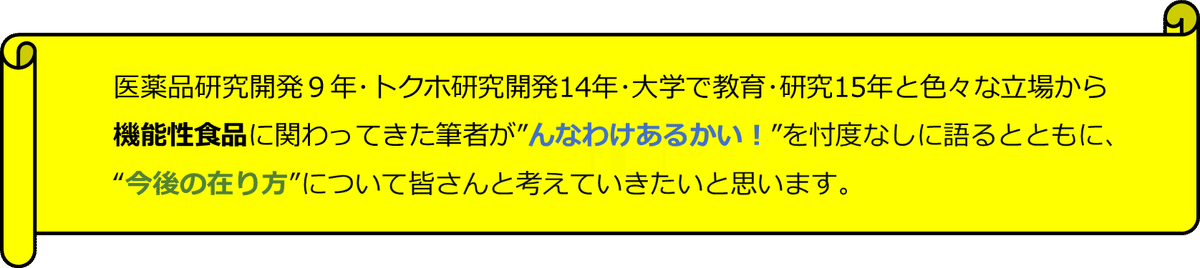
この記事でわかること【一般消費者・食品事業者・機能性食品研究者向け】
1.フードファディズムとは?
2.栄養”感”とフードファディズム
3.形を変えてはやってくるフードファディズム
1. これまでのおさらい
以前の記事で、栄養学的な栄養価と、社会通念上の栄養”感”は大きく異なるらしい ということをお伝えしました。それはおそらく、栄養(?)や食品をを取り巻く様々な立場にある大人たちの間で情報戦に私たち一般消費者が巻き込まれてしまい、義務教育で習ったはずの栄養価とは異なる
栄養”感”を知らぬ間に植え付けられているからなのでしょう。
2. フードファディズムとは?
40代以上の方は、2007年ごろにフードファディズムという言葉を聞かれているのはないでしょうか。
ファディズムとは、一時的な流行を熱狂的に信じることと訳され、
フードファディズムとは、食品や栄養が健康や病気に与える影響を過大に評価し、マスメディアが取り上げた「〇〇を食べるとがんになりにくくなる」
というガセ情報を信じて、その食品を過剰摂取するというような、
食生活のことを指しています。

現在でも、以前の記事で取り上げたスーパーフードとか、グルテンフリーとか、SNSでを通じて、根拠のない”おしゃれ”な食生活を喧伝する人達がいますよね。
思い起こすと、1960年代に「味の素(グルタミン酸ナトリウム)を
食べると頭がよくなる」というブームがあり、筆者が小学生のころは、
食卓に味の素の瓶が置いてあり、何にでもかけて食べてるよう促されていた気がします。確かに、グルタミン酸は神経伝達物質の一つですが、必要に応じて体内で合成されるので、過剰摂取しても神経系に影響は与えません。
また1980年代には、♪リノールサラダ油 サフラワー♪というCMが
ひっきりなしに流れていて、油を摂るならリノール酸という時代もありました。もちろん現在では、n-6系脂肪酸の代表格であるリノール酸とn-3系脂肪酸をバランス良く摂取することが、健康を保つ上で重要であると考えられています(脂肪酸の摂取バランスと疾患リスクの関係性については、未だに議論が止みませんね)。
3. フードファディズムの頂点?
高度成長期からバブル期にはこのようなフードファディズムが蔓延していましたが、2000年代前半にそのピークを迎えます。
特に2000年代前半には、あまたの健康情報番組や健康情報雑誌が配信・発刊されていました。健康情報番組としては「発掘あるある大事典」「ためしてガッテン」、健康情報雑誌としては「爽快」「ゆほびか」「わかさ」などです。 ところがその筆頭である「発掘あるある大事典」で、社会を揺るがす大きな問題が起こりました(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%8E%98!%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8))
2007年に放送された「納豆ダイエット」の回では、8名の女性に納豆を食べさせ、2週間後に最大で体重が3.4kg減少したという内容が放送されました。その翌日から全国のスーパーで納豆が売り切れたり品薄となるという事態に発展しました。このデータ(?)については、捏造であったこと、またこの効果について、テンプル大学 Schwartz A.G教授*(欄外参照)のインタビューの日本語訳がデタラメであったことが発覚し、「発掘あるある大事典」は放送休止に追い込まれたのです。

同時期に発売された高橋久仁子先生(群馬大学・名誉教授、2022年の栄養食糧学会でもおみかけしました)の著書「フードファディズム」は、このような背景からベストセラーとなりました。残念ながら現在は絶版のようですが。

*Prof. Schwartz A.G. Department of Microbiology, Temple University School of Medicine(2006年当時) デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)のアンチエイジング作用について研究。代表的な論文:Schwartz AG & Pashko LL.Dehydroepiandrosterone, glucose-6-phosphate dehydrogenase, and longevity Ageing Res Rev. 2004 Apr;3(2):171-87. doi: 10.1016/j.arr.2003.05.001.
番組で紹介された論文(違う著者のものです)Stwart PM. Aging and fountain-of-youth hormones. N Engl J Med. 2006 Oct 19;355(16):1724-6. doi: 10.1056/NEJMe068189.
副腎から生成するデヒドロエピアンドロステロン(DHEA)は、豊富に産生される副腎ステロイドであり、加齢によって血中濃度が低下する。DHEAは、哺乳類のグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)の強力な非競合的阻害剤であり、糖代謝に影響することが示唆される。
しかしながら、その効果は未だに明確にはなっていません。
3.形を変えてはやってくるフードファディズム
2010年ごろまで、この手の番組はなりを潜めていましたが、
現在では語り手を医者に変えたものや直接的に番組タイトルにはうたっていないもの(「世界一受けたい授業!!」、「林修の今でしょ!講座」)として復活しています。
それよりも問題だと思うのは、法律という権威を纏って復活をとげた
フードファディズムの一種ではないかと思われる
機能性表示食品制度
です。 機能性食品制度(一部トクホも含みますが)の問題点について、語っていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
