
”耳が聞こえなくても、音楽を楽しめます” 片耳難聴きこいろ 麻野さん&ピアニスト 辻さん インタビュー
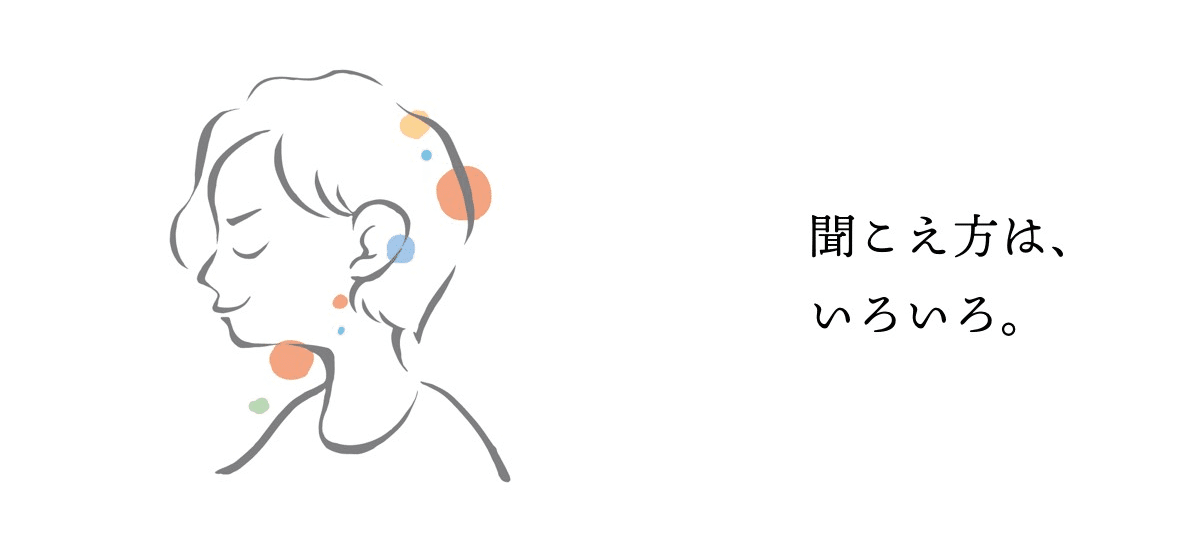
みなさまこんにちは。
七香です。💐
先日、きこいろさんの 片耳難聴×両耳難聴コラボ交流会 に参加したことをきっかけに、後日改めてインタビューをさせていただきました。
片耳難聴×両耳難聴コラボ交流会に参加した際のnoteレポート記事はこちら▽
インタビューにご協力いただいた麻野さんには、コラボ交流会の際、ご自身の片耳難聴の特徴や困りごと・工夫について教えていただきました。
また、新たにお招きいただいた辻さんは、片耳難聴の方で、ピアニストとして活躍されています。
辻さんについての記事はこちら▽
今回は、「片耳難聴の方に、音楽祭に来ていただき楽しんでもらうには」
ということを知りたく、お話を伺いました。
日常生活で困ること
片耳難聴は、いつも聞こえなくて困るわけではなく、困る場面は状況による といった、限定的なものだそうです。
そのため、周りからは一見して聞こえないとは分からず、気づかれないそうです。
聞こえない側に友達が来てしまったり、聞こえない側から話しかけられてしまい、気づかずに無視してしまうこともあります。
ーー環境面で困ることはありますか?
麻野:にぎやかな場所では、音の聞き分けが難しいです。(例:電車の中、ライブ会場)
また、小さな音声は聞こえないのにもかかわらず、大きな音が異常に響いてうるさく感じるなど、聴覚過敏のような症状がある人もいます。
辻:音源定位が難しく、どこから音が出ているのかが分かりづらいです。
自己表明としてのルーツの一つ「片耳難聴マーク」
きこいろさんは、
片耳難聴の方が、片耳難聴のことを自己表明したり伝えられるために
片耳難聴のマークを作成されています。
紹介いただいたものから一部を載せておきます。


マークについての詳しい内容はこちら▽
このようなマークの存在によって、
当事者が片耳難聴のことを表明しやすくなり
私たちも、片耳難聴についての意識や理解を深めることができると思いました。
いつ起こるかわからない、めまいの怖さ
聞こえ 以外にも、体調面での困りごともあります。
耳の器官の一つである内耳には、体のバランスの働きを司る器官があります。
そのために、内耳の障がいによる難聴では、めまいが起こる場合があります。
ーーいつ起こるかわからない、そのような怖さを念頭において外出される際に、どんな対応があると良いですか?
麻野:ちょっと一息できるような休憩スペースがあると助かります。
このことを伺った際、休憩スペースというのは 高齢者の方やお子様連れの方がよく利用するイメージでしたが、聴覚障がいの人にとっても必要とされているものだとわかり、視野が広まりました。
音楽の楽しみ方について
ーー片耳難聴の方は、音楽をどのように楽しみますか?
麻野:わりと自然に興味があります。聴覚過敏がある場合は、耳栓をしたりイヤーマフをしている人が多くなってきました。
最近は、「耳を大切にしようキャンペーン」みたいな感じで、適切な音量のライブもあります。
麻野さんから教えていただいた、ライブ専用の耳栓に関する関連ページはこちら▽
ーー音楽祭では、どのような配慮があると助かりますか?
麻野:「ここ数年で片耳難聴になった」という人の中には、音楽を聞くのが怖いと感じられる方もいます。もう片方の耳まで悪くなってしまったらどうしようという不安や、また、音の聞こえ方が変わったことに慣れず、聞くこと自体が疲れるという方もいます。
そのため、アコースティックなどの、静かなステージゾーンがあると助かると聞くことがあります。
ーー辻さんが、ピアノを演奏される際、片耳難聴の方たちに向けて何か工夫することはありますか?
辻:片耳難聴者が聞き取りづらい場面として、コンサートホールのように「音が反響する環境」があります。
ホールでは、複雑なつくりや細かいパッセージがある曲を演奏するとき、音のスピードを下げたりして、一つ一つの響きを丁寧にしています。
「耳が聞こえなくても、音楽を楽しめます」
お二人と話しているうちに、音楽の楽しみ方や、音楽祭を運営するコツをたくさん知ることができました。
また、お二人の 音楽が好き という気持ちが伝わってきました。
麻野:私たちも、音楽のイベントを開催したいねって考えていたところなんです。
「耳が聞こえなくても、音楽楽しめるぞ!」
ということを知ってほしいです。
私は、障がいをお持ちの方、特に耳の聞こえない方は、どのように音楽を楽しむのだろう?と考えることが増えましたが、
音楽は多様な方に愛されている
そう感じます。
もちろん、全員音楽が好き とは言い切れませんが、
音楽を楽しみたい と思っている人たちがたくさんいることを実感しました。
聞こえもさまざま
音楽の楽しみ方も、さまざま。
先ほど紹介していただいたようなライブ用耳栓などのデバイスが普及されたり、デバイスのような大掛かりなものではなくても、
環境面に配慮したり、サポートを工夫するなど些細なことから始めることによって、
誰でも楽しめる音楽(音楽祭) というのは多くの方に必要とされ、可能性が広がっていくのではないかなと思いました。
そして、音楽を通して「つながり」を感じられたり
新たな出会いや学びがあることによって
音楽の魅力はますます大きくなると思うのです。
きこいろさんの音楽イベント、開催された際はぜひ行ってみたいです。♩
今回インタビューで伺った内容は、私がプロジェクトメンバーとして参加している、
国籍・世代・性別・年齢・障がいの有無限らず誰もが楽しめる音楽祭
「ホッチポッチミュージックフェスティバル」
の運営にも反映し、
より多様な方が音楽祭に訪れて楽しんでいただけるような音楽祭作りに励んでいきたいと思います。
今年も秋に開催される予定なので、もしよかったら、こちらの音楽祭にも足を運んでみてください。
麻野さん、辻さん、貴重なお時間をありがとうございました。🕊
本日も読んでいただき、ありがとうございました。🌿
きこいろ 片耳難聴の情報・コミュニティサイト ホームページ▽
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
