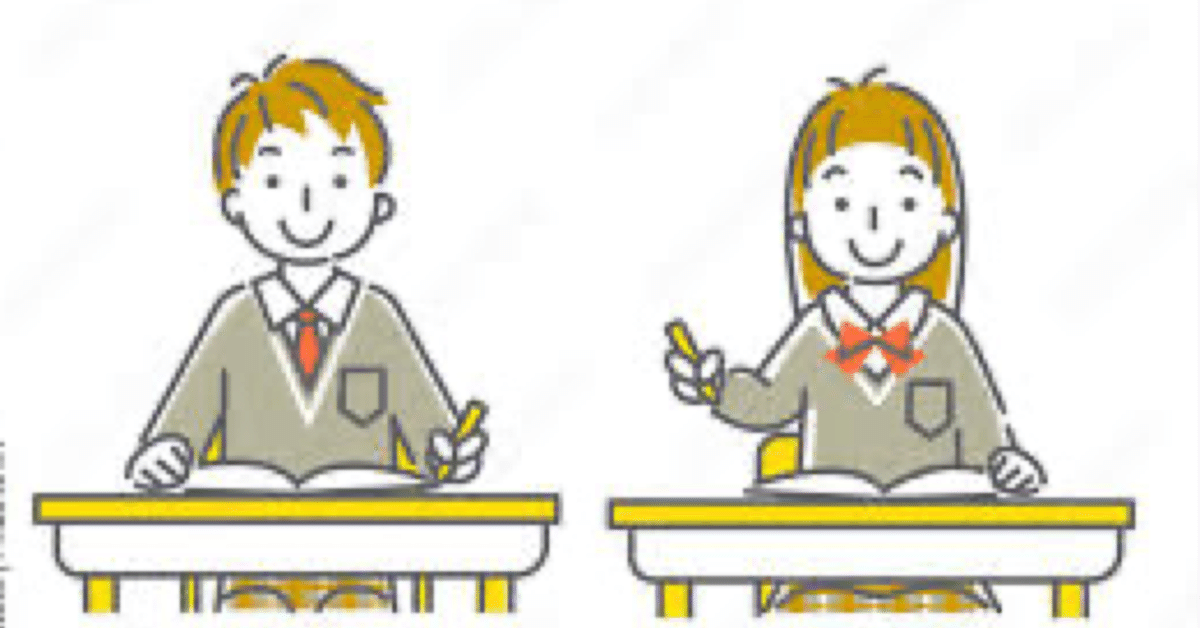
大学生には「生活保護」ではなく「共通テスト上位30%給付型奨学金」で支援を
*有料記事ですが最後まで無料で読むことができます。
面白い・役立ったと思った方は投げ銭をお願いします。
厚生労働省は昨年11月14日、5年に1度の生活保護や生活困窮者支援制度の見直しに向けた報告書案を示した。それによると、生活保護世帯からの大学進学を支援するために従来よりも貯蓄を柔軟にできるようにする一方で、保護を受けながら大学に通うことは引き続き認めないという方針が示されていた。
大学生の生活保護認めず 進学向け貯蓄は柔軟に、厚労省
このニュースを受けて、Twitterでは「外国人に生活保護を支給するのに、日本人の大学生には支給しないのか?」「貧乏人の子供は大学に行かずに働けということか!」という怒りと嘆きの声が多く上がった。
こうした意見は「感情」としては理解できるものだ。しかし、それを踏まえても大学生を生活保護の対象にすることは現実的にあり得ないことで、今後もこの状態が変わることは決してないだろう。大学生には「生活保護」ではない形で支援をするべきだ。
その理由について書いていく。
学生を生活保護の対象にすると何が起こる?
現在、日本には学部在籍者のみでも約260万人の大学生がおり、その半数が一人暮らしをしているという。
・第57回学生生活実態調査 概要報告
・2021年度の大学生総数、約263万人で過去最多を更新
現在の生活保護制度では、「単身世帯で資産が無く収入が保護費(11万円前後)以下」という条件を満たせば受給可能であるため、仮に「一人暮らしの大学生」を保護の対象にするだけでも、新たに100万人の受給”対象”者が生まれることになるのだ。
そして極端なことを言えば、「世帯を分けて一人暮らしさえすれば親の経済状況とは関係なく大学生も生活保護を受けられる」ということになれば、最悪の場合は200万人以上が新たに受給”対象”者になるのだ。
現在の生活保護受給者の総数は200万人程度なので、これらがいかに大きな数字か分かるだろう。
もちろん、現実的には大学生を生活保護の対象にしたところでほとんどの学生は受給しようとせず、これまで通りに仕送りやバイト、奨学金で暮らすことを選ぶだろう。
しかし、「奨学金」という名の借金を負ったり、バイトに追われたりすることもなく大学生活を送れると考えると、「生活保護を受けながら大学に通う」というのはかなり魅力的な選択肢であるのは間違いない。教育費が家計に大きな負担となっているのは疑いようがない事実であり、数十万人の学生が受給を真剣に検討するというのは決して「控えめな予想」ではないだろう。
ここまで、大学生を生活保護の対象にするとどうなるか?というシミュレーションをしてみたわけだが、制度とは最悪のケースを想定して作られるものであるため、理論上は100万人単位で受給”対象”者が増えるような制度変更が行われるはずがない。
「生活保護世帯の子供だけを対象にすればいいのでは?」という意見もあるだろうが、それも現実的には難しい。いまや年収300万~400万円台前半でカツカツの生活を送りながら子供の教育費を払う世帯が多数あるため、もしもそのような制度変更を行うと、「生活保護をもらった方が働かないで暮らせて子供も無料で大学に行けるじゃん」という状況になりかねないからだ。
このことを政府は「低所得層との公平性の観点から」というオブラートに包んだ表現で説明しているが、「”諦めて生活保護”という合理的な判断をする国民を増やしたくない」というのが本音だろう。
以上のような理由で、「大学生が生活保護の支給対象になることは今後も決してない」と考えられるのだ。
共通テスト上位30%給付型奨学金のススメ
とはいえ、大学生の約半数が奨学金を借り、それでも足りないからバイトに明け暮れ、卒業後はすぐに利子をつけて奨学金を返済する日々を送るというのは、やはり正しいことだとは言えない。生活保護ではない何らかの形で支援をするべきだと思う。
例えば、「共通テストで受験者の上位30%の成績を収めた人には給付型の奨学金を与える」というのはどうだろうか?
「受験者の上位30%」はその集団の中で偏差値55程度であるわけだが、仮にこの数値を大学受験偏差値に当てはめれば「日東駒専」~「MARCH」の間くらいにボーダーラインが発生することになる。
大学受験を経験した人ならわかると思うが、「返済義務のない給付型奨学金」を支給する対象としては、このあたりにボーダーラインがあるというのは「絶妙」と言える学力水準だ。
このあたりのランクまでを対象に給付型奨学金を与えれば、「大学生への国からの支援」としては十分すぎるのではないだろうか?(というか、これ以下の偏差値の大学生に税金でサポートを与えるメリットはほとんどないと考えられる。)
もちろん、無制限に給付型奨学金を与えるわけにはいかないので、「年間100万円を上限とする授業料分のみ」みたいなルールが必要だと思う。その場合、2022年度の共通試験受験者総数が約50万人であることを基準に考えると、上位30%は約15万人なので、財源として必要なのは1500億円程度ということになる。
この1500億円という数字は、「国公立大学の完全無償化に必要な予算が年間3000億円程度」という試算を文科省が以前出していたことを考えると、かなり安く抑えられていると思う。余裕があるなら年間上限を200万円まで引き上げてもいいのかもしれない。
なお、同じくらいの予算であれば「国公立大学無料化」よりも「共通テスト上位30%給付型奨学金」の方が学生にとって選択の幅が広がるので、個人的にはこちらを推している。奨学金を使って国内の大学に行ってもいいし、海外に留学してもいいし、あるいは専門学校に行くのもいい。柔軟に学生の進路希望を叶えられる制度にするべきだ。
ちなみに、私立大学まで含めた大学の完全無償化に必要な予算が年間3兆円だそうだが、「英語」の授業と称して中学レベルのbe動詞から教えていたり、「数学」の授業と称して引き算の筆算を教えていたりするFランク大学の学生まで税金で支援することになるため、賛同する国民は決して多くないだろう。
やはり、共通テストで上位30%くらいまでの成績を収めるような、それなりにやる気と学力のある学生だけに絞って支援を最大化する方が、実現性の面でも納得感の面でも有力な案と言えるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

