
平成ベストソングを選ぶ
2024年は3月からいろいろあって心身ともにバタバタな日々を過ごしていたので全然投稿ができていなかった。
そんなわけで下書きに書きかけのまま大量に溜まっているnoteの1つを放出して今回はお茶を濁そうと思う。
本ポストは2023年9月に作成したようだ。
今見返してみると「なんでこんな曲を選んだのか?」とか「なんでこんなこと言っているのか?」と当時の自分を問い詰めてやりたい曲や文章もあるのだがそれも含めて当時の自分の気持ちが表れているのであろうと思い、特に修正するのは止めた。
なぜかオーサカモノレールの文章が1センテンスのみになっていたけどもういいや。
というわけで以下本文。
はじめに
ふと気づけば令和もあっという間に丸々5年が経過しようとしている。すなわち平成が終わって5年が経過しようとしている(小泉構文)。
ネットで時々見かける「平成ベストソング」なるものや、テレビの企画でそんなランキングをやったりして以前話題になっていたようで、自分も平成を振り返って見ようというポスト。
が、如何せん音楽を「アルバム」で聴く世代なので、曲単位での選定は難しい。
なおかつ「邦楽」自体あんまり知識がないんよね…。自分の邦楽の知識と記憶の扉を全開にしてひねり出した30曲。30曲も選べないよ…。
一応選定基準としては、
①自分が好きな曲
②当時の、又は後の音楽業界になんらかの影響を与えた(ような気がする)曲。(ただし完全に主観)
③②とは別に影響をほとんど与えずそのミュージシャンの個性・孤高感が強く出た曲(ただし以下略)
④発売当時の時代の空気感を纏った曲
以上の4点から、できるだけシングルとして世に出た曲を選んでみた。
「平成」とわざわざ謳っている以上、対象は「邦楽」「日本人ミュージシャン」がメインで制作された音楽。
ランキングではなく発売年順です。
高野寛 / ベステンダンク(1990・平成2年)

前曲「虹の都」と併せ、そんなにポピュラー・ミュージックに興味のなかった小学生時代に耳にして子どもながらにいい曲だなあと思った。トッド・ラングレン・プロデュースなんだと。シティ・ポップ、渋谷系の再評価の時に話題になるかと思ったけど、そうでもなかった人。楠瀬誠志郎と時々自分の中でごっちゃになる。
陣内大蔵 / そして僕は途方に暮れる(1991・平成3年)

何かのシングルのB面、カップリングだった記憶があったが、wikiによると「空よ」と両A面として発売されたとの記録あり。だが画像検索しても「空よ」のシングルに本曲のタイトルが記されたものが見つからなかった…。大沢誉志幸の曲で今では時代を超えてカヴァーも多く「曲」の強さを感じる。暗めの曲だけど子供ながらに響くものがあり、よく覚えている。兄の影響でアルバム「Blow Wind Blow」もよく聴いた。
United Future Organization / Loud Minorty(1992・平成4年)

サンプリングの妙技を尽くした高速ジャズ・ダンサーは海外のフロアを沸かせた。藤原ヒロシや福富幸宏、Kyoto Jazz MassiveにDJ KENTARO等々…枚挙に暇がないが、当時から現在に至るまで日本のクラブ/DJ文化はドメスティックよりグローバルでの評価が高いようだ。本作を聴くとネタ元のディー・ディー・ブリッジウォーターのアジり(曲自体はフランク・フォスター)が聴きたくなる。
Nokko / 人魚(1994・平成6年)

レベッカは全く世代ではなかったので「フレンズ」ぐらいしか知らなかった。この曲と次シングル「ライヴがはねたら」はほんと名曲だと思う。この曲は筒美京平なんだね。安室奈美恵もカヴァーしている。
Judy And Mary / ドキドキ(1995・平成7年)

レベッカの影響を受けつつそれをアップデートしたポップ・アイコン、YUKI。現在に至るまで日本のミュージック・シーンにおける女性像に有象無象の影響を与え続けている。楽器隊の実力は言わずもがなだが、恩ちゃんのさわやかポップスもTAKUYAのパンキッシュさも平然と乗りこなして見せる彼女の存在こそがジュディマリそのものであったと解散して気づかされた。
ソウル・フラワー・モノノケ・サミット / 復興節(1995・平成7年)

1995年の阪神・淡路大震災を受けてはじめたソウル・フラワー・ユニオンの別動隊。「東京の永田云々~」の歌詞が発売禁止になったらしいがそれほど過激か?インディーからのリリースとなったが流通はエイベックスがしていてJDS便に乗っていたので入手はしやすかった(販売経路の話)。原曲は関東大震災を受けて作られた曲なんだとか。3・11の時は多くの応援歌が生まれたけどその走りといえる曲。まあ単純な応援歌ではないけど。
Mr. Children / マシンガンをぶっ放せ(1996・平成8年)
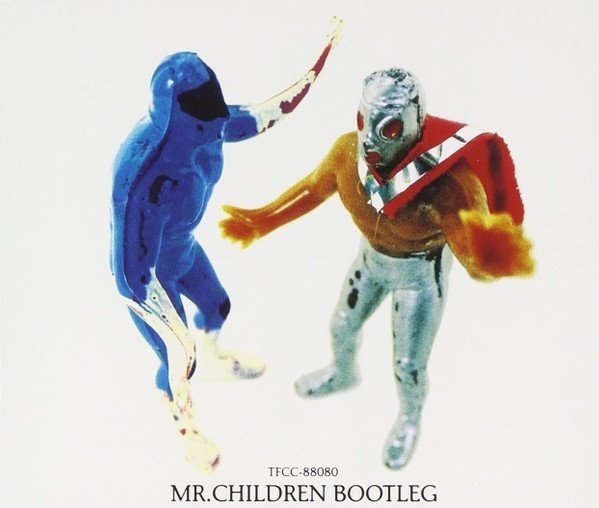
「深海」からのリカット。無邪気なバンドマンがダークサイドに堕ちていく時期だけにヴィジュアル含めギラギラに尖りまくった桜井が最高にかっこよかった。時事ネタを盛り込んだやさぐれた歌詞とサウンドは国民的ポップ・スターの階段を上っていた彼の魂の叫び。シングル収録の3曲ともそんなノリ。
The Yellow Monkey / Jam(1996年・平成8年)

同じ「歌謡ロック」でもB'zとはまた違うベクトルだったイエモン。見た目が70年代の海外ハード・ロック・バンドみたいなカッコよさなのにこんな湿っぽい情緒を醸し出すおかしなグループであった。後年、件の飛行機墜落ニュースのくだりをどうこうツッコむ意見があったがあまりにも野暮。この曲で言いたいことはそういうことではないんだよ。
Thee Michelle Gun Elephant / リリィ(1996・平成8年)
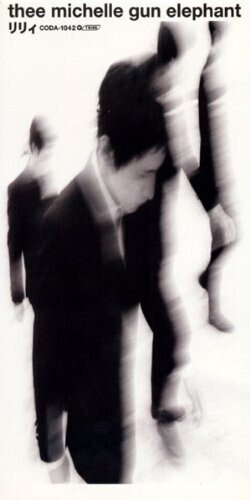
どこで聴いたのか全然記憶はないけど初めて聴いたミッシェルの曲。がなるヴォーカルと尖がったギターがヒットチャートを賑わせるロックとは異なる、正しく「オルタナティヴ」なサウンドだった。曲自体もポップで良きかな。
黒夢 / Maria(1998・平成10年)

「Fake Star」、「Drug Treatment」と「脱・ヴィジュアル系」の歩みを進めていた黒夢がスカコアやメロコアに本腰入れて挑んでいた時期。KEMURIやGeluguguのような本格的なバンドと比べればノリと言うかグルーヴ感は乏しいしぎこちなさは否めないが、それもまたオリジナリティとして受け止めるとよい。もともと二人の関係が良くなかったらしいが結局この路線を突き詰めることなくバンドは崩壊の道を辿る。フロントマンの清春ばかりが目立つけどバンドとしても結構いいグループだったと思う。
UA / ミルクティー(1998年・平成10年)

アラニス・モリセットやフィオナ・アップルをロール・モデルとしている椎名林檎やCoccoを筆頭とする露悪系(?)女性ミュージシャンと、それらをやたらと礼賛するリスナーが今なお量産され続けている状況には吐き気がするが、そのような露悪系とは一線を画して音楽を追求していたUAが朝本浩文と組んでいた時代の名曲。本曲は前例のミュージシャンのあけすけなエロスではなく、まったり漂うエロスが良い。
Globe / Wanna Be A Dreammaker(1998・平成10年)

世紀末の日本を席巻した稀代のヒット・メイカー、小室哲哉もあまりにも際限なく曲を提供し続けたせいかセールスはゆっくりと下降線を辿る事に。しかしながら制作意欲は先鋭化されていったようで、自身が参加するこのユニットは良くも悪くも「壊れた」曲が増え、KIEKOに無茶苦茶なキーを歌わせるように。この曲はそのイントロダクションと言える。誰かこれ以降のGlobeのフラットな評価をしてくれないかな。
Air / Kids Are Alright (1998・平成10年)

ミッシェルの「Chickin Zombies」と同日発売のアルバム「My Life As Air」のアナウンス・シングル。近鉄パッセのタワーに入荷日に買いに行ったのは良い思い出。エールではなくアリアでもなくエア。車谷浩司。オルタナやパワー・ポップ等90年代初頭~中期の洋楽ロックの影響を色濃く受けたバンド・サウンドが分かりやすくかっこよかった。まんまウィーザーの曲とかもある。
Triceratops / If(1999・平成11年)

ソニーから「Rasberry」のデビューはインパクト大だったが、ロック特有の屈折、屈託がなさ過ぎて大ブレイク出来ず仕舞いだったトライセラ。今聴けばこの曲はソウルフルなロックをやりたかったのかなとも思う。ストーンズの「Beast Of Burden」みたいな感じ?違うか。
aiko / おやすみなさい(2001年・平成13年)

ブレイクした「花火」の「変さ」は当時ではなかなかの衝撃で、その後順調にSSWとしてのキャリアを歩んでいる彼女。小手先の違いはあるけど音楽的にはドラスティックな変化もなく歌詞はひたすら恋愛模様を歌う姿勢は潔さと清々しさを感じる。名曲揃いのシングルの中で本作を選んだのは個人的な思い出が強いから。
ウルフルズ / 笑えれば(2002年・平成14年)

トータス松本は絶対陽キャで、人付き合いもめっちゃうまいと思うのにこんな曲を作れるんだからずるいと思う。「ええねん」「暴れだす」「サムライソウル」等この時期のウルフルズは泣ける。
スーパーカー / Storobolights(2002・平成14年)

青臭いシューゲ・バンドだったのに時代の波のみ込まれてこんな風になってしまった。コウダイが不憫でならない。あとバンド名が英語表記が正しいのかカタカナ表記が正しいのかいまだにわからない。当時ロック系イベントに行くとくるりの「ワールズエンド・スーパーノヴァ」とかこの曲がタヒぬ程かかっていた。仕事終わって朝までクラブにいてそこからまた出勤するという今となっては信じられない生活をしていた。もうあの頃には帰りたくないです。
スガシカオ / 光の川(2004・平成16年)

初期のころは予算的なこととかセールス的なこともあって中途半端なファンクだったスガだけどこの頃は本人が思い描くファンクを音にできていたのではないか。知らんけど。ブレイク・ビーツ(たぶん打ち込み)に揺らぐエレピ、ワウ・ギターと分かりやすいぐらい教科書的ファンク。「秘密」とかこの頃の彼は密室性は薄れたが、正にファンカホリックであった。
Rip Slyme / 黄昏サラウンド(2004年・平成16年)
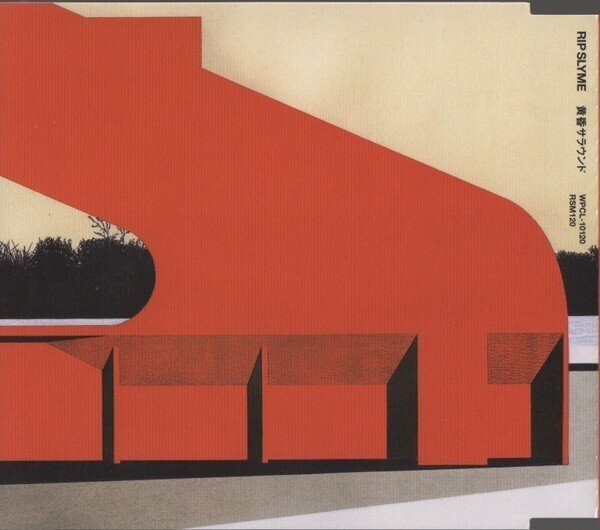
「今夜はブギーバック」「DA.YO.NE.」「Greatful Days」とメジャー・シーンに侵攻していったジャパニーズ・ヒップ・ホップ。本国アメリカのそれとは違い「クロさ」を感じさせるものはごく少数ではあるが、それ故にお茶の間にもわかりやすく届いたのであろうし、アメリカとも違う独自の進化をみせている。(今ではアメリカのヒップ・ホップも「クロい」ものはほとんどない)ヒップ・ホップが渇いているののにこんなにも日本的メランコリックになれるなんてまさに独自。やっぱりPESあってこそのリップだと思うんだ。
Tokona-X / 知らざあ言って聞かせやSHOW(2004・平成16年)

自分が某CDショップ勤務時代、職場にLA留学経験のあるゴリゴリのヒップ・ホップDJがおり、名古屋のヒップ・ホップ・コミュニティにも加わっていたのだが、そんな彼から教えられた1曲。名古屋弁(常滑だから西三河弁?)の日本語リリックでこんなにもグルーヴさせることができることが衝撃であった。ちなみに教えてくれた彼は、見た目いかにもな厳つさだったが中身はいろいろと気が付くとてもやさしいいい人であった。ゴリッゴリのウェッサイものばっかりイニシャル(初回発注)入れようとするのでUKロック大好きの女性上司にめっちゃ煙たがれてたw
くるり / バースデイ(2005・平成17年)

この曲から「Superstar」~「赤い電車」と立て続けにポップな名曲をリリースしていたくるり。ロキノン~Snoozer系からはやたらと評価されてて正直気持ち悪いが、私の中でこのバンドは完全にシングル・ミュージシャンであってアルバム1枚通して好きなものは「言葉にならない笑顔を見せてくれよ」ぐらいしかないのだ。
Urb /Half (2005・平成17年)

類家心平が在籍したジャズ系ジャムバンドとでも言うべきか。ゼロ年代初頭はクラブ寄りな日本のジャズ・コンボが海外で注目されたがなぜかこのグループは日本のメジャー・レーベルからのリリースであった。様々なスタイルの曲が収録されている1stアルバムから類家心平のモーダルなこの曲を。売り出すタイミングと方法がもう少し違っていればもっとメジャーになっていたはず。
安室奈美恵 / Want Me, Want Me(2006・平成18年)

一時代を築いたが故に、セールスでの下降線を辿った安室がSuite chicの活動などを経て独自の道を歩んだ2000年代。先鋭的な国内外のプロデューサーと組み、メディアへの露出もコントロールしてチャートとは異なる路線を突き進む。アメリカでの流行を取り込みつつ妙な譜割りの歌メロや、ハイレベルなダンスはK-POPの先鞭をつけたような音楽性で、韓国のように国を挙げてのエンタメ売り込み作戦をしていれば彼女がBTS的存在になっていたかもしれない。自身のコピー「アムラー」を大量生産した彼女はしかし、誰も真似できない孤高のカリスマとなった。この辺りの活動方法は優秀なブレーンがいると思っていたがあっさりと引退したあたり彼女自身が相当頭がいいのかもしれない。孤高すぎて評価が全然追いついていないと思う。
Sleep Walker / The Voyage(2006・平成18年)

Mondo Grossoといえば今や大沢伸一のこ洒落たハウス系ユニットというイメージだがもともとはジャズ・ユニットだった(らしい)。そのメンバーだった中村雅人と吉澤はじめの結成したコンボ。やたらと「スピリチュアル・ジャズ」と言われるグループだがファラオ・サンダースを迎えた本曲含め、シンプルに素晴らしいジャズと言いたいところ。
Quasimode / Down In The Village(2006・平成18年)

クラブ・ジャズ、Nu(Nue)-Jazzが盛り上がった2000年代にスウェーデンのレーベルからリリースされ世界のフロアを賑わせたクオシモードによるタビー・ヘイズのカヴァー。U.F.O.の「Loud Minority」がクラブ・ジャズへのDJサイドからのアプローチだったのに対し、この曲はジャズ・コンボからのアプローチとなった。
B'z / ゆるぎないものひとつ(2006・平成18年)

自分の人生に欠かせないバンドだが、改めて考えてみると、好きなのはアルバム曲が多くシングルを選ぶのは意外と難しかった。2000代以降はチャート1位こそ継続していたけどセールスも影響力も落ち着き、本人たちのやりたいことをやって固定ファンが支持するというすっかりベテランになっていったし、個人的にもほとんど聴かない時期であったがこの曲は好き。B'zの曲にしては歌謡曲的な雰囲気が薄く乾いたミドルの曲調が心地よい。ファンの間では地味な曲扱いなんだとか。
オーサカモノレール / Groovy, Groovy, Groovy (Parts1&2)

日本が世界に誇る熱血ファンクと言えばこのバンド。
Mountain Mocha Kilimanjaro / 乱暴(2010・平成22年)

「薄汚いライヴ・ハウスから来た」どっかのバンドよろしく、自称「埼玉の粗大ゴミ」と言う1stがJazzmanからのリリースだったファンク・バンドの2nd「Uhuru Peak」より。一番有名な曲と勝手に思っていたけど他の曲はタイアップとかとっているみたいである。ざらついた演奏と音は まさに「乱暴」。もう活動してないのかな。
在日ファンク / 根にもってます(2014・平成26年)

浜野謙太率いるJBスタイルのファンク・バンド。フェラ・クティのアフロ・ビートの香りも漂わせつつ「歌詞・言葉」でもグルーヴさせるのは見事。解散以降いつの間にか「SAKEROCK=星野源がリーダーだったグループ」みたいな風潮になってしまったのはほんと不憫。
レキシ / 年貢for you feat.旗本ひろし、足軽先生(2014・平成26年)

在日ファンクが60s末~70sはじめのプリミティヴなファンクを下敷きにしていることに対し、レキシはもう少し後のスムーズなファンクやソウルの影響を受けているようだ。日本史をテーマにバカバカしくもためになる歌詞を心地よいサウンドに載せて歌うという謎の新発見。ceroとかSuchmos等を代表とする、一時シティ・ポップ・ムーヴメントなる流行も巻き起こした音楽も決して突然メジャー・シーンに現れたわけではなく、SAKEROCKやSuper Butter Dog、ズットズレテルズのようなブラック・ミュージックの影響を強く受けたグループの活動が下地にあったからの様な気がするけどどうでしょう。
まとめ
90年代までは流行の音楽を追って、ゼロ年代になると流行とは関係ない音楽も積極的に聴くようになった、ということがまるわかりのチョイス。U.F.O.はもちろん後追いでのリスニング。
以上。
今振り返ってみるとモノノケ・サミットやスーパーカー、B'zとかは他の曲がよかったなあ、とか
GlobeとかRip Slymeは入れなくてもよかったなあとか、
UAとか黒夢はもうちょっとうまく書けたなあとか、
安室いやに気合入って書いてるなあとか、
いろいろ思う所があるけどもう仕方ない。
もっとしっかり選盤して推敲した文にすればよかったね、って話でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
