
2024年大阪出張の記録 ①
小代焼中平窯の西川です(^^)
6月1日から開催されました大阪での個展に合わせて、5月31日から3日間大阪へ出張しておりました。
その大阪出張での記録を2回に分けてご紹介しようと思います。
まず最初に、5月31日に訪れた大阪市立東洋陶磁美術館について書いていきます。
大阪市立東洋陶磁美術館は長期間改修工事が行われていまして、2年前の大阪出張では訪れることができず、今回ようやく伺えました。
ちなみに改修工事前には2回~3回ほど伺っております。
館内は撮影自由とのことでしたので、展示品の画像を中心にこの記事を書いていきますね。


中国の鈞窯作とされる器です。
正確には原料が解明されていませんので、断定的なことは言いにくいのですが、小代焼に伝わる白小代・青小代・黄小代の伝統は源流をたどるとこの鈞窯へたどり着くと考えています。
今後の藁灰釉の参考のために撮影しました。

ふと見上げると陶製の鳥が居ました。
これは改修工事前から居ましたので、思わず心の中で「ただいま、お久しぶり」と挨拶していました。
個人的には東洋陶磁美術館のマスコットキャラクターだと認識しています。

国宝に指定されている8碗中の1つです。
東洋陶磁美術館の目玉であり、展示にも力が入っていました。
金属的な輝きがあり、万人が美しいと感じる逸品かと思います。
3Dでの体験コーナーもあり、作品解説も充実していました。


美しい青磁の小壺でした。
精緻な唐草模様が施されており、清涼感のある美しさに目を奪われました。
作り手の目線から見ても手の掛かる、繊細な作品です。


牡丹に魚という、なんともアベコベな文様が施された瓶です。
なぜ陸と水中を組み合わせたのか、想像もできません。
しかし、この間抜けな魚の表情が微笑ましく、傍らにずっと置いておきたいような瓶でした。


白磁の素材感が持つ清々しさを体現したような質感の扁壺です。
端正な作りですが、僅かに変形した器形や中心からズレた首など、日本人の美意識にも適う作品でした。

キャプションを撮影し忘れました…。
失礼しました…。
やや艶消しの黒釉がなんとも触覚を擽り、両手で包んで撫でまわしたい衝動に駆られる壺でした。
いずれ、再現したい釉調の1つです。


白釉が流し掛けされた水注です。
個人的にはこの作品に強く引き付けられた訳ではありませんが、私が小代焼を制作していく上での参考になると思い、撮影しました。
思い切りのある流し掛け模様です。


安土桃山時代の花生です。
「美濃伊賀」に分類される一品で、「古伊賀」と比べるとやや人為的な作為が勝ちすぎているきらいがあり、品格としては一段階劣るように見えます。
しかし、造形は生命力に漲っており、当時の破格の美をよく表しています。


桃山時代特有の形であり、同時代の志野焼等にも見られる形式の水指です。
備前焼は古い歴史を有しますが、このように造形力のある作品が作られたのは安土桃山時代になり、茶の湯が流行してからのことです。
備前焼の人間国宝・金重陶陽氏が桃山の古備前に引き付けられたのも頷けます。


堂々たる大作でした。
到底茶室で使えるようなサイズ感ではなく、おそらく当時は水甕や藍甕などの実用の甕であったはずです。
その体表にたっぷりと掛かる自然降灰釉のダイナミックな流れが力強く、焼締陶の美しさを教えてくれる逸品でした。


鳥や魚の模様がユニークな瓶です。
特に鷺を表したとされる模様はなんともユーモラスであり、まるで空想上の生物を描いているかのようです。
ジブリ映画「もののけ姫」の世界感を連想しました。



葡萄の茎が胴体をグルっと一周回った大胆な模様を施された壺です。
丸々とした力漲る胴体が非常に豊かな姿をしており、今後壺を制作する際に手本にしようと思える作品でした。
技術的には未完成とも言える鉄絵が、逆に情緒を感じさせます。


神への供え物として作られた白磁の馬です。
情けない垂れ目に哀愁があり、一見弱々しくもみえる不完全さと美しさが同居した動物置物でした。
まるで子供のような拙く幼い造形力が、この作品一番の魅力となっています。

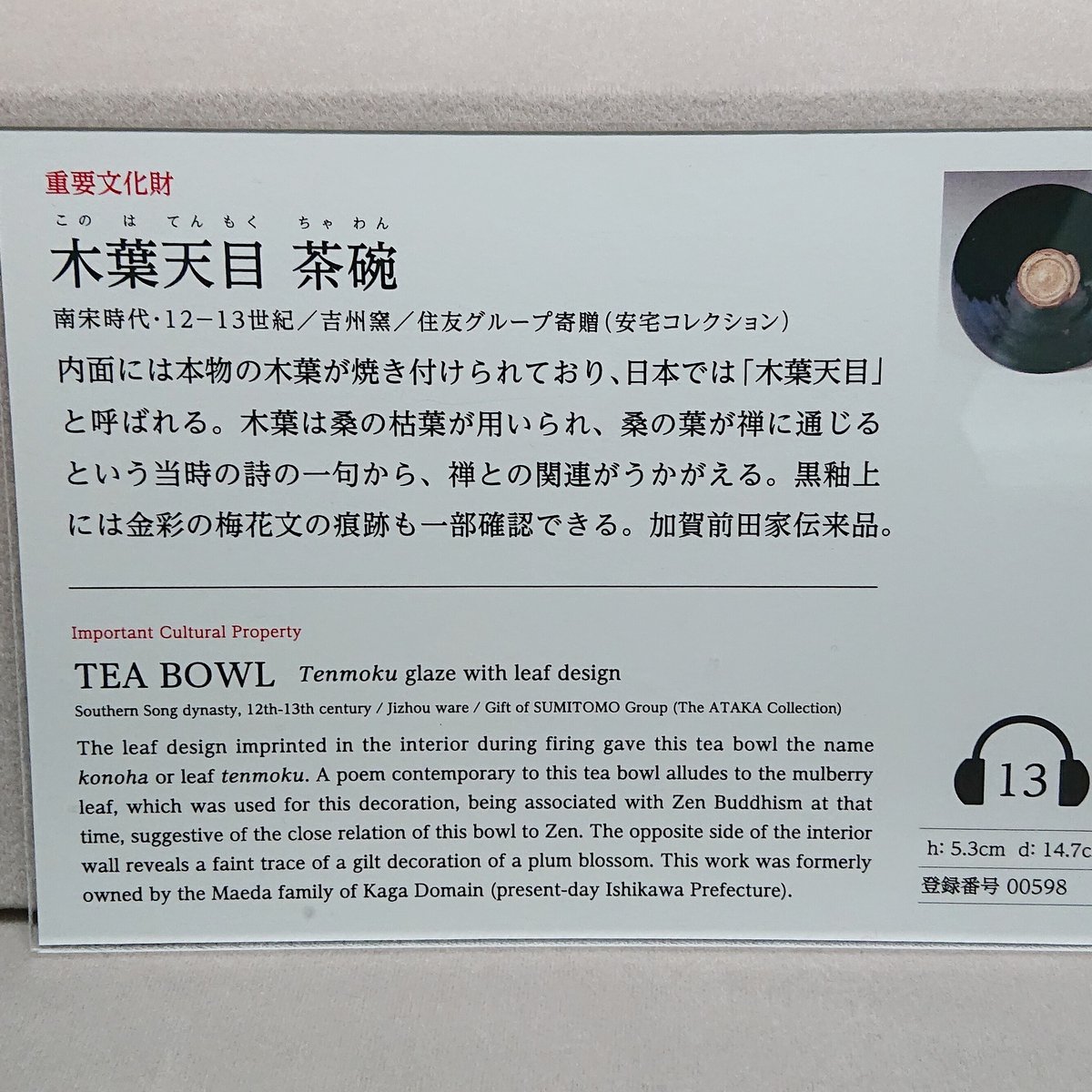
重要文化財に指定されている逸品です。
この作品に限らず、所謂天目形の茶碗も含めて意外と小ぶりな茶碗です。
木葉天目と言えば、日本で最初の人間国宝・石黒宗麿氏が思い出されます。
以上、大阪出張の備忘録でした(^^)
近いうちに第2回の記事も書く予定です。
2024年6月8日(土) 西川智成
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
