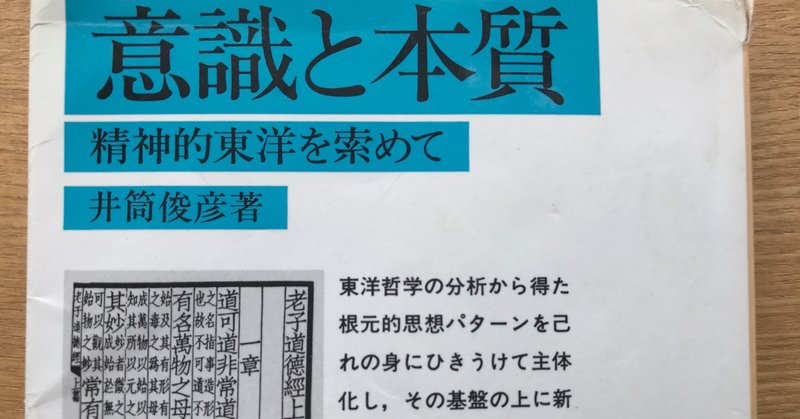
井筒俊彦『意識と本質』(7)
井筒俊彦の「意識と本質」をただ読むだけではなく、体系的に理解したいという思いで、章ごとに自分なりに概要をまとめてみる、という試み。
【基本的に『意識と本質』(岩波文庫)の本文を引用しつつ纏めています】
実際の禅の修行の過程は、「悟り」を頂点とした三角形の山の形で表すことができる。(この三角形の底辺の2点ABは経験的世界である。)底辺のAから頂点に向かう一方の線はいわゆる向上道、頂点から経験的世界の底辺Bに向かい下降線はいわゆる向下道である。向上道は「未悟」、向下道は「己悟」の状態。経験的世界から出発して上に登り、頂点の「悟り」に達してまたもとの経験的世界の次元に下降してくる。
禅者のあり方を示すこの「未悟(経験的世界)」→「悟(頂点)」→「己悟(経験的世界)」を、「本質」論の見地から「分節Ⅰ(経験的世界A)」→「無分節(頂点)」→分節Ⅱ(経験的世界B)」という形に置き換えてみる。
三角形の頂点をなす「悟り」すなわち無分節は意識・存在のゼロポイント。我々が普通、事物同士の間や事物と自我の間に認めている一切の区別、つまり分節がきれいさっぱり一掃された様態なのである。
それに対して三角形底辺の両端を占める分節Ⅰ・Ⅱは、事物が相互に区別され、またそれらの事物を認知する意識が事物から区別された世界、要するに我々の日頃見慣れた、普通の経験的世界である。分節ⅠとⅡは全く同じ世界であって、表面的には両者の間に何の違いもないように見える。しかし無分節という形而上学的「無」の一点を経ているかいないかによって、分節(Ⅰ)と分節(Ⅱ)は根本的に次元が異なる。なぜなら、どちらも等しく分節ではあっても、「本質」論的に見て、分節(Ⅰ)は有「本質」的分節であり、これに反して分節(Ⅱ)は無「本質」的分節だからである。
唐代の禅師・青原惟信の言葉からその流れについて見てみよう。
骨身を削る長い修業の年月を経て、ついに悟りが深まり、安心の境位に落ち着くことができて豊熟しきった青原惟信が禅者としての己の生涯を回顧して、これを三つの段階に分ける。
第一段階は禅の道に入る以前の時期。彼は普通の人の普通の目で、自己の外の世界を眺めている。山は山であり、川は川。世界は有「本質」的にきっぱりと分節されている。同一律と矛盾律によって厳しく支配された世界。山はどこまでも山であって川ではありえない、山は山の「本質」によって規定され、川はまた川の「本質」によって規定されているからだ。
ところが第二段階では、参禅して、ある程度悟りの目を開いてみると世界が一挙に変貌する。第一段階であれほど強力だった同一律と矛盾律が効力を失って、山は山でなく、川は川でなくなってしまうのだ。山も川も、あらゆる事物が、「本質」という留金を失う。それまで、いわゆる客観的世界をぎっしりと隙間なく埋め尽くしていた事物、すなわち「本質」結晶体が融けて流れ出す。存在世界の表面に縦横無尽に引きめぐらされていた分節線が拭き消される。もはや山は山であるという結晶点をもっていない。川は川であるという結晶点を持っていない。つまり、山はもう山ではないし、川はもう川ではないのだ。そして、そんな山や川を客体として自分の外に見る主体、我、もそこにはない。すべてが無「本質」、したがって無分節、もっと簡単に言えば「無」なのである。
第三段階は再び「有」の世界。第二段階でいったん無化された事物がまた有化されて現れてくる。第一段階の世界と一見少しも違わぬ事物の世界が目の前に拡がる。山を見れば、それは以前と同じく山であり、川を見れば、相も変わらぬ川。悟りが深まり安心の境地に落ち着くことの出来た達道の人の目に映るのは、第一段階と同じく分節された存在の姿、分節的世界なのである。だが、第一段の分節世界と第三段の分節世界との間には一つの決定的な違いがある。第一段階でそれぞれに「本質」を与えられ、整然と分節されていた様々な事物は、第二段階で「本質」を奪われ、分節を失う。第二段階から第三段階への移りにおいて、それらの分節は全部また戻ってくる。しかし、分節は戻るが、「本質」は戻ってこない。存在分節があるからには、もはや無一物の世界ではない。山は山として存在し、川は川として存在する。山もあれば川もある。だが、それらの山や川には「本質」がない。言い換えれば、それらの山や川は「本質」的凝固性をもたない山であり、川であるのだ。
第一段階、すなわち分節(Ⅰ)」は事物が不変の「本質」によって固定されているので、互いに混入し合うことはない。全ての存在は不透明である。山は川に対して不透明であり、川は山に対して不透明である。この「本質」はどこから現れるのか。大乗仏教の世界ではこれらの「本質」は人間の「妄念」によってもたらされると考えられる。本当はありもしない「本質」をあたかも実在するかのように錯覚するのである、と。我々の経験的世界、すなわち「現実」とは、この実在しない「本質」を元に作られた幻のような虚構に満ちた世界である、と考える。
その世界を妄念、妄想と認識し、経験的世界の全てが本当は無「本質」なのだと悟る時、人は「向上」の道への第一歩を踏み出す。妄想分別を取り払ってしまえば、「山である」と認識されているXと「川である」と認識されているYとの間に区別はなくなる。一切の存在者について我々の意識の妄想的分別、すなわち分節機能を停止してしまえば、全ては無分節、無「本質」、より禅的に言うならば「無」となる。しかし、それが単なる理性的な理解であるなら、表層意識を一歩も出ていない。表層意識で理解されたものは何であれ有「本質」的に分節されている。修行を通じて表層意識が完全に打破され尽くしたところに初めて現れる、深層意識的事態こそがこの三角形の頂点、「悟り」であり、無分節、「無」である。
しかし禅の説く「無」は絶対無分節者としての「無」ではあるが、静的な無ではない。それは不断に自己分節していく力動的、創造的な「無」である。分節に向かってダイナミックに動いていかない無分節はただの無であり、ひとつの死物にすぎない。それは禅の問題にする「無」ではない。禅の考えている「無」は宇宙に漲る生命の原点であり、世界現出の太源である。
だからこそ第三段階、「分節(Ⅱ)」では頂点である無分節の頂点から再び経験的世界に降りてくる。分節(Ⅱ)の世界は分節(Ⅰ)の世界と同様、山は山、川は川、花は花、とそれぞれの事物が分節された世界である。しかし分節(Ⅰ)が「本質」によって事物が分節されているのに対し、分節(Ⅱ)は事物は「本質」によって固定されていない、無「本質」的な分節である。分節(Ⅱ)の次元では、あらゆる存在者が互いに透明である。ここでは、花が花でありながら…あるいは、花として現象しながら…しかも、花「である」のではなくて、花「のごとし」(道元)である。「…のごとし」とは「本質」によって固定されていないということだ。この花は存在的に透明な花であり、他の一切に対して自らを開いた花である。分節(Ⅰ)の次元では、花は一つの、それ自体で独立した、閉じられた単体だった。花はすべての他のものにたいして固く自らを閉じていた。だが「本質」のない分節(Ⅱ)の世界に移される時、花は、頑なな自己閉鎖を解き、身を開く。
それでは、もともと「本質」に依拠するはずの分節がどのようにして「本質」ぬきで生起しえるのだろうか。
分節(Ⅱ)が分節(Ⅰ)と異なる決定的な特徴は、それが無分節と直結しているということにある。分節(Ⅱ)の世界は経験的世界のあらゆる事物の一つ一つが、それぞれ無分節者の「全体を挙げての」自己分節なのである。「無」の全体がそのまま花になり鳥になる。「分節(Ⅰ)」のように、現実の小さく区切られた一部分が断片的に切り取られて、それが花であったり鳥であったりするのではない。現実の全体が花であり鳥であるのだ。局所的限定というものが入り込む余地は、ここにはまったくない。つまり無「本質」的なのである。
こうして、無分節の直接無媒介的自己分節として成立した花と鳥は、根源的無分節性の次元において一である。このような境位において、このような形で分節された事物の間に、存在相通が成立するのは当然のことだ。花が咲き鳥が啼く。鳥と花とは互いに透明であり、互いに浸透し合い、融け合い、ついに帰して一となり、無に消える。だが、消えた瞬間、間髪を容れず、また花は咲き鳥は啼く。
電光のごとく迅速な、無分節と分節とのこの間のこの次元転換。それが不断に繰り返されていく。繰り返しではあるが、そのたびごとに新しい。これが存在というものだ。少なくとも分節(Ⅱ)の観点に立って見た存在の真相(=深層)はこのようにダイナミックなものである。分節された「もの」(例えば花)が、その場で無分節に帰入し、また次の瞬間に無分節のエネルギーが全体を挙げて花を分節し出す。この存在の次元転換は瞬間的出来事であるゆえに、現実には無分節と分節とが二重写しに重なって見える。それがすなわち「花のごとし」といわれるものなのである。
また、すべてのものがそれぞれ無分節者の全体そのままの顕露であるゆえに、分節された一々のものが、他の一切のものを内に含む。花は花であるだけではなくて、己の内的存在構造そのものの中に鳥や、その他一切の分節を含んでいる。鳥は鳥であるだけではなく、内に花をも含んでいる。すべてのものがすべてのものを含んでいる。
無分節者が不断に自己分節していく、その分節の仕方は限りなく自由。我々人間が、人間特有の感覚器官の構造と、コトバの文化的制約性とに束縛されながら行なう存在分節は、無限に可能な分節様式の中の、非常に限られた狭隘な一つであるにすぎない。例えば水を見る時、人間の限られた視点を超えて、もし天神や龍魚たちのより高次な視点で見れば、水は全く違って見える。しかしさらにそこをも超えて、「水、水を見る」ところに跳出しなければならない、と道元は言う。人が、天人が、あるいは魚が見る水ではなくて、水が見る水。
「水、水を見る」ここに分節(Ⅱ)はその幽玄な深みを露わにする。「水、水を見る」の境位は、人間の言語的主体性の域を超えている。そこに水を見る人間がいないから、「人、水を見る」のではなくて、「水、水を見る」のだ。すなわち、人間がXを見て、「水」という語を発し、水として分節されたXに水という「もの」を見る、のではない。水が水そのもののコトバで自らを水と言うのだ。水のこの自己分節を「水、水を見る」と言う。水そのもののコトバで、とは無分節者自身の生のコトバで、ということ。水が水自身を無制約的に分節する、それが水の現成である。だから、分節された水は明々歴々として現成するけれど、これに「本質」を与え、水を「本質」的に固定するような言語主体はここにはいない。しかしながら、水が水自身を水にまで分節するということは、結局、分節しないのと同じである。分節しながら分節しない、それこそが無「本質」的存在分節の真髄であると言えるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
