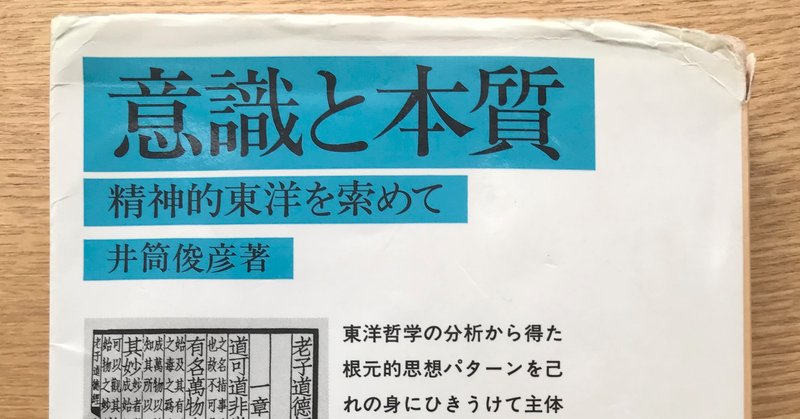
井筒俊彦『意識と本質』(2)
井筒俊彦の「意識と本質」をただ読むだけではなく、体系的に理解したいという思いで、章ごとに自分なりに概要をまとめてみる、という試み。
【基本的に『意識と本質』(岩波文庫)の本文を引用しつつ纏めています】
→Ⅰ章のまとめはこちら
〜井筒俊彦「意識と本質」Ⅱ章〜
井筒俊彦は、「本質」には二つあり、この二種類を意識的、方法論的に明確に分けた哲学の例としてイスラーム哲学を挙げている。神を唯一の例外として、あらゆる存在者に二つの「本質」を認め、区別している。ひとつは「マーヒーヤ」(māhīyah)、もうひとつは「フウィーヤ」(huwīyah)である。簡単に言うと「マーヒーヤ」は普遍的リアリティのこと、「フウィーヤ」は個別的リアリティのこと。
「マーヒーヤ」は語源的には「それは・何であるか・ということ」を意味する。例えば目の前に花がある時、「それは・花・である」つまり、目の前の「花」を「花」として成立させている「花」性のことを指す。
「フウィーヤ」は語源的には「これであること」いわば「これ性」を意味する。先の例で言えば、目の前の「花」自体がもたらす存在感、リアリティー、そのものの実感を表す。
井筒はこの二つの「本質」に対する異なる向き合い方をする作家や詩人を例に論を進めていく。
まずは本居宣長の「もののあはれ」。宣長は抽象的・概念的な思考を極度に嫌った。宣長にとって普遍的な「本質」つまり「マーヒーヤ」はひとかけらの生命もない死物に過ぎなかった。目の前の生きた事物を生きるがままにとらえること。自然で素朴な実存的感動を通じて「深く心に感」じることしか道はない。物にじかに触れ、その物の心を、外側からではなく内側からつかむこと、それが「もののあはれ」を知ることであり、そういうことのできる人を宣長は「心ある人」と呼ぶ。
次にリルケ。彼にとって、物をその普遍的「本質」すなわち「マーヒーヤ」を通して見ることは、その物から一回限りの独自性を奪ってしまい、「花」は「花」という個物ではなく、どこにでもある無数の「花」になってしまう。こうしてリルケは「マーヒーヤ」に背を向けて「フウィーヤ」に赴く。
リルケは「意識のピラミッド」について語っている。その頂点の表層意識は言葉の意味分節が支配する次元。そして底辺の深層意識はそのものが言葉以前にものとしてのリアリティーを開示する領域。
言葉の意味分節の力の及ばぬ深層領域に開示される「もの」の「フウィーヤ」を詩人は改めて言語化しなければならない。言語は基本、表層意識に属するものである。深層体験を表層言語によって表現しようとするというこの悩みは、表層言語を内的に変質させることによってしか解消しない。それはある意味、禅における「転語」のような状態。ここに異様な実存的緊張に充ちた詩的言語、一種の高次言語が誕生する。
次に『古今集』『新古今集』における「ながめ」。
『古今』的和歌世界は一切の事物、事象がそれぞれの普遍的「本質」において定着された世界。春は春、花は花、恋は恋というふうに自然界のあらゆる事物、存在者が普遍的「本質」的に規定され、もしその「本質」の網目から外れたりすれば、その意外性自体がひとつの詩的価値を帯びるほどの強力な規定性がそこにある。
いわゆる「マーヒーヤ」的「本質」が、ぎっしりと隙間なく充満するこうしたマンダラ的存在風景にあきたらぬ詩人たちは、王朝文化の雅びの生活感情的基底であった「ながめ暮らす心」を普遍的「本質」の消去の手段として、ひとつの特殊な詩的意識のあり方にまで昇華させた。「眺め」は『古今集』ではどちらというと淡い性的気分を表すものであったが、『新古今』的幽玄の世界では「眺め」とはむしろ事物の「本質」的規定性を朦朧化し、そこに生まれる情緒空間の中に存在の深みを得ようとするものではないだろうか、と井筒は言う。
「ながむれば我が心さへはてもなく、行へも知らぬ月の影かな」
「帰る雁過ぎぬる空に雲消えていかに詠めん春の行くかた」
(いずれも式子内親王)
月は照り、雲は流れ、飛ぶ雁が視界をかすめる。しかしこの詩人の意識はそれらの事物に鋭く焦点を合わせていない。それらは限りなく遠いところに眺められている。
「眺め」の焦点をぼかした視点の先で事物はその「本質」的限定を超える。そこに存在深層の開陳がある。だから「眺め」は「マーヒーヤ」の否定ではなく、「マーヒーヤ」を肯定するからこそあえてそれをぼかそうという態度が出てくる。
そして最後に松尾芭蕉。
全ての存在を存在たらしめているもの、永遠不易の普遍的「本質」、すなわち「マーヒーヤ」を芭蕉は「本情」と呼んだ。この「本情」を井筒は、花は花、月は月といった『古今』的な、感覚表層に現れる「本質」ではなく、事物の存在深層に現れる「本質」であると言う。
「物と我と二つになりて」つまり主体と客体が二分してその主体が自己に対立するものとして客観的に外から眺める次元を存在表層とよぶとして、ここで存在深層とはこの主客二分以前の根源的存在次元である。
「…の意識」はすでに主体客体が二分された存在表層の次元。これに対して根本的な変質が起こらないといけない。この変質を芭蕉は「私意をはなれる」という言葉で表現する。つまり二極分節的ではない主体として「もの」を見るということ。このような方向に自己を絶えず修練していくことを「風雅の誠」と芭蕉は言う。
しかし、美的修練をつんで存在深層が垣間見えるようになった人たちに、必ずしもあらゆるものの「本情」がつねにあらわれているわけではない。人はつねに「…の意識」で事物に接している。しかし『内をつねに勤めて物に応』じる特別な修練を経た人の実体験として、ものを前に突然「…の意識」が消える瞬間がある。そういう瞬間にだけものの「本情」がちらっと光る。「物の見えたる光」という一瞬のひらめく存在風景「物に入りてその微の顕れ」ること。
人の側では二極分裂の主体が意識の中で消え、ものの側では、普段深部にかくれて見えない「本情」が自らを現す。この時自己を開示するものは「本情」つまりは普遍的「本質」でなければならない。
この永遠不変の「本質」すなわち「マーヒーヤ」が芭蕉の実存体験において突然、瞬間的に生々しい感覚すなわち「フウィーヤ」に変わって現れる。「マーヒーヤ」が突如として「フウィーヤ」に転成する瞬間。この「本質」の次元転換の微妙な瞬間を間髪入れず詩的言語に結晶する。俳句とは芭蕉にとって、実存的緊迫に満ちたこの瞬間のポエジーであった。
いずれにしても普遍的本質である「マーヒーヤ」をそのまま受け入れるのではなく、個体的リアリティー「フウィーヤ」との関係性においていかに手触り感、実体感を得ていくか、という点で共通しているように思える。しかし、一方で「マーヒーヤ」をそのイデア的純粋性において直観しようとする人々がいる、と井筒は言う。詩人であるマラルメ、宋代の儒者による理学「格物窮理」を例に井筒は次に論を進めていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
