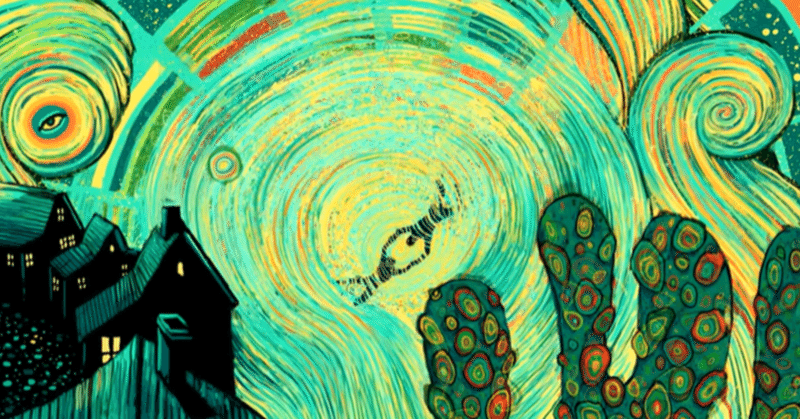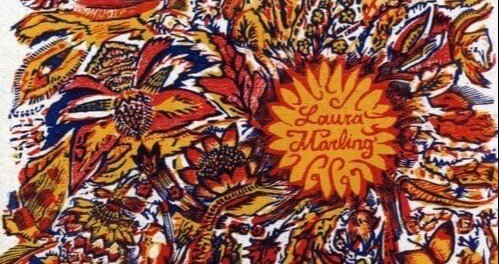
- 運営しているクリエイター
2023年12月の記事一覧

聴く「Screen」Visible Cloaks(2017 米国)・「Jupitor」Miyako Koda(1998 日本)
アルバム名「Reassemblage」は、ベトナムの映画監督:Trinh T. Min-haの1982年同名作に由来。 という解説で目にとまる。 トリン.T.ミンハさんの著書 「女性・ネイティブ・他者 ーポストコロニアリズムとフェミニズム」、 一読したが、結局、頭の中でまとまらなかったので、今年の心残り。 その方の、映像作品をアルバム名にしている Visible Cloaks(米国ユニット)は、何者かと思いましてね。 ミニマルミュージック、エクスペリメンタル・ロックなどと