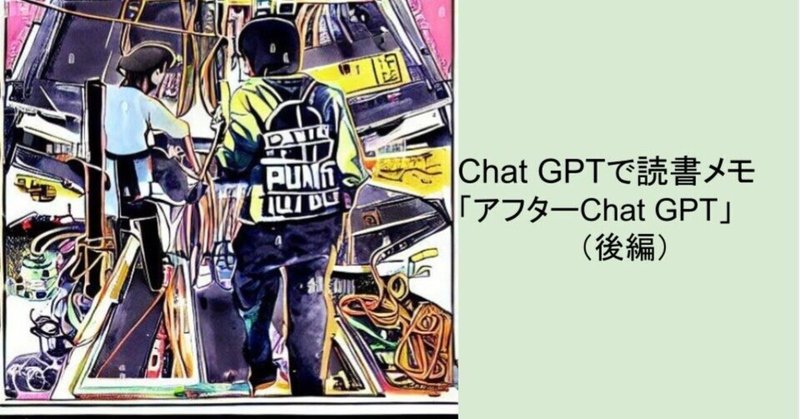
AIが人の心を、動かす。そのコツが手に入る1冊。後編【Chat GPTで読書メモをとる】
生成AIが言葉に関わる人のすべての営みに影響を与える。
小説を書く会社員K'です。AIで創作を、Chat GPTで小説を書いています。その創作の相棒であるChat GPTをより理解するため、よりいい小説をつくるための1冊を読みました。
AIが社会に実装される。その中で私たちはどうすればいいのか?
その答えを導くための大きな方向性が、この書籍「アフターChatGPT 生成AIが変えた世界の生き残り方」で多角的に考察されています。
この本では、生成AIの現状と未来、さらにはその社会への影響について幅広く説明されている。AIの便利さを享受する一方で、その限界と課題もしっかりと理解することです。
その上で、人間がどのようにAIと協働あるいは共存していくべきかのヒントを得ることができます。この知識が、今後の仕事やキャリアにおける方向性を考え、一歩目を踏み出すための大きな助けになる1冊です。
今回の記事は、前回の記事で提起したテーマに対する回答の記事となります。(この記事の問いとなる前回の記事は以下を御覧ください。)
それでは、どうぞ。
(この記事は、ほぼChat GPTに書いてもらっています。手を動かしたアクションは最初のコンセプト設計と最後の編集のみです。)
AIとのコラボレーションのカタチ
自らの価値を高めるために、AIとコラボレーションする新しい時代に踏み出すために、まず何をすべきか?
そのヒントとしてこの1冊から手に入れた3つのポイントを紹介します。
①生成AIが今なぜ社会に登場したのか。
生成AIが社会に登場した背景は、数回のAIブームと冬の時代を経て、特に第3次AIブームがその火付け役となっている。このブームの根底にはディープラーニング、特にニューラルネットワークという技術があり、これが人間の脳の仕組みを模倣する形でAIの学習を可能とした。
そこにクラウドサービスの普及が大量のデータの処理を容易にし、AIの学習におけるハードルを下げ、識別系AI(例えば、画像認識)で「生成AI」が注目を集めるようになったのは、「トランスフォーマー」という新しい深層学習モデルの登場が大きな要因となっている。
この「トランスフォーマー」という技術は、対話型AIや画像生成AIなど、テキストで指示を入力する生成AIの能力を飛躍的に高めた。
②AIと遊ぶという新しい視点がもたらすクリエイティブな可能性
生成AIが広範な産業で進化と導入を見せる中で、クリエイティブな仕事にも大きな影響を与えています。
イラストや文章生成のような領域でAIが活躍することにより、クリエイティブな職種が危機に瀕しているという見方もあります。しかし、この状況は逆に「AIとどうクリエイティブに共演するか」という新しい視点と可能性をもたらしています。
たとえば、AIが効率的に基本的なデザインや文章を生成できるとすれば、人間はより高度な戦略的思考や創造性を発揮する余地が広がります。法務や伝統的な技術のような領域でAIがルーチンワークを効率化すれば、専門家はより複雑で要求の高い問題解決に集中できるようになる。
要するに、生成AIと遊ぶ、つまり協働することで、これまでにない形のクリエイティブなアウトプットが可能となる。AIの進化とともに、人間自身の価値は「AIをどうクリエイティブな方向で活用できるか」によっても測られる時代が到来していると言えるでしょう。
効率化や業務支援を超えた、私たちとテクノロジーとの新しい関係性
「Microsoft 365 Copilot」の例を通じて、効率化や業務支援を超えた、私たちとテクノロジーとの新しい関係性が明らかになってきています。
生成AIは単なる効率化ツール以上の存在として、私たちの「副操縦士」として機能しているのです。この関係性で重要なのは、最終的な判断が人間にあり、AIはあくまで協力者やパートナーであるという認識を持つことです。
また、テクノロジーに対する新しいスタンスとして「差分を問う」アプローチが求められます。単に新しいテクノロジーを受け入れるだけでなく、それが従来の方法とどう違うのか、何を新しく提供できるのかを理解し、自らの手で試して学ぶことが重要です。
このようにして、生成AIや新しいテクノロジーは、私たちの生活や仕事において単なる「ツール」から一歩進んだ「協働者」へと位置づけられ、その結果、私たち自身の創造性や判断力も高まっていくでしょう。
この読書メモの取り方は次の記事を御覧ください。
*関連マガジン
*プロフィール記事
AIを使えばクリエイターになれる。 AIを使って、クリエイティブができる、小説が書ける時代の文芸誌をつくっていきたい。noteで小説を書いたり、読んだりしながら、つくり手によるつくり手のための文芸誌「ヴォト(VUOTO)」の創刊を目指しています。
