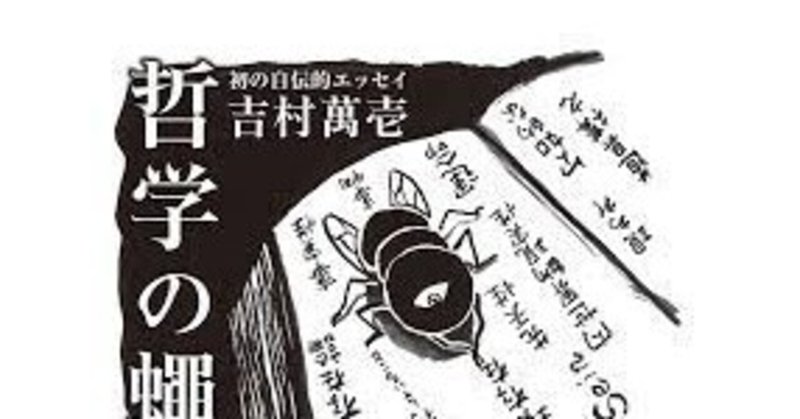
感想 哲学の蠅 吉村萬壱 とにかく強烈なんで勇気のない人は読むべからず。ある意味、これは人生を揺るがす名著です。

強烈でした。エッセイということですが、私小説でしょう。そこに哲学を絡ませている。自ら哲学に絡まりにいっている。混沌というのか汚というのか、衝撃的な読書体験でした。
冒頭、激しい異常な母親の虐待からはじまり、よくありがちな子供による虫殺し、犬殺し。大きくなってからは、女をまるで物みたいに扱い。変態行為の数々。この人芥川賞作家で、元教師。しかし、その実態はヤバい人。とてつもなくヤバい人でした。しかし、そこで語られる哲学というか生き様や考え方はとても面白かった。この本と出合えて良かったと思います。
o君という友達をいじめた吉村少年の異常さを示すこの文章が怖い。
私はその瞬間、さんざん我慢した小便を便器にぶちまけたような快感を味わった。
母親の虐待が、吉村少年をサイコパスにしたのだった。
学生時代に先生に言われた言葉が、吉村少年の精神性の背景になったのは確かだ。
文学を志す人間は、人と同じであってはいけません
二-チェとの出会いも彼を変えたと思う
すべての偉大なことは、市場と名声から離れたところで起こる。昔から新しい諸価値の創案者たちは、市場と名声から離れたところに住んだのだ。
のがれよ、わが友よ、きみの孤独のなかへ。わたしは、きみが毒バエどもによってさんざんに刺されているのを見るのだ。かしこへのがれよ、荒々しい強い風の吹くところへ。
ありのままの赤裸々な自分を友の前でさらけ出す
そういう考えにも反発する
これも二-チェの影響かな
きみは、自分の友人の前では、なんの衣服も身につけないでいたいと思うのか?
ありのままの君を彼に示すことが、きみの友人の名誉になるというわけか?。だが、そんなことをすれば彼はきみを悪魔にくれてやりたいと思うだろう。
ありのまま人間なんか、それは醜悪でしかない。
人は誰かといる時、それに適した仮面をかぶっているもので、そうすることにより円滑な関係性が保てるわけであり、小さな暴君に付き合う暇人などこの世界には存在しないのだと吉村さんは二-チェから学んだ。
自分を隠しだてしないものは、ひとを憤慨させる。
吉村さんは、フランクフルの夜と霧のような悲惨な文学作品や映画をたくさん見たり読んだりした。
普通は、嫌悪感とかを暴力に感じるのだが・・・
自分が虐殺されるという恐怖だけならまだ正気を保っていられたかもしれないが、私の中では虐殺する側のゾクゾク感もありありと渦巻いていた。
これは幼少期の屈折がもたらしたものか。
友達にこんなことを言われる
この言葉がとても印象的だった。
お前はかつて虐殺したことも、虐殺されたこともあるんや
吉村さんのこれも名言です。
世界は分からないことに満ちていて、わからないことの前では人は沈黙しなければならない
これは深い言葉です。
知らないのに知ったふりしているような人が、どんなに多いことか。
知らないのなら学べばいい。聞けばいい。
でなければ沈黙すべきだ。
教員養成大学の学生の時に一人旅行した感想も面白い。
電車が数秒の狂いもなく発着し、町にはゴミ1つなく、約束を守るのは当たり前で、水戸黄門の小さな印籠に額ずき、実態のない世間体を過剰に気にするような国は日本だけであり、我々は世界の中でもかなり特殊な国に暮らしているらしいと気付けるだけでも海外旅行にはメリットがある。
これはカミュの言葉だ。これも印象深い話しだ。
人間は、自分一人で、自分に固有な価値を創り出すことができるのか?。それが問題のすべてだ。
人は自分の価値を他者からの評価で確定している。それは他者に依存した価値である。それは自分の価値ではないと吉村さんは言う。
フォロアーの数とか、勤めている企業の名前とか、お金持ちとか
他者から誉めてもらえなきゃ自分に価値がないとか、そんなのおかしいということです。
大切なことは自分に固有の価値の創造ですと作者は言う。
いきなり、社会の教師をしていた時の話しになり
自分の変態ぶりを開陳するところがある
アパートの和式トイレに放った大便を発作的に握りつぶしたり、雨の中を濡れつつズボンの中で放尿しながら歩いたり・・。即ちそれは母の言う世間などの思い通りになりたくないという断固たる逸脱志向であり、また文学を志すものは、人と同じであつてはいけませんというT先生の箴言・・・
まるで不良少年ですね。やってはいけないことをやることで自分は他者とは違うと示す。
これが俺のアイデンティティーですみたいな。それを社会人になってからもしていたのが変。
私小説を描くことについての芥川賞作家の車谷さんの話しは面白い。
詩や小説を書くことは救済の装置であると同時に、1つの悪である。ことにも私小説を鬻ぐことは、いわば女が春を鬻ぐに似たことであって、私はこの二十年余の間、ここにしめした文章を書きながら、心にあるむごさを感じつづけてきた。併しにも拘らず書き続けてきたのは、書くことが私にはただ一つの救いであったからである。凡て生前の遺稿として書いた。書くことがまた一つの狂気である。
このエッセイじたい。この車谷さんの引用文の私小説そのものであり、それは狂気に近いと思う。
人はみんな、世間体とか常識に囚われている。
それについて作者が述べているところが面白かった。
人の道という人として踏み行うべき道があらかじめ決まっていて、それを踏み外さぬように生きていく人生が当たり前と考えられていることの背景には、彼らをそう信じ込ませる強大で暴力的な力の存在を感じる。彼らは刑務所や軍隊にいるのではない。市井に暮らす自由人であるにも拘らず、なぜ自ら進んで人の道という型に自他を嵌め込もうと腐心するのだろうか
この発想も面白かった。
例えば の という字を沢山書いていくと、やがてゲシュタルト崩壊が生じて の が の に見えなくなり、それを当たりの前の の に戻すためには一定の力を必要とするということが起こる。
馴染みのある の ですら油断すると意味不明な記号になってしまう。だから力づくで当たり前を維持し続けなくてはならないと思っている。
何かまとまりのない私小説であり、哲学でもある。
インパクトは強烈。
やたらと僕の心に爪痕残していきました。
また、再読したい、そんな本でした。
2022 3 19
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
