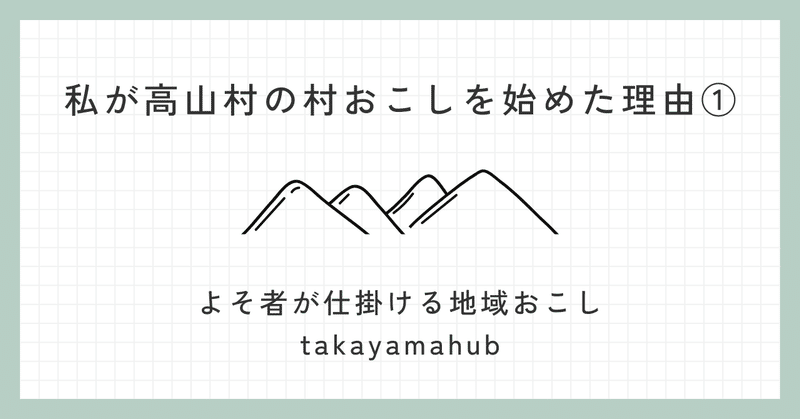
私が高山村の村おこしを始めた理由①
前回の投稿にも書きましたが、「どうして高山村の村おこしを始めたの?」と聞かれることが最近増えてきました。
生まれたわけでも育ったわけでも今住んでるわけでもない長野県高山村の村おこし。なぜそんなことを始めたのか、自分でもきっちりと言語かできているわけではありません。頭の中の整理も兼ねて、しばらくこのテーマで記事を書いていこうと思います。
まず頭に浮かぶ一つ目の理由としては 「やりたい!」と思ったこと。
当たり前?そらそうやろ?って感じ(笑)
ようは高山村という地に惚れ込んだのが第一の理由。
何にそんなに惚れ込んだのか・・・いくつかある気がします。
私が初めて高山村に訪れたのは2020年10月。
ふるさとプロボノ(*)という企画で「近年生産が増えてきたワインをテーマに村の観光を盛上げよう」というプロジェクトにボランティア参加したのがキッカケ。
たくさんの風景を見て回り村民の方々とふれ合ううちにすっかりこの地が好きになり、いつしか年に数回は関西から通う関係人口となっていました。
*ふるさとぷろぼの:地域活性化に取り組む地域内のコミュニティや団体と、地域外のビジネスパーソンをつなぐプログラム。
何度か通う中で感じてきた高山村の魅力とは・・・
古き良き日本の原風景
四季を通じて村を彩る自然、里山風景、夜になると降りかかる星、村のあちこちに立つ火の見櫓、昔から引き継がれる祭りや風習などなど。
見るもの、体験することの全てが都市生活とは異なる非日常。
村に来るたびに心身ともにリフレッシュし、エネルギーを充電してまた都市生活に戻っていく、そんな感じがしています。
個性的な観光資源
人口約6,600人の小さな村に、豊富な観光資源がキュッと集まっています。
秘湯好きが通う8つの温泉、裏見の滝・雷滝、非圧雪エリア7割で国内最長13kmのロングコースをもつヤマボクワイルドスノーパーク、春の五大桜と秋の紅葉など。
ひとつ一つがそれを目的に訪れるファンをもつ一級品の観光資源、「知る人ぞ知る」の集合体。
本物が集まる地の力
高山村は、標高が高く冷涼な気候、昼夜の気温差が大きい、年間降水量が少ない、砂礫質な土壌、長い日照時間など、果樹栽培に適した地域です。このような自然を活かして作られたりんごやぶどうは市場から高い評価を受けています。
ワインぶどうの質の高さで注目を集めていた地であり、さらにはここでのワイン造りを望む醸造家も集まり、村内には6軒のワイナリーが存在しています(2023/3月時点)。
地元の猟師で獲られた鹿や猪などのジビエ、山間の地で育った山菜やキノコなどの特産品が豊富。村の恵みに引きつけられた職人が根付き、この地の食材を最大限活かした料理を提供しています。
高山村には何か強力に人をひきつける力がある、そんな印象です。
ここに住む人々
親しみやすくオープンな性格で外部の人間をスッと受入れてくださる村民の皆さん。
どこにいっても気さくに話をしていただけ、何度か通ううちに友達?親戚?みたいな感覚がわいてきます。
村に行くのも「なにしよかなー」といった旅行感覚でなく、「○○さんに会いたいなー」という感じ。
私は、京都府北部の生まれですが、家から通える大学がないことから進学と同時に地元を離れ、その生活は今もずっと続いています。
地元に残った友人が少なく、年月の流れとともに家族や親戚も減って、最近では地元に帰る機会が次第に減ってきました。
そんな私にとって、昔ながらの仲間や親戚に会いに帰るような不思議な感覚をもてる土地、いわば自分にとっての第二のふるさとのように感じています。
ざっとこんな感じかなー。
考えたらもっと色んな魅力が出てくるんだろうけど、一旦こんな感じで。
とにかく、この地が好き、この地の人が好き。
日本全体に押し寄せる人口減少の波。
そんな中で今の高山村を次の世代にもその次の世代にもずっと残したい。
そのために何か自分にもできることあるのなら…それは迷わず”やりたい”。
そんな感情を抱いたことが、私がtakayamahubを始めた最もベースにある理由なんだろうと思います。
takayamahubでは、村の内外に関わらず、一緒に村を盛り上げていただける仲間を募集しています。
また、インスタ、ツイッター、Facebookで高山村に関する情報を日々発信しています。
ぜひ下記ホームページよりご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
