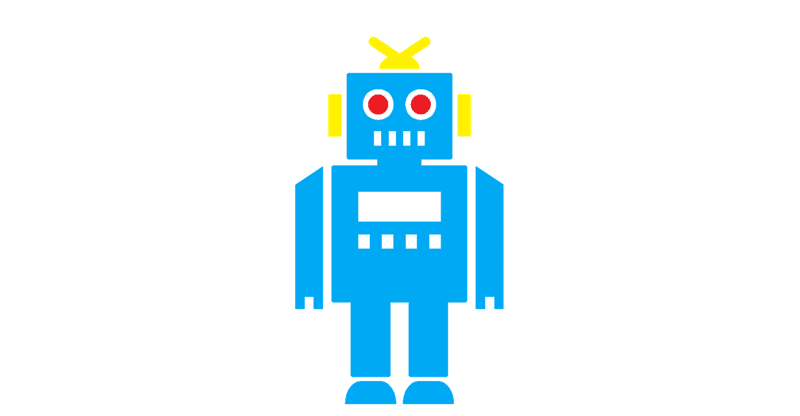
鉄の心を持つ彼女は
彼女の心は鋼鉄製だった。
とても頑丈で、壊れることのない彼女の心。心に限らず、彼女はそのすべてが鋼鉄製だった。腕も、足も、体も、顔も。彼女の見た目は古いブリキのおもちゃのロボットみたいだった。ぜんまい仕掛けで動くような、角ばっていて、動くときにはガチャガチャ音を立てるような。実際、彼女が動くとガチャガチャと耳障りな音が立った。もとい、ぼくはそれを不快だと思ったことはない。彼女の姿にしても、見る人によってはそれは醜いと感じる人もいるのかもしれないが、ぼくは一度としてそれが醜悪だと思ったことはない。なぜなら、ぼくは彼女に恋をしていたからだ。 恋は盲目、という言葉にぼくは首肯しない。ぼくが盲目なのではなく、世間に見る目がないだけなのだ。見た目がブリキのロボットであり、その声がスピーカーによって増幅された電子音でも、彼女が魅力的な人であるという事実は絶対的で、否定できないことなのだ。
「そんなことないよ」と、彼女は自嘲気味に笑いながら、そのスピーカーから電子音を鳴らしながら言う。「わたしはなんの取り柄もないから。だから」と言って、彼女は黙り込む。
彼女は失恋の痛手から回復していないのだ。彼女の心に刻まれた深い深いキズ。それは彼女がその姿になる前に負ったキズだ。
「もうあんな思いをしたくなかったから」と、出会ったばかりのころ彼女は言った。「わたしはキズつかないように、すべてを鋼鉄製に作り変えたの」
彼女の生身の体は放棄され、それと同じように脆く儚い彼女の心は鋼鉄製に作り変えられた。
「もう二度とキズつかないように」
「君は」と、ぼくは尋ねる。「それで幸せになれたの?」
夕方の公園、ぼくらは少し間をあけて座っていた。少し手を伸ばせば彼女の手に触れられるような距離。でも、ぼくは手を伸ばさない。好きな人の手に触れるのにはそれなりというか、相当の度胸がいる。ぼくの持ち合わせないものだ。あるいは、その触れた鋼鉄の手の、硬さや冷たさを感じることを恐れていたのかもしれない。彼女が鋼鉄製であることを実感することを。恋人たちが手を繋いでぼくらの前を通り過ぎる。彼女がその姿を目で追っているのがわかる。行き交う人は彼女を好奇の目で見ている。ぼくはその視線に気づく。彼女は気づかない。なにしろ彼女の心は鋼鉄製なのだ。そんなものにキズつけられるはずがない。彼女が心を痛めるのは、まだ鋼鉄になる前に負った心のキズだけなのだ。
ぼくはそのキズを負わせた人間のことを憎む。彼女が心を痛めているからだ。
「それで」と、ぼくは言う。「幸せになれた?」ぼくはそう言う。彼女をキズつけてやろうとして。
彼女は鋼鉄の肩をすくめる。「どうかな? わからない」
ぼくは肩をすくめる。彼女はキズつかない。なぜなら、鋼鉄の心を持っているからだ。鋼鉄を殴るみたいなものだ。痛むのはぼくの方だ。ぼくはキズつく。彼女がキズつかないからだ。ぼくは彼女が好きだ。好きだから、ぼくの一言でキズつき、喜んでほしい。けれど、ぼくのなにも彼女を一喜一憂させない。なぜなら、彼女の心は鋼鉄だから。だからこそ、ぼくは彼女をキズつけた人間を憎むのだ。そいつが羨ましいから。彼女をキズつけられたそいつのことが。ぼくなら、彼女をキズつけないのに。彼女が目で追う恋人たち。彼女はそこにかつての自分たちを見ているのだ。彼女と、彼女をキズつけたそいつ。そこにぼくはいない。
「君は」と、ぼくは言った。「幸せになっていいんだと思う」
「幸せ?」と、彼女は鋼鉄製の小首をかしげる。それが初めて聞く単語ででもあるかのように。「幸せ」
ぼくは意を決して、手を伸ばす。彼女の鋼鉄製の手を握る。それは予想通り硬く、冷たい。
「ぼくなら」と、ぼくは言う。「ぼくなら、君を幸せにできると、そう思うんだ」
彼女は首を回し、ぼくを見る。アイカメラがフォーカスを合わせようとしている。モーター音。
「わたし」と、彼女はつぶやくように言った。「もう幸せだよ」
ぼくは彼女を見る。
「絶対にキズつかないんだから、これ以上幸せなことって、ある?」
「そっか」と言って、ぼくはうつむいた。彼女の手の上に置かれた自分の手を見た。自分がとても間違ったことをしているような気がした。そして、その手を引っ込めようとした瞬間、水滴がぼくの手の甲に落ちた。雨? ぼくは思わず顔を上げた。彼女のカメラの目から、液体がこぼれている。
「あれ?」彼女が動揺した声を上げる。「なに? これ?」
それは次から次へと溢れてくる。とめどなく。それの流れていくところの鋼鉄が、どんどん溶けていく。冷たい光を放っていた鋼鉄が、溶けていき、その下から柔らかい肉が現れる。
彼女は夢中になって泣いた。泣いて、泣いて、泣いて、泣き続けた。涙が全身を洗い流し、そしてついに、彼女は生身の人間になった。彼女はその体を、ぼくに預け、さらに泣いた。
きっと、彼女は幸せになれるのだろう。でも、それは別にぼくが幸せにしたわけではない。彼女は自分を自分で幸せにするのだ。そうだとしても、それでいいと思う。
No.643
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
