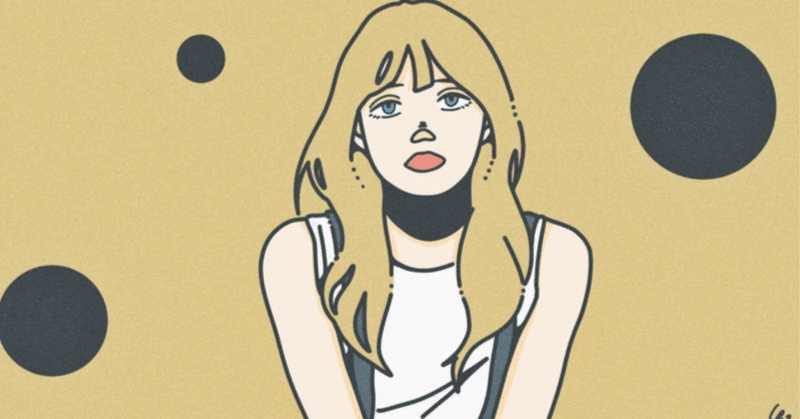
これは恋?
若いころ思いを寄せていた人の夢を見た。いや、その夢を見て、自分が彼女に思いを寄せていたということを理解したのだ。
目覚めたわたしは、自分の老いさらばえた手の甲を目の前にかざした。ああ、自分は老いたのだと、腑に落ちた。わたしは老いたのだ。彼女もまた老いたのだろう。どのくらい会っていないだろうか。わたしは横を向き、眠っている妻の背中を見た。妻もまた老いた。誰にも時間は平等である。そうしてときは流れていき、みな死ぬ。いたって平等だ。誰もそれから逃れられない。
わたしは妻を愛している。長年連れ添った妻だ。そもそもの始まりからして、愛しているからこそ結婚したのだ。そして、子どもたち。もう立派に独り立ちした彼らのことも愛している。それは間違いのない事実である。わたしは、わたしの家族を愛している。
しかしながら、わたしは夢を見た。そのことが、わたしを少なからず動揺させた。いや、嘘だ。動揺はしていない。その胸の高鳴りは、恋によるものだった。もう老い先短いわたしは、夢の中で恋をしていた。動揺はしていなかった。いや、動揺していたのかもしれない。夢の中のわたしはまだ若く、そして彼女もまた若かった。妻も、子どもたちは存在しないようだった。夢の中のことである。多少の理不尽は許されるだろう。妻も子どもたちも存在しないことに、夢の中のわたしは一切頓着していなかった。それよりも、目の前にいる彼女のことで頭がいっぱいだった。
彼女は、現実の彼女は、わたしの友人だった。あのころ、わたしは自分が彼女に思いを寄せているとは思っていなかった。それぞれに恋人がいたし、お互いの恋人のこともあけっぴろげに話していた。彼女もまた、わたしをただの友人としてしか捉えていなかったのだろう。わたしにしたってそうだ。わたしたちは友人だった。
夢の中のわたしは、彼女の腰に手を回した。まるで恋人同士がするように。彼女はくすぐったがって身をよじった。しかしながら、そこに拒絶の気配はなかった。わたしは彼女の顔を見た。彼女はわたしを見上げ、微笑んでいた。わたしも微笑んだ。若いわたしと、若い彼女だ。
あたりにはなにも無かった。茫漠とした空間だ。わたしと彼女しかいない。
「どうやら」と、わたしは彼女に言った。「ぼくは君に恋をしていたみたいだ」
「バカじゃないの?」と、彼女は笑った。
「バカみたいだ」と、わたしも笑った。そして、息をついた。「ホント、バカみたいだ」
わたしはじっと彼女を見た。
「なに?」
「これは、恋なんだろうか?」わたしは尋ねた。
「違うよ」と、彼女は言った。「君はわたしが好きなんじゃないし、好きだったんでもない」
「じゃあ」と、わたしは言った。「この思いはなんなんだろう?」
「君が恋しているのは、自分が恋をしていたころの自分、若かった自分。若い自分。わたしに恋をしてるんじゃない。そんなこともわからないの?」そういうと、彼女は笑い声を上げた。そして、わたしの手からすり抜け、駆け出した。
わたしは彼女を追いかけた。彼女は風のように走ったが、わたしも飛ぶように走れた。体が綿のように軽かった。息が切れることもない。わたしは走りながら笑っていた。彼女も笑っていた。
「捕まえた」わたしは彼女の腕を掴んだ。彼女は振り返り、わたしに微笑みかけた。わたしは息をついた。「行くんでしょ?」彼女は言った。
「そうだね」と、わたしは言った。「いつまでも、ここにはいられないでしょ?」
「そうだね」と、彼女は言った。
「うん」
「バイバイ」
「うん」
「またね」
わたしは目を覚ました。わたしはきっと、彼女に恋をしていたのだ。
No.996
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
