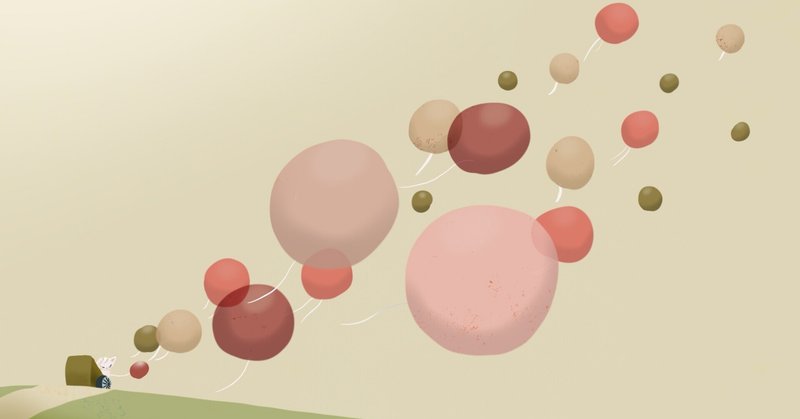
詩人はどこだ?
彼は武骨な人間だったので、芸術のようなものには全く興味が無かった。有名な画家の描いた絵画も、彼にとっては壁のシミも同然、音楽は耳障りな雑音だし、文学なんて戯言に過ぎなかった。壁を打ち砕くつるはしこそ現実であり、ボルトを締めるペンチのような実用性こそが尊ばれるものだし、食卓に並ぶ肉や魚、野菜や酒こそが求められるべきものだった。
そんな彼が恋をした。いや、恋に落ちたという方が正確だろう。それは有無を言わさぬ落下と同じだった。抗う術などなく、彼は真っ逆さまにそれに落ちていった。
とはいえ、武骨な彼である。その自分の胸の中に芽生えた感情とどうやって折り合いをつけるべきなのかが皆目わからない。四六時中それは彼の胸の中にあり、もぞもぞと彼を落ち着かなくさせる。いつでも相手のことを考えさせる。昼も夜も無く、いや、夜の方が症状はひどいかもしれない。実際に胸をかきむしり、煩悶し、寝床の中で右往左往する。ため息をつく。いつも心ここにあらずになる。周囲の人々は彼がなにか重い病気にかかったものと思い、盛んに医者に診てもらえと勧める。
「いや」と、彼は力なく首を横に振った。「違うんだ。医者じゃ治せない」
周囲の人々は首を傾げるばかり。もちろん、当の思われている人もそんなことは露も知らない。
そしてついに、彼の思いは彼の胸を破裂させるのだった。そこから奔流のようにほとばしって出たのは言葉だった。詩の言葉だ。それは彼の思いに形を与え、音を与えた。一幅の絵画よりも彩り豊かに、十曲の音楽よりも軽やかにかつ重々しく、軽妙で、洒脱、千の詩をしのぐ情感に満ち溢れ、言葉は言葉を呼び、それによって感情がさらに生まれ、また言葉が呼び出され、それによって編まれていく文章は春の草木のように繁茂し、花を咲かせ、甘美で、艶やかな香りを振りまいた。彼は自分の中にそんなものが収まっていたことに驚いたが、同時に納得もしていた。それまでの重々しいものが、そのいちどきで軽くなったのだ。そのくらいたくさんの言葉が詰まっていなければ、その重々しさの説明がつかない。
彼から溢れ出た言葉は人々を感動させた。美しい詩であり、甘美な文学、それは本になり、飛ぶように売れた。比喩ではない。広場に群れなす鳩たちが飛び立つみたいに、本当に羽が生えているかのようにそれは次から次へと売れていった。記録的なベストセラーだった。
誰もが彼をほめそやした。本が売れたために彼は巨万の富を築くことになった。テレビやラジオに引っ張りだこ。一躍時の人である。しかしながら、彼はそんなものに興味はない。どこかいつも寂しげで、そうした世間的な成功に無頓着なように見えた。そして、それがまた彼の本の、そして彼自身の人気を高めることになった。さらに本は売れた。しかしながら、それは彼の求めるものではなかった。彼の求めたのは恋の成就することである。それ以外にはなんの価値もない。
そしてついに、彼の思っていた人が、その彼の言葉に打たれたのだった。彼の恋は成就したのだった。めでたし、めでたし。
めでたし、めでたし、ハッピーエンド、とはいかなかった。その恋が成就すると、彼はなにも書けなくなった。それはそうだろう。彼の胸の中にはもう言葉が残っていなかったのだ。恋が叶い、愛になり、日常になる。もちろん、彼は彼なりに愛の言葉を囁こうとしたのだけれど、元が武骨な彼である、それは日に日に空疎なものになり、彼自身も嫌気がさして、ついにはそんな甘い囁きもやめてしまった。
世間は世間で彼に二作目を求めた。彼は四苦八苦しながらなにかを書こうとしたが、出来上がるのは目も当てられないようなものばかり、紙屑の山だけだった。
そして、日は過ぎた。かつてのベストセラー作家も完全に過去の人である。
「ああ、あったね、そんな本。懐かしいな」みたいな感じ。
そして、彼の愛もまた、日にさらされ、色あせていっていた。当初の輝きは失せ、くすみ、ホコリすらかぶっていた。それは時間の問題だった。
「別れましょう」というセリフも、あまりにも予期されていたものだから、むしろやっと出て来たか、という感じだった。
とはいえ、失われてみればそれは輝きを取り戻す。過去の愛ほど甘美なものもあるまい。身勝手なことだ。
そして彼は、その失恋の詩を書いたが、それはちっとも売れなかった。
No.458
兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。
1話から100話まで
101話から200話まで
201話から300話まで
noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。
よろしければ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
