
味覚に偏在する音楽会:落合陽一x日本フィル、そして私たちが音楽会になる
過日、赤坂にあるサントリーホールにて、落合陽一×日本フィルハーモニー交響楽団(以下、落合陽一x日本フィル)による「偏在する音楽会」が開催されました。
同主催者による音楽会は今回で6回目で、私も何度か参加しているのですが、カコイチ素晴らしい内容だったと思います。
この記事では、音楽会を振り返りながら、クラシックのホールコンサートの面白み、次の音楽会はどうなるのか?などについて述べたいと思います。
前日譚:ラストワン土器、クラウドファンディングのお祭り感

落合陽一x日本フィルによる音楽会は、毎回クラウドファンディングによる資金調達が行われています。
実際にコンサートを訪れる人だけでなく、このプロジェクトのビジョンや活動内容に共感した人が応援できる仕組みがあるということは、クラシック音楽の持続可能性の観点からも素晴らしいと思います。
参加する身としては、このクラウドファンディングの時期から音楽会が始まっていると言え、コンサートのコンセプトや、仕掛けられている色々のギミックやそれの意味するところが明らかになったり、クラウドファンディングが達成されるのか否かを見守る、という体験を得ることができ、エンターテイメント性も拡張されていると言えると思います。
クラウドファンディング最終日には、落合陽一氏によるTwitterスペース(ライブ配信)が配信されました。
配信開始時には、目標金額5,000,000円に対して、達成率は80%程度、1時間弱で約100万円の追加支援を得られなければクラファン達成ならず、という状況でした。
落合陽一氏自らこの音楽会のステートメントや意義について語りながら、支援を呼びかけ、Twitterのハッシュタグ「#偏在する音楽会」のツイートを読み上げ、参加者の質問に答えるなどしながら、クラウドファンディングの進捗を実況中継する様子は、非常にエンターテイメント性が高く、毎回これが楽しみなのでギリギリまで支援しないという人もいらっしゃるとのことでした。
特に、特別なリターンが付いた高額のプランでの支援が入ったときなどは、「あと1つ土器が入れば達成!」などと盛り上がり、私も「ラストワン土器!」などと合いの手を入れ、追加の支援を行ったりして楽しみました。
(補足:リターンに、国宝:火焔型土器の精巧なレプリカがもらえるプランがありました)
クラウドファンディングは、締切の直前で目標対比106%程度で見事に達成、配信に参加した人みなで喜び合いました。
ミュージサーカスは縁日の祭囃子

そんなわけで、参加者はコンサートの鑑賞以外にも様々な形でプロジェクトを楽しむことができるのですが、コンサート当日の昼間には、サントリーホール前のカラヤン広場でミュージサーカスが開催されました。
ミュージサーカス(Musicircus)とは、ジョン・ケージが作った造語で、様々な演者が同じ場所で同時に、独立した演奏を行い、聴衆は会場を自由に歩き回って鑑賞するというものです。
演奏には、黒猫のマスクを被ったDJトラーズも参加していました。
コンサート当日は平日だったため、私はこれに参加することができなかったのですが、友人らがFacebookライブで中継しているのを移動の合間などに鑑賞し、その様子を楽しみました。
まるで子どもの頃、縁日の日に、遠くから聞こえる祭囃子に気持ちをはやらせながら、家の用事を片付けているときのような特別な感情を抱くことができました。
コンサートを鑑賞するという体験だけでなく、年に一度人々が集い、楽しみ喜び合うという祝祭性を持ったプロジェクトであり、音楽会が私たちの生活にとって一つの社(やしろ)になっていると感じました。
オーケストラのホールコンサートにお金を払っていいと思っている理由

私は普段骨伝導イヤホンを常用しているので、音楽もそれで聴くことが多いのですが、ほとんどの人にとって音楽を聴く場合、イヤホンやヘッドホンなどオンイヤーなデバイスを通じて聴くか、アンプとスピーカーからなるサウンドシステムで聴くことが選択肢になっていると思います。
オンイヤーな再生デバイスが耳周辺のごく小さな範囲の空気しか振動させないのに対して、サウンドシステムでは鑑賞者の周囲の空間を含めたより広範囲の空気を振動させています。
クラシック音楽をホールで演奏する場合、そのホールは演奏をよく反響し、音楽体験をより豊かなものになるように設計されています。
コンサートホールはその空間自体が大きな反響装置で、空間全体が音楽によって振動し、それを全身で感じることができます。
人間はこの空間全体の響きが好きなようで、音楽を聴くための施設だけでなく宗教施設など様々な建造物でこれが試みられてきましたし、ポピュラー音楽の歴史の中でも、マルチトラックの録音素材をLRの2つのチャンネルにミックスダウンする際に、空間の響きをエミュレートしたエコー・リバーブ成分を付加してリッチな音像を作り出そうと試行錯誤がなされてきました。
私たちが、空間的な響きとして認識している音像は、音源から直接発せられ最初に聴覚に到達する直接音と、自分の方向とは別の方向に発せられた音波が、壁や天井に跳ね返って耳に届く反射音、さらにそれが反射し続けることで音が持続しているように聞こえる残響音によってできていると分解することができます。
つまり、人工的なエコー・リバーブ成分を付与していない録音したそのままの音に、少し遅れて聞こえる最初の反射音を模した音と、反射音が空間内で繰り返し反響する残響音を模した音を足すことで空間の響きを再現しようとしている、ということになります。
私もバンドなどをやっていた時期に、ミックスダウンでそのような作業を行ってきましたが、人工的な残響音や反射音を付与することで、オンイヤーの再生デバイスや、サウンドシステムで再生するに最適な響きを付与することはできるのですが、出力装置がLRの2つのチャンネルである以上、全身が音楽に包まれるような体験を作り出すのは非常に難しいのです。
オンイヤーの再生デバイスやサウンドシステムでは、その3つの音が、LRの2つの出力装置から出力されています。
対してコンサートホールでは、実際に自分がいる空間内で反射した音が、360度、全方位から聞こえるわけで、これがまさに音の満ちた空間の中にいるような、他で得難い体験をもたらしてくれるのだと思います。
このために鑑賞料金を支払うことは、十分に意義があると考えています。
オーケストラヒット、コンサートホールを一つの楽器に変える圧倒的な演奏能力

1980年代のシンセサイザーには、オーケストラヒットという特徴的な音色が搭載されていました。
形容するなら、「ジャン!」と言った感じの、音域のひろい派手な音色で、オーケストラが一斉に一つの和音を演奏したときの音色を再現したものです。
これに「ヒット」という打撃感のある命名をしたのは言い得て妙で、前述のようにオーケストラのコンサートホールでの演奏において、全ての楽器が一つの和音を同時に演奏するような場面では、まるでオーケストラを含む周辺の空間全体が打ち鳴らされたような、大音量で低音から高音まで非常にレンジの広いパワフルな音が発せられます。
言葉で言うのは簡単なことですが、オーケストラのような大編成で、しかもそれぞれ異なる発音方式、異なる音域の様々な楽器が、同時に鳴らされていると感じるような演奏をすることは非常に高度な技術だと思われます。

バンドをやったことがある方ならわかるかもしれませんが、ライブを聞いていて心地よい、気持ちが盛り上がる、かっこいい、乗れる、と感じるような演奏は、個々の演奏者の技巧的な高度さよりも、バンドがまるで一つの楽器と感じられるようなリズム感の良さにあると思われます。
バンドが一定のテンポをキープしたり、一体的なリズムを生み出すためには、個々の演奏者の演奏スピードが同じである必要がありますが、ドラムなどのリズム楽器が陣頭指揮を取るような形でバンド全体のテンポをキープしたり、モニターイヤホンなどを使って演奏者全員がガイドリズムを聴きながら演奏したりしますが、これだけでバンドのリズムに一体感が出ることは稀だと思います。
つまり、ドラムの演奏を見る、ガイドリズムを聞く、というインプットのところで音を合わせようとしても、自分の楽器の音が出力されるには、脳から手足を動かせと言う信号を発し、それを受け取った手足が実際に手足を動かし、音を発する楽器の箇所に達することで初めて音が発生するわけで、必ず時間差が発生するのです。
合わせなければいけないのは、個々の演奏者の出力された音のタイミングであって、弾くタイミングでは無いと言うことです。
なのでバンドは繰り返し演奏練習をするなどして、演奏者間のズレを体感的に認知して修正し、バンドそれぞれのリズム感を体得していかなければなりません。
目や耳などの感覚器官や、それを処理する認知機能、またそれを実際の演奏に反映する運動機能、どれも人によって千差万別であり、一つの成功事例が全てのバンドに応用できる、と言うこともありません。
バンドメンバーそれぞれのリズムに対する感性に不一致があったりすると、「リズムが揃っている」と言う共通認識を形成することが難しく、さらに困難になります。
これは大変な労力を要する工程です。

話をオーケストラに戻しますと、オーケストラには管弦打楽器それぞれに低音域から高音域まで複数パートがあり、各パートに複数の演奏者がいます。
楽器ごとに発音のメカニズムが違い、演奏方法も違います。
打楽器のように音の立ち上がりが速い楽器もあれば、弦楽器のように音がゆっくり立ち上がる楽器もあります。
高音域の楽器は音の周波数が高く(つまり波形が細かく)、低音域の楽器は音の周波数が低い(つまり波形が大きい)という違いもあります。
つまり、楽器ごとにある音を演奏したときにピークの音量を発生するタイミングがバラバラだということです。
これをオーケストラが一つの楽器だと感じられるような精度で合わせるというのは一体どうなっているのでしょうか?
技術レベルが高度すぎて、どのような感覚でそれを捉えているのか、全く想像がつきません。
また、直感的には、非電気楽器の生演奏よりも電気的に増幅された楽器の演奏の方が音量が大きいと考えられるかもしれません。
クラシックギターの音よりも、アンプに繋いだエレキギターの音の方が大きそうな気がしませんか?
しかし実際には、電気的に増幅した音には、その扱える電気量以上の音量は出ないという上限があります。
しかし、生演奏には理論上音量の上限値がありません。
オーケストラの大編成で、幅いろい音域の、様々な発音方式の楽器が、一斉に大きな音量で演奏したときに体感できる音量は、巨大な音像に全身を打たれるような強烈な体験です。
これらのことから、オーケストラの演奏をコンサートホールで鑑賞することは他に得難い体験だと考える次第です。
オーケストラの演奏で寝るのは最高!

先ほどまで述べていたことが台無しになってしまいますが、全身を音で包まれる空間の中で、目を閉じて微睡むのは非常に心地よい体験です。
かつて胎内にいたときには、血流やその他の生体活動に由来する様々な音に包まれていたでしょうから、それに近い体験と言えるのかもしれません。
しかしながら、落合陽一x日本フィルのコンサートは、聴覚だけでなく視覚にも刺激的な演奏になっています。
今回のコンサートでも、舞台に高輝度LEDを使ったであろう非常にレスポンスが速く、かつ輝度の高いモニターがおそらく50個ほど並んでいて、音楽だけでなく映像も同時に演奏されるダイナミックなパフォーマンスでした。
これは眠ってしまっては勿体無いと思い、音楽を鑑賞しながら自分の中で何か別の感覚を喚起してみようと実験をすることにしました。
今回のコンサートでは「きのこ」が一つのキーワードになっていて、MCでもジョン・ケージの「と音楽はエンサイクロペディアで隣同士に並んでいますよ」というジョークが紹介されていました。
きのこから着想して、音楽を食べてみてはどうだろう?と閃いて、音楽を聴きながら、コンサートホールに手を伸ばして、音を摘んで口に運び、もぐもぐ食べてみる空想をしながら鑑賞してみました。
(何を言っているかよくわからないと思いますが、あまり深く考えてないでください)
マスクの下で、口をもぐもぐ動かしながら音を咀嚼してみると、この音は甘いな、この音は苦いな、など味覚が喚起されるのを感じました。
さらには食感や温度、調理方法など、自分がこれまで食べたことがある食べ物、例えばほうれん草のおひたしとか、丸ごとの果実だとか、繊細な技巧を凝らした高級な料理だとかが想起され、より味覚の解像度が上がりました。
初めて聞くような実験的な音像では、もぎたての野菜だとか、荒っぽい調理方法の料理のような、混沌とした味を感じ、オーケストラのために作曲された楽曲では、丁寧に下拵えされた繊細な料理のような味を感じました。
かと思えば形容し難い音もあり、また何か味は感じるが、これまでに自分が知らない味がするなど、聴覚と視覚の刺激から味覚を喚起するという全く個人的な新しい体験をすることができ、非常に楽しかったので、他の場面でもやってみようと思います。
誰かと一緒にやっても楽しいかもしれませんね。
地球大好き!ストラヴィンスキー

コンサートのほとんどは前述のような珍妙なひとり遊び的な鑑賞を楽しんでいたのですが、後半のクライマックスは、ストラヴィンスキーの「火の鳥」の演奏でした。
終盤のダイナミックで明るいテーマを繰り返すパートは、喜びに満ちていると言うか、地球(あるいは世界、または人間)讃歌といった感じで、大変エモーショナルで大好きなのですが、演奏のクライマックスでは音楽そのものの力に圧倒されると言うか、全身の全巻かくが音楽に打ち鳴らされるような体験ができて素晴らしかったです。
落合陽一氏が、コンサートのMCの中で何度も「喜び合いましょう」とおっしゃっていました。
ストラヴィンスキー自身がそのように考えてこの曲を作ったのかどうかはわかりませんが、喜び合うためにこの曲が演奏されたのだとしたら感動的なことだと思います。
私たちが音楽会になる

今回の音楽会を通じて、聴覚・視覚・味覚など複数感覚による音楽の受容(または喚起)、そしてミュージサーカスによる同時的体験から、現在のステージと観客席が分かれている形態から、それらが混じり合った、境界のない無い音楽会がいずれやってくるのでは無いかと言うインスピレーションを得ました。
音楽に打ち鳴らされる私たち自身もまた楽器であり、時間的空間的な境目の無い音楽体験を通じて、この世界の全てが音楽であると感じられる日がきっと来るのだと、音楽会を振り返って想像しています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
Reference
落合陽一 × 日本フィルハーモニー交響楽団
遍在する音楽会|8/25 世界は、音楽に満ちている
https://readyfor.jp/projects/vol6
音楽会は、2022年9月4日まで配信されています。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
日本フィルハーモニー交響楽団
https://japanphil.or.jp/
※定期会員券、セット券、寄付などで活動を応援することができます
社をつくり、祝祭を司る。デジタルの身体を手に入れて、両面宿儺になる。
※本文中で触れた、社(やしろ)の概念について記した記事
この記事の挿絵に使った、Midjourneyが生成した画像とプロンプト







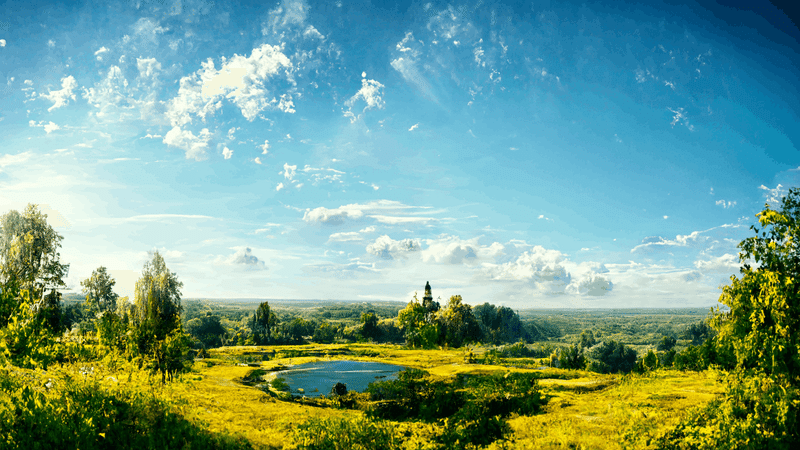

Midjourneyをはじめてみよう!すぐに始めたい人向け導入ガイド
Midjourneyをはじめて見たい人向けに書いた導入ガイド的な記事です
2022年8月29日公開
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
