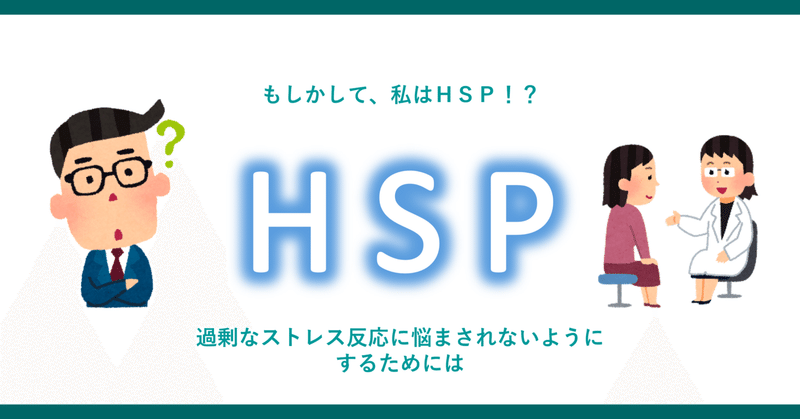
「HSP」って何?
みなさんはHSP(エイチ・エス・ピー)というワードをお聞きになったことはありますか?最近はメディアや書店店頭でも「HSP」に関する情報や書籍があふれています。MRC札幌にも「自分はHSPじゃないか」「HSPの治療方法を教えてほしい」というご相談を寄せられることが増えてきました。
「HSP(Highly Sensitive Person=高度に敏感で繊細な人たち)」は、精神医学上の疾病名称ではありません。アメリカのアーロン博士により提唱された心理傾向の概念です。「HSP」は、人の気落ちや音・香り・光などの外的刺激に敏感な人たちのことです。些細なことに疲れやすかったり、他人の感情に共感しすぎて巻き込まれて苦しい思いをしたり、ハッキリとノーを言えずに不本意な頼み事を押し付けられるなど、そんな自分のことを強く責めてしまうという傾向があるとされています。
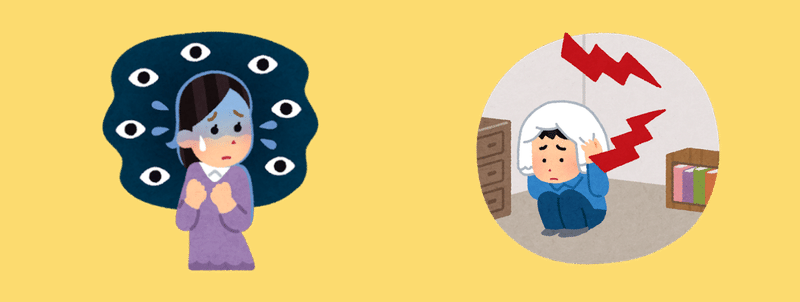
「HSP」の人には4つの属性があるとされています。
D:丁寧で深い処理が出来る(Depth of processing)
O:過剰な刺激を受けやすい(Over aroused)
E:感情の反応が強く共感力が高い(Emotional reactivity and high empathy)
S:些細な刺激にも反応する(Sensitivity to subtle stimuli)
これらの頭文字を取って「DOES」と呼ばれることもあります。
最近では人間関係に疲れてしまい、今までのめりこんでいたSNSなどを利用した他者との関わりを、前触れなくいきなりシャットアウトしてしまうケースも多いと聞きます(一部のメディアや情報では「人間関係リセット症候群」という表現をしているようです)。人間関係をリセットしたときはスッキリするかもしれませんが、リセットを繰り返すうちに、他人との関係を構築することを回避して困難になったり、信頼関係を結べなくなっていくかもしれません。少しでも、過剰なストレス反応に悩まされないためにも 以下についてご案内いたします。
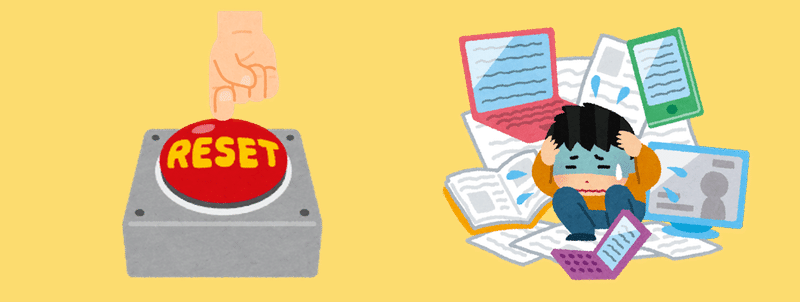
◆対策としてできること
① 無理して共感しすぎない
相手の意向を読みすぎたり、汲み取り過ぎたりすると、次第に追い込まれて苦しくなります。愚痴などの特にネガティブな内容の、他人の発言を極端に受け止めすぎないようにしましょう。人は人、自分は自分という、良い意味での割り切りが必要です。
② 人と上手に無理せずに距離を置いてみる
相手のことを考えすぎて、自分のことよりも相手に合わせがちなため、さほど興味のないことにも関心を示しすぎたり、ノーといえずに不本意なことに巻き込まれてしまうことも考えられます。
「仕事が忙しいので会う時間が取れない」「今、急ぎの要件があるからまたいずれ」など、距離を置く意志を明確にしてみましょう。
ただしあまり強く関係遮断すると誤解をされるので、強い表現になりすぎないようにしてみましょう。
③ 気分的にも鬱々したり、体調も芳しくないようなら医療機関受診を。
我慢しすぎたり、距離の置き方に苦慮していると、次第にこころとからだにもさまざまな反応が出てくることも懸念されます。眠れなくなってきた、食欲が低下した、些細なことで緊張する、呼吸が乱れる、頭痛が続いている、下痢や腹痛がある。。。等々があれば専門医の受診も検討してみましょう!(EAP相談室も是非ご活用ください!!)
悪いことばかりじゃない!?
ここまでHSPについて書かせていただきましたが、HSPだからと言って悪いことばかりではありませんよということもお伝えしておきます。
例えば、共感力が高いので気配り上手であり多くの人から好意を得られたり、想像力が豊かなので芸術家(音楽家、作家、ライターなど)として活躍したりするケースもあるかもしれません。現状を悲観するのではなく、自分の能力はどのような場面で力を発揮することができるのか・活かすことができるのかを考えてみるのもよいことでしょう。
\\読んでいただきありがとうございます//
★最新記事のお知らせ
気づけばもう11月!
インフルエンザも大流行中ですが、
気温差による体調不良にもお気をつけください!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
