
沖縄組手の衰退
以前、アメブロのほうでこんなメッセージをいただいた。いわく、その方は喜屋武朝徳のある系統を長年学んできたが、型しか稽古しない。組手について質問すると、「型だけ稽古していれば、組手も十分に強くなれる」と返事が返ってくる。喜屋武先生は組手の写真を残しているが、組手は稽古していなかったのでしょうか云々と。
筆者が知る限り、喜屋武先生が組手を稽古していなかったという事実はあり得ないように思う。以前紹介したように、近年、喜屋武先生の組手本が発見された。戦前の空手家の中には、本では組手の写真を掲載しているがそのときだけで、普段の稽古では組手を教えていなかった人もいたようだが、喜屋武先生はそういう人ではなかった。
本部家には、喜屋武先生と本部朝基は親戚同士で一緒に組手を稽古していたという口碑も伝わる。また、沖縄では「チャンミーグヮー」と「モトブザールー」の武勇伝はもっとも多いと聞く。実際、沖縄の地方自治体が発行する地方史に収録されている民話では、この二人の逸話は圧倒的に多い。二人は戦前の沖縄では組手に比重を置く「実戦派」として知られていた。
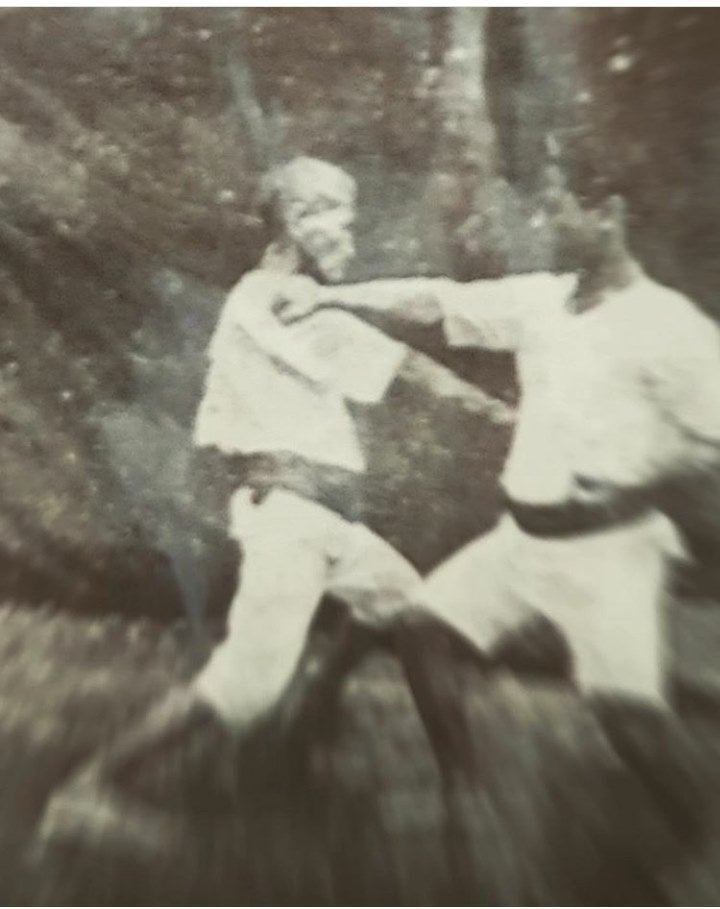
それで、どうしてその方の系統では組手を稽古しないのか、正直、筆者には分からない。ただ、戦後の沖縄空手の主流では、組手を忌避する傾向があった。一言でいうと、組手は野蛮人のするものだという考えである。そうした風潮の中で、ある種の「同調圧力」が作用して、組手の稽古をやめてしまったのかもしれない。
たとえば、以前、武芸館の比嘉清彦先生から、小林流の知花朝信先生は組手を教えていなかったという話を聞いた。清彦先生の尊父、比嘉清徳先生は上原先生の初期弟子だったが、その前には知花先生のもとでも学んでいた。「全く教えていなかったのですか?」と尋ねると、全く教えていなかったという。
おそらく型稽古が中心だとは想像していたが、知花先生が全く組手を教えていなかったという事実は意外であった。その後、同じ話を複数の小林流関係者からも聞いた。しかし、昭和30年代の沖縄では、それが普通だったそうである。その当時、沖縄で組手を稽古していたのは、沖縄拳法、一心流、本部流(本部御殿手)など少数で、沖縄空手の主流派からはしばしば異端視されていた。
喜屋武先生は嘉手納で教えていたので、首里や那覇の人たちからは「田舎手」と揶揄されることもあった。もちろん、生まれは首里で、出身の喜屋武殿内は沖縄でも屈指の名家である。本来なら、喜屋武先生を田舎者呼ばわりできる者などいないのだが、戦後はそうした出自も忘れさられて、何かと喜屋武系統は肩身の狭い思いをしたのかもしれない。それで、主流派への同調圧力が働いたのかもしれない。
沖縄では、1987年の海邦国体の少し前、1980年代になってから組手が盛んになった。これは国体の空手競技で、本場沖縄は負けるわけにはいかないと、組手稽古を強化したからである。しかし、国体のルールは、もちろん本土の空手諸流派が制定したものである。
そういうわけで、沖縄古来の組手というものは衰退してしまった。本来の「沖縄組手」がどういうものか、(一部を除いて)わからなくなってしまった。だから、喜屋武先生の組手本が注目されているのも、衰退した沖縄組手の解明の手がかりが得られるかもという期待もあるのかもしれない。それゆえ、将来は研究が進めば一度衰退した伝統がふたたび復活する可能性もある。
出典:
「沖縄組手の衰退」(アメブロ、2021年8月21日)。note移行に際して一部加筆。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
