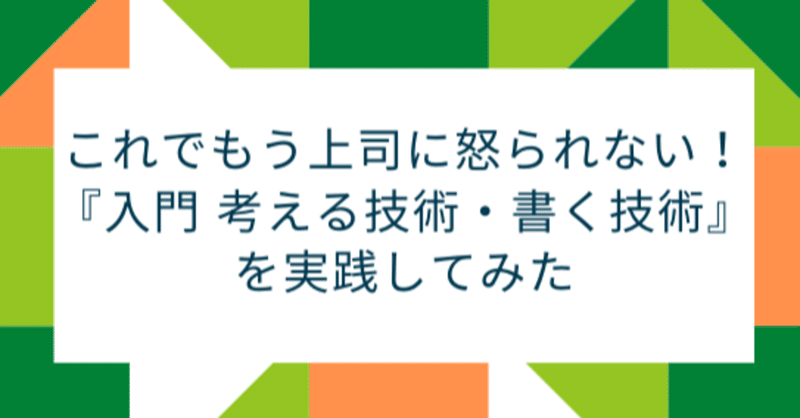
これでもう上司に怒られない!『入門 考える技術・書く技術』を実践してみた
第五弾は『入門 考える技術・書く技術』
「この本、役に立つの?」
そんな思いを持った方の少しでも力になれればと思い、始めた文章ノウハウ本実践シリーズ。5回目の今回は『入門 考える技術・書く技術』を実践してみました。ベストセラー『考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則 』の入門編である本書は、転職時にお世話になったエージェントにオススメしていただきました。ビジネス文書において欠かせないエッセンスが詰まっている本書を熟読し実践したおかげで、私は履歴書の通過率は90%を超えました。お世話になった文章ノウハウ本を改めて、文章を作成する過程とともにご紹介したいと思います!
著者は山﨑康司さん。コンサルティング業務では様々な大手企業で「考える技術・書く技術」関連の教育・研修などを行っています。原著の訳者でもあるため、「考える技術・書く技術」のプロとも呼べるでしょう。本書は原著でも紹介しているピラミッド原則で文章を書く方法を学べます。練習問題も多く用意されているため、入り口として最適です。
本記事では
・エンジニア採用が上手くいっていない顧客企業への提言
をテーマにピラミッド原則に基づいた文章術を紹介していきます。
設定
あなたの顧客企業はエンジニア採用に悩んでいたとします。なにせエンジニア採用はとても難しいのです。スキルのある人を採用するときの倍率は100倍を超えます。しかし、スピード感持ってプロダクト開発するため、テック系企業にとってエンジニア採用は、注力すべき活動の一つです。あなたの顧客は採用ノウハウがなくエージェントに頼むべき、と考えていた際に意見を求められました。どう答えましょう。
ステップ① OPQ分析をする
OPQ分析とは、読み手 = 顧客の理想(Objective)と問題(Problem)、疑問(Question)を整理することです。今回の場合は
O スピード感持ってプロダクト開発をしたい
P 技術力のあるエンジニアがいない、リソース不足
Q どうしたら技術力のあるエンジニアを採用できるのか?
今回の相談はエージェントに頼むべきか、でした。これはすなわち、どうしたら技術力のあるエンジニアを採用できるのか、という疑問です。OPQ分析をすることで、言葉通りに疑問をとらえるのではなく、真の疑問に気づけます。
ステップ② 主メッセージを決める
OPQ分析ができたら、顧客企業への主メッセージを決めましょう。
今回の相談に一言で答えるとしたら、エージェントに頼むべき、もしくは頼むべきでないでしょう。私は頼むべきではない、と考えました。頼むべきでない、としたので代案も主メッセージに含めたいと思います。今回の僕の主メッセージは以下です。
エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべき
ステップ③ 根拠を集める
主メッセージが決まったら、その根拠を集めましょう。主メッセージにとっての根拠は、家の土台のようなものです。土台がしっかりしていなければ、家は地震が来たらすぐに崩れてしまいます。根拠が揃っていなければ、その主メッセージは反論が来た時にすぐさま説得力を失ってしまうでしょう。だから、根拠は必要なのです。根拠になりそうなものを集めてみました。
( i ) 自社での採用成功経験がなく、ノウハウを溜める必要があるから。
( ii ) ノウハウを溜めることで継続的かつコスパの良いエンジニア採用の成功につながるから。
( iii ) 短期間での採用が見込めるから。(例えばある採用支援会社は半年で6人のエンジニアの採用に成功したこともある)
( iv ) 主流になりつつあるダイレクトリクルーティングは工数かかり難易度が高いが、プロに頼むことで効率的に行えるから。
集めすぎると最終的に作成する文章が長くなってしまうので、絞っています。基本的には2~5つと言われています。ただなんだか根拠として適切でないものが入っていそうな予感がします。次は、更にこの中から根拠として適切そうなものを絞り込みましょう。
ステップ④ ロジックが正しいかチェックする
このステップが一番大事です!!ロジカルでない文章は説得力に欠けます。ロジカルが正しいかチェックしてあげましょう。
では、一体どうやって確認するのか?実は、ひとことを主メッセージと根拠の間に入れてあげるだけで良いんです。実際にやってみましょう!
( i ) エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきである。なぜそう考えるかというと、自社での採用成功経験がなく、ノウハウを溜める必要があるから。
( ii ) エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきである。なぜそう考えるかというと、ノウハウを溜めることで継続的かつコスパの良いエンジニア採用の成功につながるから。
( iii ) エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきである。なぜそう考えるかというと、短期間での採用が見込めるから。
( iv ) エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきである。なぜそう考えるかというと、主流になりつつあるダイレクトリクルーティングは工数かかり難易度が高いが、プロに頼むことで効率的に行えるから。
こうしてみると、根拠として ( ii ) が正しくなさそうですね。( ii ) はノウハウを溜めた上でのメリットです。文章にする際は ( i ) に紐づけるのが良さそうです。
ロジックが正しいかのチェックは一見難しいように思えますが、たったひとこと主メッセージと根拠の間に加えて文章にしてみることでできるんですね。
ステップ⑤ 根拠の具体例を用意する
あともう一息です。頑張りましょう。
文書にするときは根拠の具体例を示してあげます。( i ) に関しては ( ii )が具体例になりそうでしたので、試しに文章にしてみます。
エージェントは利用せず、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきである。なぜそう考えるかというと、自社での採用成功経験がなく、ノウハウを溜める必要があるから。ノウハウを溜めることで継続的かつコスパの良いエンジニア採用の成功につながる。
このあと文言を修正する必要があります。しかし、修正しなくても根拠が力強くなった印象です。そうです。具体例は、根拠を強くする装備みたいなものなんです。根拠が綿密に考えられたものであれば、それだけ主メッセージの説得力が増します。
ステップ⑥ 文章にする
ようやく文章の作成です。ステップ①〜⑥で集めた材料を文章にしていきましょう。なお、例文に出てくるデータに関しては、偽物ですのでご了承ください。
〇〇株式会社 鈴木様
先日御社からご相談いただいたエンジニア採用の件、私なりに見解をまとめました。
結論から言えば、エージェントに頼った採用ではなく、エンジニア採用の実績がある採用支援会社の支援を導入すべきだと判断いたしました。以下、3つの観点からその根拠を説明いたします。
・再現性のあるノウハウ蓄積
・短期間でのリードエンジニア採用の実現
・ダイレクトリクルーティング
1 再現性のあるノウハウ蓄積
採用支援会社の支援を導入することで自社にエンジニア採用のノウハウが溜まります。具体的には
・採用コストの低いWantedlyの運用方法を学べます。自社にそのノウハウを蓄積することで、今後エンジニア採用に充てる採用活動費が年間で4分の1に削減できます。
・自社ブランディングの知見が得られます。エンジニア採用をする上で自社ブランディングができている企業とそうでない企業の間に、エンジニア採用の成功率は約30%の開きがあります。
2 短期間でのリードエンジニア採用の実現
また、短期間での採用が見込めます。
・ある採用支援会社の実績には、半年で6人のエンジニア採用に成功しています。リードエンジニアほどの技術スタックの人材をこれほど採用することは、エージェントに頼むだけではまず不可能でしょう。
3 ダイレクトリクルーティング
欲しい人材をピンポイントで狙うダイレクトリクルーティングは工数かかり難易度が高いですが、プロに頼むことで効率的に行えます。
・2019年に上場したweb系企業20社のうち、19社がダイレクトリクルーティングを実施していました。
・リードエンジニアクラスの採用手法のほとんどが、リファラル採用とダイレクトリクルーティングです。
これらの見解にご同意いただけたら、早速採用支援会社の選定に入ります。今月末までには選定作業を終え、検討結果をご報告できるよう準備いたします。ご意見を至急いただきたくお願い申し上げます。
思考を文章にし、少し体裁を整えただけでそれなりの報告メールが作成できました!
今回は文章を作成する前に思考を整理する時間が多くなりました。それだけ相手を説得したり、興味を呼び起こす文には準備が必要ということです。
※あれ、根拠がなかなか見つからないぞ、、ってなったときは
主メッセージが間違っているかもしれません。主メッセージを変えると一から根拠の集め直しですが、そうやって繰り返し繰り返し考え直された意見は強い説得力を持ちます。最初のうちは面倒臭いですが、特訓を重ねれば慣れてくるはずです。僕もまだまだこれから特訓の日々が続けていきます!
ピラミッド原則に基づいたライティング術で上司を見返してやりましょう
・報告書
・意見書
にはピラミッド原則による文章術が最適です。また、この思考法自体はプレゼンなど意思決定が必要な場面でかなり有効に利用できます。これで上司にも怒られることはなくなるはずです。文章に自分なりの考え、意見が入る際はピラミッド原則に基づいて意見を育ててみてくださいね!
今回の記事を読んで、『入門 考える技術・書く技術』が気になった方はこちら↓
入門編を終えたらこちら↓
サポートありがとうございます!頂いたサポートは自己啓発のための書籍代に使わせていただきます!!
