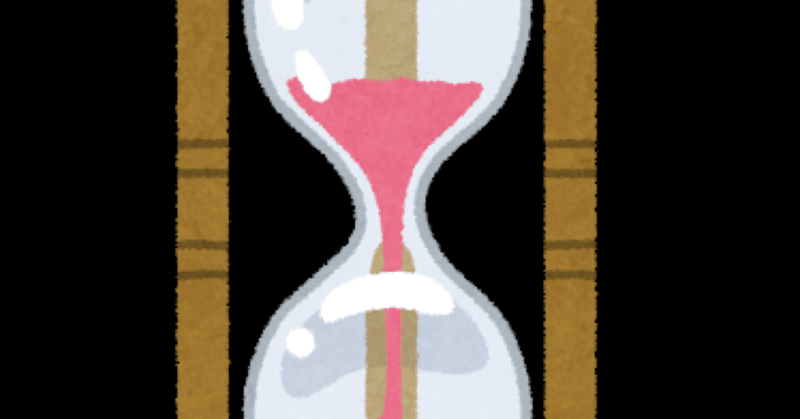
【仕事の改善】どこを改善するのか?
皆様、こんばんワン😸
会社に入社してから今まで改善を続けてきているのですが、一つ明確に見る目線が変わったタイミングがありました。
そのきっかけになったのが、この本です。
製造業をやられている方ならご存知の方も多いと思いますが、エリアフゴールドラット博士が書かれたザゴールです。
この本は、5年ほど前に参加した異業種交流会がきっかけで知りました。
私の会社では、コロナになるまで他社との交流会を行っており、私と一緒に仕事をしていた方が参加されていて、
「他の工場も見学できるし、すごい面白かったですよ!」
と言われたことと、さらに前から見学してみたいと思っていたグループ会社へ見学に行けると言われたこともあり、参加を決めました。
その交流会では、各会社の次期リーダー候補が参加して、それぞれの現場を見て回り、意見交流会ののち、半年かけて自社を改善し、その結果を報告しそれに対してさらに意見を交換するといった流れで、開催していました。
そのうちの一つの会社でされている改善として説明されていたことが、この本に沿った改善の方法でした。
その会社も、私の会社と同じように受注設計生産品を扱っていたのですが、私たちの生産の半分くらいの工期で製品を完成させており、成果を出しておられました。
その会社の生産本部長から話を聞いた時に
「これこそが、うちの会社が取り組むべき考え方ではないのか?」
と雷に打たれた感覚でした。
「同じスタイルのものづくりやし、同じことをすれば成果が出せるはず!」
と考え、早速この本を読むことにしました。
かなり分厚い本で、読む前は読み切れるかな?と不安だったんですが、いざ読み始めるとストーリー仕立てで実際に試行錯誤のステップを踏みながら読んでいけるため、飽きずに一つずつ段階を経て理解できる非常に読みやすい本でした。
この本の内容は、制約条件の理論(theory of constraints)について書かれており、そのマネジメント手法はTOCと呼ばれています。
TOCとは、
自分の仕事は他の仕事とつながっている
各仕事のパフォーマンスにはばらつきがある
という前提であれば、制約に集中して改善することで、全体に成果をもたらすことを示した科学的な理論です。
具体的な例として、本の中で紹介されているのは、ボーイスカウトでのハイキングを例に説明されています。
主人公は、ハイキングの引率を頼まれて、指定の時間までに目的地に辿り着くために、子供達を率いて進んでいきますが、予定通りに進むことができません。
計算上では、間に合うはずなのになぜ遅れるのか?考えていくうちにあることに気づきます。
それは、どれだけ一人一人の歩く速度が早くても、一人遅い人がいると全体の歩く速度も遅くなるということです。
ハイキングのゴールはみんなを時間通りに目的地に連れていくことがゴールなので、遅い人間を置いていくわけにはいきません。
そこで、足の遅い人の荷物を他の人が持ったり歩くのをサポートすることで、最後には時間通りに辿り着くことができました。
このことが示しているのは、
みんなが手伝うことで、ゴールが早まる。
まさに制約に集中することで、成果が上がることが示されています。
それと同時に、制約と違うところを改善しても、制約の能力が上がらなければ改善の効果はない。ということも証明しています。
この理論を読んだ時に、今まで自分が感じていたモヤモヤが吹き飛んで自分のやるべきことがすごくクリアになり、視界が広がる感覚がありました。
この本を読んで以降、何かを改善する時には必ず
今の工程のボトルネックはどこか?
どうすればそこを改善することができるか?
を常に考えて改善するようになりました。
皆さんも、改善してもなかなか成果につながっていないと感じている方がいるのではないでしょうか?
そんな時は、自分の仕事のボトルネックはなにか?一度考えてみて、そこの能力を最大化することに注力してみてはいかがでしょうか?
ってなとこで今日はおしまいです😼
ご覧いただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
