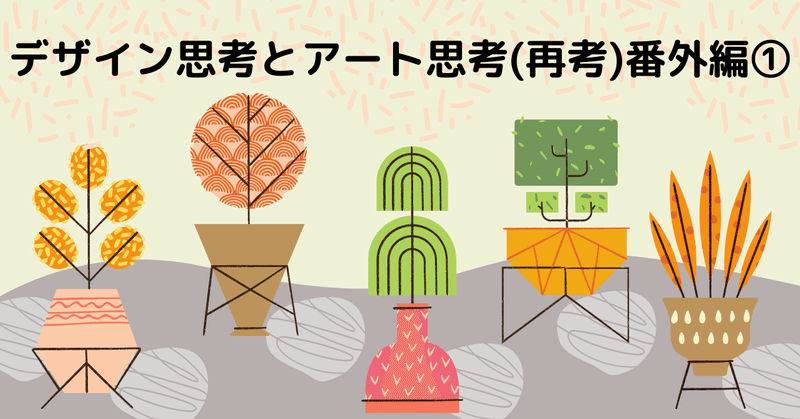
デザイン思考が苦手なこと
デザイン思考が苦手なことについては、様々なことが言われているが、ここでは、それらを理由と共に整理してみたい。
1.3つのFが苦手?
まず、デザイン思考が問題解決活動の一種であることを鑑みれば、それに馴染まないものは扱いづらいということになる。この点につきヒントをくれそうなのが、消費者行動論での情報処理モデルを巡る議論である。消費者行動論では古くから、情報処理モデルでは快楽的消費(Hedonic Consumption)を上手く説明できないとされてきた(Hirschman and Holbrook,1982)。
ここでいう情報処理モデルとは、消費者は買い物を行う際に、自ら情報を探索してそれを評価し、主体的に選択していると考えるモデルのことであり(Bettman,1979)、それはSimon(1978)のいう問題解決プロセスと類似している。さらに、そのモデルでは、消費者が「ファンタジー(fantasy)、フィーリング(Feeling)、ファン(fun)」(3F )などを求める快楽的消費については説明できないとされてきた。情報処理モデルでは、限定されているとはいえ、一応合理的な意思決定を前提としているため、過度に情緒的で非合理的な意思決定を取り扱うことは苦手なのである。
そして、このような考え方を援用すれば、(需要側と供給側の違いはあるものの)問題解決活動の一種であるデザイン思考も同様に、ファンタジー、フィーリング、ファンなどの消費者の感情経験を革新するような製品やサービスを作り出すことは苦手と見做すことができるかもしれない。具体的には、楽しみや喜びを提供する娯楽的要素の大きいゲーム(ビデオゲーム及びボードゲーム)やアニメ、音楽(楽器も含む)[注1]、美的な感動をもたらす工芸品や美術品などがそれに該当する[注2]。通常、そのような気持ちの良さや楽しさ、美しさなどの「快楽」は極めて個人的で主観的なものであるため、他人を観察せずとも、自分の感性を頼りに押し通すことができる(むしろ、個人の嗜好性や強烈な思い、主観などが活動の基盤となる)。その意味では、そのような製品やサービスはデザイン思考よりも、アート思考向きと言えるかもしれない。
また、ファンタジー、フィーリング、ファンの追求は、デザイン思考が得意とする有益性や有用性の追究とは一線を画す場合が多い[注3]。しばしば混同されるが、楽しい経験やワクワクする経験などは、使いやすさや使い勝手とは基本的に性格が異なる(使いやすさや使い勝手は、有益性や有用性と結びつく)。使いやすいデザインが使って楽しいデザインとは限らないからである。著名な認知心理学者のドナルド・ノーマン(Norman, D.A.)氏は、前者のような使いやすいデザインのことを「行動的デザイン」と呼び、後者のように使って楽しいデザインのことを「内省的デザイン」と呼んで、両者を異なるものとして捉えている(Norman,2004)。
ただし、本編⑨のところで見るように、デザイン思考は代替案の探索から始まる通常の問題解決活動ではなく、問題の理解から始まる特殊な問題解決活動である。そのため、時には新しい意味が形成されることもあり、そのような場合には、(確率はそれほど高くないかもしれないが)消費者の感情経験を革新するような製品やサービスが生まれるかもしれない。例えば、アレッシイの沸騰時に小鳥がさえずる「バードケトル」や、コルクを抜く際にダンスを踊るワインオープナーの「アンナG」のような製品である。それらはいずれも、意味のイノベーションの一例であるとともに、消費者の感性に訴えかける製品でもある(Verganti,2006・2009)。
2.「0→1」も苦手?
さらに、デザイン思考は、「1→100」は得意でも「0→1」は苦手と言わることがよくある。なお、ここでいう「0→1」や「1→100」などの表現の主体は価値である。したがって、「0→1」とは、これまで全く価値がなかったもの(無価値であったもの)を有価値に転換することであり、難易度はかなり高い。これは人文学の世界でいえば、思想家の柳宗悦氏による「民藝」の発見と普及(柳,2006)や、芸術家の岡本太郎氏による「縄文」の再発見と普及(春原,2009)、イラストレーターのみうらじゅん氏による「ゆるキャラ」の発見と普及(みうら,2018)などに相当する。要するに、これまで見向きもされなかったものや、忘れ去られていたものへの価値づけを行うことが「0→1」なのである。
本編⑤のところで見たように、デザイン思考も他人の観察を通じて、私の知らない私に気づこうとする試みであるため、原理的には、そのような隠された価値に気づくことは可能である。しかし、残念なことに、実証的な事実が欠落している。このようにデザイン思考が「0→1」型のイノベーションを起こせないとされる背景には、実践の際の観察範囲の狭さがあると考えられる(佐々木,2020)。実践的なデザイン思考では、観察を行う範囲が限定されている場合が多い。その理由は、特定の状況下でのユーザーの行為や意味を理解することに主眼が置かれ、ユーザーの日常生活全般を理解することに主眼が置かれていないことや、企業での実践を考えた場合、観察範囲の過度な拡大は効率性を悪化させるからである。その結果、新たな価値の発見に辿り着くことなく、特定製品の改善や革新に留まってしまう。
その一方で、アート思考では、原理的にも実践的にも「0→1」型のイノベーションを起こすことが可能である。まず、アートの世界では、本来重要でないと思っていた周辺的な要素(間)に価値を見出し、それを自ら学び取っていくことが欠かせないとされている(横地,2020)[注4]。また、Soup Stock Tokyoのようなアート思考を活用した成功事例もいくつか散見される。それまで存在しなかったスープ専門店は、創業者である遠山正道氏の「スープには社会的な価値がある」という強い思いから始まった(遠山,2006)。この例に限らず、革新的な事業は、創業者個人の強い嗜好や強烈な思い込みなどが起点となって始まるケースが多い。その意味では、「0→1」型のイノベーションはアート思考向きと言えるかもしれない。
反対に、デザイン思考が得意としている「1→100」型のイノベーションとは、既に有価値であるもの(少なくとも無価値ではないもの)を、さらに高い価値へと引き上げることを指している。より具体的には、脱コモディティ化や脱成熟化などがそれに該当する(その意味では、コモディティ商品の意味を革新して価値を高めようとするデザイン・ドリブン・イノベーションもこちら側に近いといえる)。ビデオカメラ市場を脱成熟化させたシャープの液晶ビューカムの事例がそうであるように(森永,2021)、デザイン思考の成功事例には、価値を飛躍させるための基盤となるものが既に存在している場合が多い。それは狭い範囲の観察でも、実現可能だからである。
[注1]「ゲーム」や「アニメ」、「音楽」と一口にいっても、すべてが画期的なコンテンツであるわけではなく、ヒット商品の続編や焼き直しなども多いため、そのような場合は、デザイン思考でも貢献できる可能性が高い。
また、デザイン思考が苦手とする3Fを、もう少し具体的にいうとすれば、雑貨を扱うオーサムストアやヴィレッジヴァンガードで売られているようなおしゃれ雑貨や(良い意味で)ナンセンスな商品をイメージすればよいのかもしれない。
[注2]実際に、Hirschman and Holbrook(1982)は、従来の消費者行動研究において見落とされていた側面として、美術・工芸品などの役割、製品を享受するうえでの多様な情緒的な側面、楽しさや喜びを提供してくれるプレイの役割などを指摘している。
[注3]ただし、「美」と「使い勝手」は全くの無関係というわけではない。デザインが美しいと認識されたものは、より使いやすいと認知され、実際の使いやすさよりも、より好意的に評価される傾向が見出される。そのような効果は「美的・ユーザビリティ効果」と呼ばれている(Norman,2004)。また、それとは反対に、分かりやすく、使いやすいデザインは、美しいと評価される傾向にあり、それは「ユーザビリティ効果」と呼ばれている(Lidwell, Holden and Butler, 2004)。
[注4]このような思考法については、「無駄づくり」をコンセプトに創作活動を行っている藤原麻里菜さんの以下の動画(約90分)が分かりやすい。視聴をおススメしたい。
●参考文献
Bettman, J. R.(1979), An Information Processing Theory of Consumer
Choice. Addison-Wesley.
春原史寛(2009)「岡本太郎「縄文土器論」の背景とその評価 : 戦後日本の
「美術」と「縄文」をめぐる動向についての一考察」『筑波大学芸術学研
究誌』第25巻、79-102頁。
Hirschman, E. and M.B. Holbrook. (1982), “Hedonic Consumption:
Emerging Concepts, Methods and Propositions.” Journal of Marketing,
Vol.46, Summer, pp.92-101.
Lidwell, W., K. Holden and J. Butler. (2004), Design rule index. Rockport
Publishers. (小竹由香里/株式会社バベル訳『Design rule index: デザイン
新・100の法則』BNN新社、2004)
みうらじゅん(2018)『「ない仕事」の作り方』文春文庫。
森永泰史(2021)『デザイン、アート、イノベーション』同文舘出版。
Norman, A. D. (2004), Emotional Design: Why we love (or hate) everyday
things, Basic Books. (岡本明・安村通晃・伊賀聡一郎・上野晶子訳『エモ
ーショナル・デザイン』新曜社、2004)
佐々木康裕(2020)『感性思考』ソフトバンク・クリエイティブ。
Simon, H. (1978),The Science of The Artificial 3/e, MIT Press. (稲葉元吉・吉
原英樹訳『新版 システムの科学』パーソナル・メディア、1987)。
遠山正道(2006)『スープで、行きます:商社マンがSoup Stock Tokyoを作
る』新潮社。
Verganti, R. (2006), “Innovating through Design.” Harvard Business Review,
Vol.84, No.12, December, pp.114-122.
Verganti, R. (2009), Design-Driven Innovation: Changing the Rules of
Competition by Radically Innovation What Things Mean. Harvard Business
School Press. (佐藤典司・岩谷昌樹・八重樫文・立命館大学経営学部 DML
訳『デザイン・ドリブン・イノベーション』同友館、2012).
柳宗悦(2006)『民藝とは何か』講談社学術文庫。
横地早和子(2020)『創造するエキスパートたち:アーティストと創作ビジ
ョン』共立出版。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
