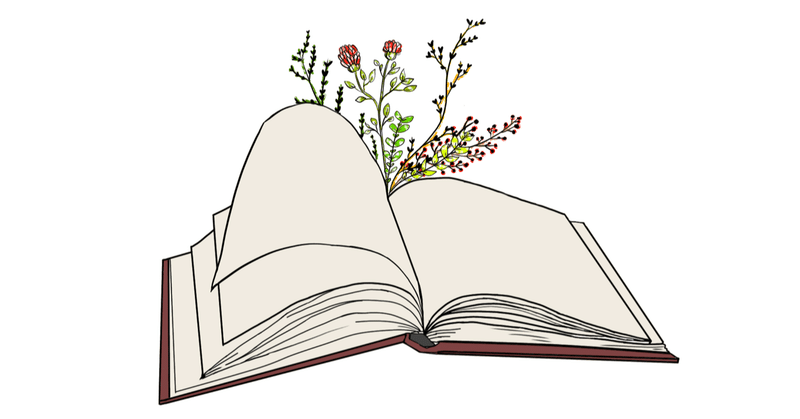
"書を読む"ということ
最近は本ばかり読んでいる。今年に入って読んだ冊数は6冊で、これは"自称"読書愛好家の自分にしてはかなりハイペースである。読んでいる本の大半が小説で、稀に俳句や短歌などがある。どうしてこうも書を読んでいるのか。読みたくなるのか。
そもそも本を読むようになったのは大学生になってからである。それ以前の人生では、読書感想文や朝読書といった強制の場面で仕方なく読むことはあっても、自ら興味を持って読書をする時間は一切なかった。厳密に言えば、"興味がない"で済ますことができないくらい読書という行為を嫌っていた。国語の問題の常套句である「主人公の気持ちを○字以内で書け。」という問題に対して、「いや、そんなのそいつにしか分かんねぇだろ!!」と屁理屈を働かせていたタイプの人間であった。
そんな自分が読書をするようになったのは、高校2年生の現代文の授業である1つの物語に出会ったことがきっかけだった。その物語は安部公房の『鞄』という物語。内容には深く触れないが (『笑う月』という作品に収録されています。短くて読みやすいので是非読んでみてください。)、この物語を読んだ時の衝撃は今でも鮮明に覚えている。今まで読書に対して抱いていた"難しい"、"堅苦しい"というイメージがいとも簡単に払拭された。良い意味で文学作品らしさがなく、とても読みやすい上、何か深く考えさせられるような内容にドップリとハマってしまった。それ以来、読書というものに興味を持つようになった。
大学受験を乗り越えてから、安部公房の他の作品『砂の女』『壁』に手をつけた。『壁』は難し過ぎて訳が分からなかったけど、『砂の女』に関しては確かに"面白い"という感覚を抱いた。それから安部公房だけでなく、色んな作家の本を読むようになったのである。
ここまでは読書をするようになったきっかけを書いてきたが、では何故、その頃から引き続き、飽きずに(正確にいえば飽きる時もあるが、)読書をしているのか?
自分が"書を読む"ということに抱く考え方は大きく3つある。そのうちの2つは好きな理由につながっており、残りの1つは少し違った観点からのものである。
まず1つは、「自分とは違った人物の視点が手に入る」ということである。
この違った人物とは、物語の中の登場人物でもあり、その物語を書いた作家でもある。要は、その物語の中の登場人物の考え方や行動から新しい視点を手に入れることもできるし、その物語を書いた作家がどういう経緯で創作したのかに対する考察から新しい視点を手に入れることもできる。
前者であれば、登場人物と現実の自分が重なった場合は自分の行動を見直すヒントになりうるし、重ならなかった場合は自分の新たな行動への道標となりうる。後者であれば、作家の考え方をあれこれと妄想するだけでも楽しい。「自分だったら結末をこうするけど、この作家はそう締めるのか...」と素人ながらに考えてみると、その作家の空想や創作の中における考え方や信念を何となく知れたような気がして面白いものだ。現実と空想は隔たれているが、最低限のマナーや常識を兼ね備えた上で、その隔たりを無視して生きる方が楽しいと思う。物語の中の人物やそれを創作した作家から、楽しく、寂しく、美しく自分が現実を生きていくためのヒントを得ることができるというところに読書の魅力があると考えている。
2つ目は、「言葉を知れる」ということである。
先ほど述べたように、元々は文を読むことが嫌いだったが、言葉を知るのは大好きだった。偉人の名言や好きなアーティストの歌詞には何回も感動させられたし、そういったものに出会えた瞬間も大好きだった。安部公房の『砂の女』を読んだ時、素人ながら"表現の豊さ"に感銘したのもそういう言葉に対する敏感さが備わっていたからなのかもしれない。美しい言葉とは何か?綺麗な表現とは何か?そういうものを探求するのに読書はもってこいなのだ。それこそ、自分が俳句や短歌に興味を持ち始めたのもこの点がルーツにある。自分にとって美しいと思える文章、表現、言葉に会えた時の気持ち良さは堪らないものである。この点に関しては、なかなか共感されることはないが、今度自分が今まで出会ってきた好きな言葉を羅列するだけのブログを書きたいと思う。
3つ目は、上に挙げたものと少し異なる考え方だが、「読書は孤独が表出される活動だ」ということである。
1人で授業を受ける人、1人でご飯を食べる人、1人でランニングする人。そういう人たちには見えない孤独感が読書をする姿に見られる。その孤独感の正体は分からないが、ギターやピアノで弾き語りをする姿にも似たような要素を感じることから自分が芸術に対して抱いているイメージと関連しているのかもしれない。自分は読書が好きな人をとても魅力的に思うが、それは、同じ趣味を共有できるからではなく、孤独を表出しているその姿に親近感と憧れを持っているからである。以前このブログでも書いたように孤独感を抱いている人はとても魅力的に見えるという謎の性癖が自分にはあるのだ(詳しくはこちら→『弱さの魅力』)。この読書の孤独感によって、本を読んでいる人に魅了されることもあれば、読書している自分に嫌悪感がさすこともある。本を読みたいと思って読んでいる自分と、その自分から孤独感が表出されていることに気付いて読書を今すぐにでも辞めたくなる自分が葛藤する時がある。その葛藤の時間は虚しく気持ち良いものではないが、客観的にみるとなかなか面白い。
以上、"書を読む"という行為に対して自分が思っていることを記してみた。相変わらず、書いている自分ですら何を言っているのかよく分からないという部分もあったが、こんなことを長ったらしくオープンにしても如何本仕様もないので、またいつか、今度は気軽に「オススメの本紹介!」などをできたら良いのかなと思う。
Twitter:檸(@nei_monologue)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
