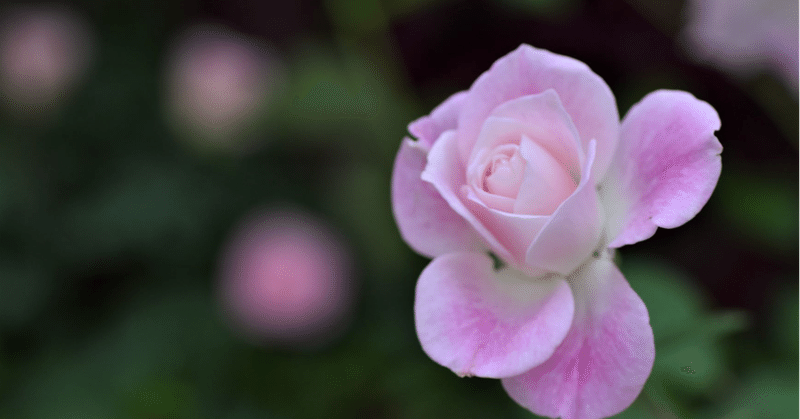
大人の恋愛小説・マダムたちの街Ⅱ-3
その3 終わりと始まり(最終章)
駅から五分の立地のいい谷さんのマンションは築三十五年らしく、かなり古ぼけていた。
五階の東向きで日当たりはかなりいい。ベランダに出るとその下には線路が数十本、束のようになって北へ伸びているのが見える。車両がひっきりなしに通過する。上から見ると、線路というものは無骨で荒々しいものだなと思った。
ベランダには小さな鉢植えがひしめき合い、花や実をつけていた。谷さんにはこういう趣味もあるのだ。
窓を開けて膝附椅子を二つ窓際に運び、僕はその片方に腰掛ける。小さな丸いテーブルを置いて、そこへ谷さんが台所からカレーを運んできた。
思ったより辛くてパンチのあるカレーに僕は水を何度も飲んだ。
僕を見て谷さんは「あら、辛すぎた?」と微笑んだ。
「カレーパーティって、いつも何人くらい集まるんですか?」
涙が出て来たのを悟られまいとどうでもいいことを尋ねる。
「そうね、今日は六人かしら」
「そうなんですか」
何度も心に浮かんでは消えしていた疑問を口にしてみる。
「ところで、谷さんは僕と一緒になったら、家事を全部こなしてくれるんですか?」
「あら、具体的に来たわね」
少し考えて、「どうして欲しい?」とこちらの表情を伺う素振りを見せた。
「そりゃあ…、僕が仕事するんなら、すべてやって欲しいですね」
フフン、鼻で笑うと谷さんは
「そりゃそうよね。でも、このご時世、あなたも出来ることはやった方がいいんじゃない?」と返す。
まぁ、そうですが、と僕は視線を窓の外へ向けた。
鉄道がこんなに間近なら、頻繁に行き交う列車を僕なら一日中見ていたい気になる。つい目を奪われる。
もしかすると、このマンションは谷さんのパートナーかその子供が好んだ風景だったのではないか。そんなことを考えた。
でも、それが何だと言うのだ。
「正直に言います。僕はあなたと、もう一人の養子と一緒に生活する想像が、止まらんのですよ」
「あらまぁ」
谷さんは声を張り上げた。
「それって、嬉しいってこと?」
「そうでしょう」
谷さんは僕の右肩をポンと叩いて、
「あなたのそういう正直なところ、好きよ!」と楽しそうに言った。
「実はね、養子縁組について調べたら思いがけない事が分かったのだけど」
谷さんが神妙に切り出した。
「特別養子縁組って、実の親の戸籍から子供を抜いて次の親と新しい親子関係を作る制度なんですよ、ご存じの通り」
「ええ」
「子供は6歳未満と言う決まりがあるの。小さい内に親子関係をキチンと築くためだわね。そして、親と子の年齢差が45歳以下でないといけないの」
「つまり、僕との差は大丈夫だけど、谷さんとの差が…」
「完全にアウトだわね」
僕はシュンとした。…そうだったのか。一辺に夢は吹き飛んだ。
「まぁ、でも普通養子縁組なら、その条件はないんだけどね」
しかし普通養子縁組なら片親でもなれるのだ。なら別に僕と結婚しなくてもいいのではないか。
そう考えると今までの話がご破算になる。
「私はあなたとやって行きたいのよ。あなたがお父さんならいいなと思って」
それはどうも、と一応頭を下げる。普通と特別の差は根本的に何なんだろう。
目まぐるしく頭を回転させる。
「あなたはどう思うの?」
谷さんはいつも僕にボールを投げて来る。
そう言われても、すぐに答えは出ない。
「よく考えてみますよ。幾らでも時間はあるし」
「頼むわね」
窓の下の線路に長い長い貨物列車がゆっくり通り過ぎていくのをぼんやり僕は見つめていた。
その日から度々僕と谷さんは会い、これからの人生設計を話し合った。
一応、普通養子縁組でいいという結論になった。
更に、住まいはどこにするか、僕の仕事をどうするか、お互い家事をどれだけ分担するか、どういう子供を迎え、どのように育てて行くのか。必要経費は。麻生さんは確実に資金を出してくれるのか、など、話題は限りなくあった。
時には脱線して冗談か絵空事になってしまいそうになる。だが踏みとどまって極力現実的に話し合おうとした。
未来を想像し、設計するのがこんなに楽しく心躍るものとは僕は考えた事もなかった。
しかし肝心の本心を僕はいつまでも打ち明けなかった。
このような重大な話をしながら、本当に彼女と結婚したいのかを明らかにしなかった。
やはり突き詰めれば僕の中に抵抗があった。
それは動かしがたい事実と言っていいだろう。
突然、典子さんに会いたくなった。
別れて半年近く経つ。今なら一度くらい会っても許されるだろうという甘えがあった。
口実を探してみる。家の中に彼女が残して行った持ち物が何個かあった。タオルケットと本、靴下。そんなところである。
それらを詰め込んだ紙袋を持って典子さんのマンションへ向かった。
ラインも解消したので、とにかく行ってみるしかない。平日の夜、多分7時半には部屋にいるだろう。
彼女のマンションまでの道のりは、懐かしくちょっと切ない思いがした。
部屋の前に立つと、急に躊躇いが大きくなった。が、思い切ってチャイムを押す。
中から聞こえてきたのは男の声だった。
「典子さんは仕事からまだ帰っていません」
と言う。
僕は、典子さんの友人で、預かっていた物を届けに来ましたと告げた。
玄関が開いて、一人の男性が出て来た。
「ご苦労様でした。預かります」と言って、無表情で僕が持っていた紙袋を引き取った。若い男だ。よく見ると、それはいつか典子さんの会社の玄関先で出会った彼女の部下だった。
一瞬で合点が行った。
そういうことなのか。
「ありがとうございました」と男は言って、僕の鼻先でドアが閉まった。
何故か頭の中がカーッとした。
その後じわじわと屈辱的な思いが湧いてきた。あたかも床上浸水のように。
「まぁな。でも仕方ないさ」
帰り道、歩きながら僕は呟いた。
ふーっと久しぶりに深く長い溜息が出る。
もう半年だもんなぁ、と彼女と会っていない日を振り返った。
空を見上げる。無数の星がキラキラチカチカと瞬いている。
ところで自分はなぜ彼女に会いたいなんて思ったんだ?という疑念が渦を巻いてわき上がってきたが、僕は押しとどめた。
きっと明日は素晴らしい天気に違いない。
僕はそう思いこもうとした。
ついに僕は決断した。
谷さんの話を受け入れる、つまり結婚を承諾しようと決めたのだ。
ラインに明日大事な話があると書き、午後一時頃そちらに伺いますと記し、僕は準備をした。
翌日、お日柄も良く空は五月晴れ、気持ちの良い風が空を駆け巡っていた。
花屋で赤とピンクの薔薇にかすみ草の花束を作って貰い、谷さんの指に合う指輪も用意した。彼女の部屋へ入ってすぐに言う台詞も練習した。
新調したジャケットにワイシャツ、細身のチノパンツ。
用意は万端だ。
谷さんの部屋のチャイムを押し、玄関を開けると谷さんが出て来た。
僕はリビングまで行き、用意したセリフを言おうとタイミングを見計らった。
しかし谷さんは僕を見ず、何かチョコマカと動き回っている。旅行用バッグに衣類を詰め込んでいる。視線が彷徨っているのを見て「え?」と様子を見る。
彼女はどうも頭が一杯で僕の存在には関心がない様子だ。
「何かあったんですか?」と僕が問うと、寄ってきて
「ごめんね、さっき電話があって麻生さんが倒れたらしいのよ」
と言う。
「心筋梗塞らしいの。取りあえず病院に運ばれたみたいだから、行ってみるわ」
「ハァ…、僕も行きましょうか?」
「いえ、あなたはいいわ。私だけで行ってみる」
バタバタとスリッパを鳴らし、バッグを整え、カーテンを引き始めた。
「ここに帰って来ないつもりですか?」
「ええ。色々と入院の準備や身の回りのことがあるでしょうから、あの人の部屋へ泊まってくるわ。私くらいしかそういう役が出来ないはずだし」
僕は途端に心細くなった。
「谷さん付き添いするんですか」
「十中八九そうなるわね」
「僕も大事な話があったのに…」
谷さんはやっと表情が和らいで、
「また今度ね」
と僕を見た。
「力になれることがあったら言って下さい」
「そうするわ」
膨らんだバッグを谷さんは持って、二人で部屋を出る。
マンション前に着いたタクシーに慌ただしく乗り込んで谷さんが行ってしまった。
一人残された僕は花束と指輪の箱が入った紙袋を提げて立ち尽くした。
その後谷さんから聞いた話に寄ると、麻生さんは急性心筋梗塞の危機は脱したらしいが検査とリハビリで入院は3週間続くそうだ。何日か谷さんが付き添いに行ったが、麻生グループの面々が駆けつけて、交代で付き添いや身の回りの雑用をすると言う。しかし谷さんはほぼ毎日病院へ行くので、暫く僕とは会えないと言うのだった。
谷さんの気持ちが一気に麻生さんになだれ込んだのを僕は感じ取っていた。
僕との将来は一旦棚上げになったと言える。
谷さんと麻生さんがどんな関係か知る由もない。改まって聞く気もしない。麻生さんがすっかり良くなって退院するまで、僕は黙って待ち続けようと思った。
こういうところが自分の弱い所である。悉く寛容だ。
いつまでも待てる。別に急いでいない。人間関係について問い詰めることもしない。
しかし、こういうのは人としてどうなのか。自分に甘い男は他人にも甘くなる。そもそも世の中に対する見方が甘いのだ。
この時僕は安心しきっていた。自分の気持ちは固いのだから、うろたえる必要はまるでないと、安心していたのである。
ところがそんな独りよがりは通用しない。
一ヶ月で退院した麻生さんは、その後リハビリ通院をしなければならなかったもののひとまず以前の生活に戻った。ところが退院して十日も経たずに、麻生さんは容態が急変して亡くなってしまったのである。
谷さんの話だと、亡くなった後に親戚が押し寄せ、葬儀はすべて彼らが執り行ったと言う。
友人らは一掃された。見舞いにも来なかった親戚縁者が、である。
谷さんは参列したが、僕は葬儀には出なかった。
麻生さんが亡くなってから、谷さんの落ち込みは酷かった。
ある日僕がマンションを訪ねると、谷さんは抜け殻のようになって部屋にいた。
以前の彼女とは別人のようなやつれ方だった。
部屋はどことなく汚れ、埃が舞っていた。
窓を開け放して風を入れる。部屋に溜まった埃がハラハラと逃げ出していくのが分かる。椅子にぐったりと腰掛ける谷さんに僕は恐る恐る声をかけた。
「大丈夫ですか?」
「まぁね。大丈夫かと聞かれれば、そうではない気もするけど」
僕はしずしずと紙袋の中から指輪の箱を取りだした。花束は、もう買う気にならなかった。
「これ、谷さんへ僕からです」
差し出した指輪の箱を物憂げに見ると、谷さんは言った。
「その話だけど…、こちらから言い出したことで悪いんだけど、忘れて貰えないかしら?」
「え?」
僕は理由を尋ねた。
谷さんは説明を始めた。あの計画は飽くまで麻生さんあっての計画だった。つまり、スポンサーありきの話だったのだ。
「私たちは資金を麻生さんから提供して貰う約束だった。税理士と弁護士に頼んで、キチンと資金を移して貰える筈だった。でも、それをする前に麻生さんは逝ってしまった。もうどうすることも出来ない。すべて後の祭り」
僕は絶句した。資金の移動については一度そんな話を聞いた気がする。でも軽く考えていた。真剣に向き合うまでは行かなかった。
僕は終始結婚後の楽しそうな生活に心を奪われていたのである。
何と愚かな人間だろう。
「親戚の人たちが思った以上にやって来て、誰が誰やら分からなかった。まして資産のことなんか聞き出せるはずがなかった。今となっては私との話はすべて口約束だったと言えるだろうね」
言い訳のような弱々しい言葉に僕は耳を疑った。
僕は肩を落とした。
「あなたお腹すいてるでしょ?カレーでも食べてく?」
ハイ…、と生返事をする。谷さんはエプロンをきりりとつけてもう台所に立っている。
やがてカレーが運ばれてきた。谷さんは僕にノンアルコールのビールを注いでくれた。
カレーを何口か食べると口の中が痺れるように熱くなった。
「辛い!…何ですか?このカレーは」
谷さんは自分の分も皿によそって運んでくる。
「市販のルーの混ぜ合わせだわよ。大辛とか中辛の」
「僕は子供舌なのかなぁ。甘いのがやっぱりいいなぁ」
次第に現実が心に迫ってきた。
二人で窓の外を眺める。
「私ね、来月末までにここを出るから」
ふいに谷さんが言う。
「来月末…、急ですね」
「何だかこの町にいたくなくなってね。この町にいるだけで麻生さんや皆のことを思い出すのがつらいのよ」
そうだろうな、と思った。
「あ、あなたもね。‥あなたのことが、一番つらい」
急に涙が湧いてきた。僕は目尻を拭った。
頭の中に谷さんとの生活、養子との生活がめくるめくように浮かんでは消えて行った。
「‥君は、‥いい子だね」
谷さんが僕の肩をポンポンと叩く。
「ごめんね。せっかくその気になってくれたのに」
僕は言葉にならず、打ちひしがれていた。
日が落ち、部屋は次第に薄闇に包まれた。
僕は目頭を押さえながらいつ席を立とうかと考えていた。
六月。
連休が終わり、街の喧騒は収まった。新緑がまぶしい。
一人になった僕は新しい仕事を始めた。マンション管理の仕事である。
一週間に四日、午前八時から午後五時まで色々な人と話をしたり、設備の業者さんに立ち会ったり、共用部分の掃除をする。一日があっという間に終わる。仕事を始めてから、余計なことを考えなくなった。夜も熟睡できるようになった。
そう言えば柏木が、たまに気になる話をする。
例えば、いつぞやの谷さんと麻生さん、典子さんの三人の旅行はあらかじめ企てられていたものだとか。
谷さんと麻生さんは典子さんが僕と別れるように強力に説得したのだと言う。
また谷さんは、僕がコンビニで働いていたころ、数年前から僕に目を付けていたのだという。この情報は典子さんから柏木が聞いたものらしい。
しかしそんな事はどうでもいい。
何故なら彼女たちはもう自分の前からいなくなったのだから。
笑って関心を示さなくなった僕に、柏木は対戦を挑んできた。
百メートル走である。
何故か知らないが、柏木は僕の運動神経に対して猛烈な嫉妬心を抱いていた。
僕は高校の時に百メートル走でインターハイ8位の成績を残している。
それを聞いた柏木の顔色が変わった。自分は大会に出場できなかったが陸上の選手だった、それぐらいは行けると言う。すごい自信だ。
ということで、陸上競技場で、百メートル走の対決をすることにした。
約束のその日、現れた柏木は短パンにランニングシューズという本格派だ。こっちは高校時代に着ていたジャージーにすり減ったスニーカー。さすがに恥ずかしかった。
タイムキーパーも頼んで、笛でスタートを切る。
一足一足がままならず地面が固くて足がもつれる。たが、僅かな差で僕が勝った。タイムは13秒40だ。
柏木は14秒。まずまずではないか。
柏木は悔しがって二戦目を挑んできた。すると、なんと今度は逆転され柏木が13秒75で僕が14秒10となった。
何度も続けて計7本走った。3対4で僕の勝利だ。
柏木は次は1キロ走をやろうぜと競技場を去った。
いいじゃないか。それまでに、無くなった筋肉を復活させてやる。
家へ帰ってきた僕は部屋の真ん中に立って家の中を見回した。
何かが変わっていた。そう、自分自身だ。
自分の体の中がやけに熱く感じたのだ。
人気のない寂しいこの家が灰色だとしたら、自分の心はくすぶる赤だ。何人かの人によって揺さぶられ、それまで眠っていたものが発火した。
ブスブス燃える火種となって胸の中に住み始めた。
消すに消せない火。ハートに火がついた、というやつだ。
僕はここから何かを始めるだろう。幾つか案があるが、僕はその中から一番むずかしいものを選ぶだろう。いや、難しいものではない。一番出来そうなものだ。
足下が固まったら、その先には幻のようなあの楽しい未来が待ち受けているかも知れない。
想像すると期待に胸が高まった。
僕は確かに体の奥からムクムクと得体のしれない力が湧いてくるのを感じていた。 (了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
