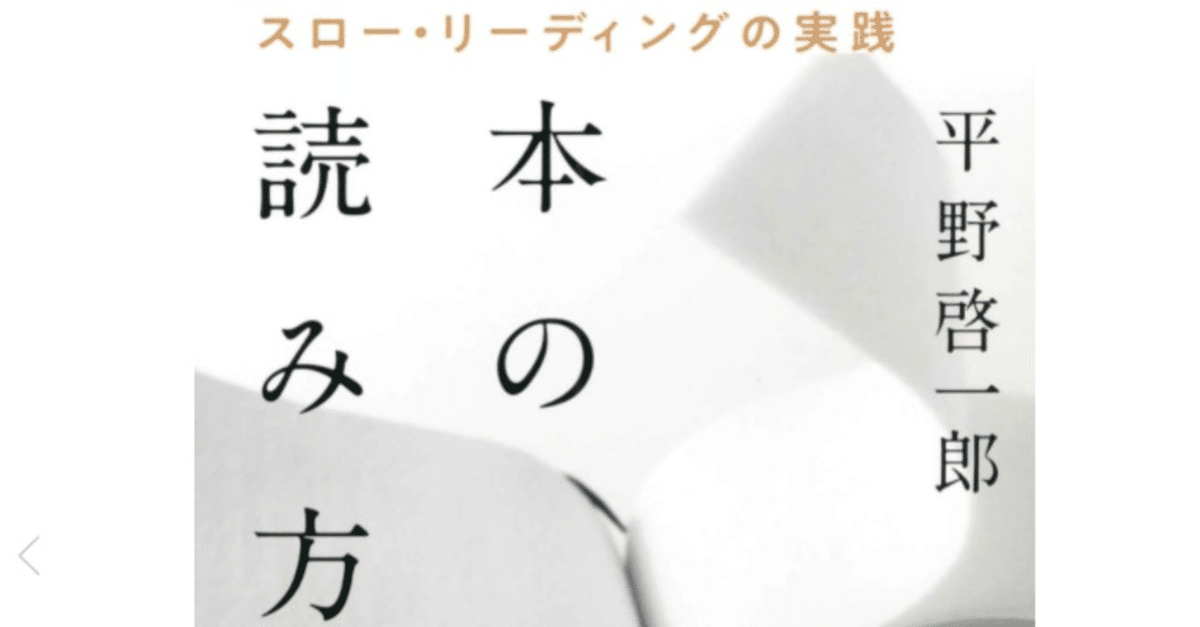
本の読み方 スロー・リーディングの実践/平野 啓一郎 (著):読み方によっては文章を書く人のための解説書
決して多読・速読が悪いと言っているわけではないが、それはデータ収集のための読み方で実用書やハウツー本向けである。
ショーペンハウアーの「読書について」と論旨が近い。
小説は作者が仕掛けた仕掛けやノイズに気がつけば、筋を追うだけの読み方で得られないものを得ることができる。
要旨を簡単にまとめると、そんな感じである。
本を流し読みする人であれば「ふーん、そんなところまで気がつかないよ」と思うかもしれないが、小説や物語を書いたことのある人は「ストーリーには必要ないけど、ここにその一言を入れた方がその後の雰囲気が変わるよね」等々、執筆中のことを思い出し、納得するところも多いのではないかと思う。
全体構成
第一部「量から質への転換を:スロー・リーディング 基礎編」
・スロー・リーディングとは何か?
・「量」の読書から「質」の読書へ
・仕事・試験・面接にも役立つ
・速読家の知識は単なる脂肪である
・コミュニケーションとしての読書
・速読本は、「自己啓発本」だった
(略)
第二部「魅力的な誤読のすすめ:スロー・リーディング テクニック編」
・「理解率70%」の罠
・助詞、助動詞に注意する
・「辞書癖」をつける
・作者の意図は必ずある
・創造的な誤読
・「なぜ」という疑問を持つ
(略)
第三部「古今のテクストを読む:スロー・リーディング 実践編」
・夏目漱石『こころ』
・森鴎外『高瀬舟』
・カフカ『橋』
・三島由紀夫『金閣寺』
・川端康成『伊豆の踊子』
・金原ひとみ『蛇にピアス』
(略)
感想
『一冊の本を、価値あるものにするかどうかは、読み方次第である』
この文の説明に海外出張を例に出して説明しており、腑に落ちる。
出張で訪れた街を空き時間のほんの1~2時間でざっと見て回るのと、一週間滞在して、地図を片手に丹念に歩き回るのとでは、同じ場所に行ったといっても、その理解の深さや印象の強さ、得られた知識の量には、大きな違いがあるだろう。旅行は、行ったという事実に意味があるのではない(良くそれを自慢する人もいるが)。行って、どれくらいその土地の魅力を堪能できたかに意味がある。
最近、個人的に中国ブームの知り合いがおり、流行病が終わったら観光に行く気満々なご様子。行きたいところの話をすると、私が「(出張で)行ったことがある」「うん、そこも」というと、その都市にある有名な場所のことを聞かれる。でも、どこも知らない😅
流行病で有名になった武漢市は数泊したことがあるが武漢東湖(中国国家5つA観光スポット)には行っていない。長沙市には都合10日ほどいたが、有名な観光地(があるらしい)へ行っていない。
上海は多いときには、2か月に一度訪れているが、上海のいろいろなところを知っているかというと、たぶん知らない。
いずれも「仕事で行き、用事を済ませる」が主目的なので「地図を見て知っている(今時ならGoogle Street Viewをで見たことがある)」と大差がない。
その土地柄をあまり理解していないと思う。
小説を書かれる方に
第三部では著者から見た、有名な小説家が書いた文章の注目点が書かれている。それぞれの作家が、文章を綴る時どれほど注意を払っているのかを。
素人の物書きが読むと、レベルは違うが参考になる。
この本で一貫しているのは、小説家 平野 啓一郎氏からみた本の読み方であり、小説を書かれている方、これから書こうと思っている方には「参考になるアドバイス」として読めば、それなりに得るものがあるのではないか。
第二部のテクニック編で「小説家は文章を書く時、このようなところに気配りをしている」という点は、自分が書く立場になれば、同じ気配りをしても良いところではないかと考える。
平野啓一郎氏について
彼の本を紹介するのは2回目。
まだ、長編小説は読んでいない。
いずれ読むと思うが、その小説のレビューを書くのは難しいなと思っている。
著者にはnoteのアカウントがある。
Twitterでも発信中。
https://twitter.com/hiranok
与党の施策等に厳しく意見を発せられており、文学界の中では珍しいのではないかと。納得できる意見も多くフォローしている。
10年ほど前のTEDでは、こんな方。
MOH
