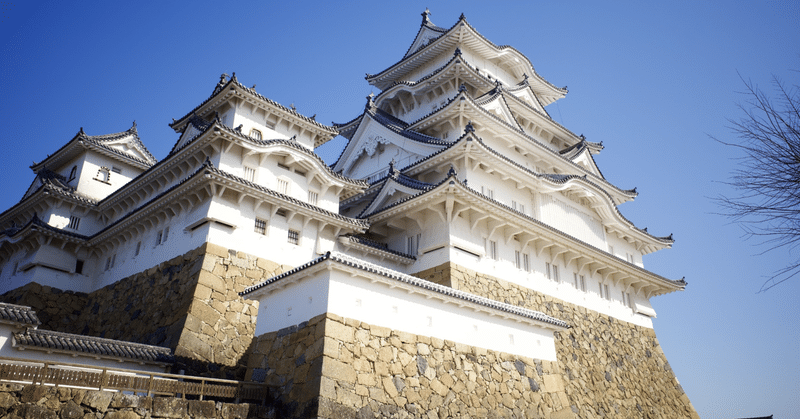
鎖国と高度経済成長と
◉玉木俊明京都産業大学経済学部教授による、江戸時代初期に実行された鎖国によって、耐久消費財を人々が購入することで経済成長が起きた、高度経済成長はそれに似ているという論考ですが。自分は経済は素人ですが、歴史は多少かじってる程度の知識はあるので、ちょっと疑問に思う部分を、いくつか書いてみたいと思います。
【江戸時代の「鎖国」が導いた日本の高度経済成長】東洋経済オンライン
戦後日本は、なぜ高度経済成長を実現できたのか。手数料と物流という枠組みから世界史を捉えなおし、覇権国家の成立条件について論じた『手数料と物流の経済全史』を上梓した経済史研究者の玉木俊明氏が解き明かす。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、姫路城の写真です。時代劇では、江戸城の代わりに表示されるので、江戸っぽいので。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■経済を敵視する宗教■
詳しくは、上記リンク先をお読みいただくして。個人的には、社会学者マックス・ヴェーバーとヴェルナー・ゾンバルトの、どっちが正しいという二者択一ではなく。ゾンバルトが言うように、人間は欲望を開放する生き物ですが、どうも単純な欲望の開放には、どこかブレーキが掛かる生き物という側面もあります。真っ赤な果物があるから美味そうだで食っちゃう人間がいるから、人間は毒がある果物とない果物の、知識を得ることができた部分があります。同時に、これは食べたらヤバそうというブレーキがかからないと、群れは毒の果実をホイホイ食って、全滅してしまいます。
さて、ここで聖書の話を。永遠の生命を得るためには、どんな良いことをしたら良いかと質問した青年にイエスは、殺すな・姦淫するな・盗むな・偽証を立てるな・父と母とを敬えという戒めを守り、自分を愛するように隣人を愛せよと説きます。青年がそれをすべて実行したと報告すると、「あなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい」と答えます。青年は立ち去り、イエスは弟子に「よく聞きなさい。富んでいる者が天国にはいるのは、むずかしいものである。また、あなたがたに言うが、富んでいる者が神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通る方が、もっとやさしい」と語ります。
宗教の多くは、経済活動を嫌悪します。商売というのは才覚によって、結果が大きく変わります。人間が農業をコツコツやって1年で得られる収入の、何倍も何十倍も儲かることありますから。そうすると、商才なき人間は、人が作った作物や工芸品を右から左に移動させてるだけで、莫大な収入を得る(ように見える)商人への、ルサンチマンを溜め込みます。聖書の律法を守り隣人を愛しても、金持ちというだけで天国に入れない。それほど金持ちの罪は大きい。持ってるだけで罪。これがルサンチマンの原型。
■資本主義と禁欲主義■
故に、プロテスタントの禁欲主義が資本主義を生んだというヴェーバーの説は、逆説なんですよね。玉木教授の解説は、両者の主張を単純化しすぎに思えます。富や貨幣経済を否定する宗教にあって、禁欲的に働いた結果稼いだ金は問題ないという〝抜け道〟を、プロテスタントの作ったんですね。そのトレードとして、勤勉を尊ぶ禁欲主義がセットで、プロテスタントには育まれた面が。
人間は、自分に絶対な正義があると思い込んだ時、他者に対してこの上もなく残酷になれます。十字軍の蛮行やルワンダ虐殺はもちろん、ポル・ポトによるカンボジアでの知識階級や富裕層への虐殺が起きた理由も、これです。禁欲的で勤勉なプロテスタンティズムも同様に、信者に正義を与えました。プロテスタントの牧師は、お金を稼いでも、神はその勤勉を褒めこそすれ、罰しないよと説いたんですね。
教科書では、カトリックの腐敗への怒りとか、活版印刷技術の発明によって聖書が安価に、大衆でも手に入れられるようになって聖書中心主義に回帰したとか、いろいろ解説されていますが。宗教改革の本質は、これです。これによって、プロテスタントは真面目に働き、自然に蓄財し、身分の低い庶民階層の人間でさえ、ある程度の貨幣経済での蓄積が生まれます。これが大衆消費社会の出現を選んだわけです。それが資本主義の正体。
■ヴェーバーの超慧眼■
この、一般大衆に自分で動かせる資産ができたことが、資本主義社会を生んだと言うのが、ヴェーバーの考えのコアの部分です。この逆説を、玉木教授は了解しているように思います。ヴェーバーもゾンバルトも、人間の欲望が経済を発展させたという点は同じなのです。ただ、ヴェーバーは禁欲的で勤勉なプロテスタンティズムが資本主義を生んだという逆説を発見したという点において、深いのです。
日本でも、江戸時代の初期までは呉服屋などは、大名や高位の武士や豪商などの富裕層に、お得意周りをし、商売をしていました。ところが都市部が発展し、庶民が経済力を持ってくると、大衆を相手にした三井高利の越後屋のような商売が成立したわけです。三井は店舗に客が来て、反物だけではなく小さな端切れまで売ってくれる。Amazonがボールペン一本から宅配してくれるのと実は似ています。
伝説の豪商紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門は、幕府の公共事業を請け負う、いわば政商です。ところが武士階級が没落し、庶民階級が金銭という力を持つようになると、大衆をターゲットにした商売が成立する。テレビ局が放送権を独占していた頃は、YouTuberなんて商売が成立しなかったわけで。雑なまとめではありますが、マックス・ヴェーバーの言っていることはこれに近いわけです。ユダヤ・キリスト教のルサンチマンに興味がある人は、以下のnoteも参照してください。
■朝鮮特需はあった?■
記事の中で気になったのはもう一つ。敗戦で焼け野原になった日本国の復興は、朝鮮戦争勃発に伴う朝鮮特需によるものであると、説明してある点ですね。この朝鮮特需説も、現在では否定的な意見も各方面から出ています。『はだしのゲン』史観の影響なのかもしれませんが、戦時中は戦争によって軍需産業が儲かったというのは、現実ではありません。国家総動員体制では、会社利益配当及資金融通令や会社経理統制令で、軍需産業の株主や役員の力は剥奪されていました。戦争で確実に儲かっていたのは、朝日新聞などマスコミです。
日本は、このような状況から立ち直り、高度経済成長を経験したのである。その大きなきっかけとなったのは、1950-53年の朝鮮戦争特需であった。1949年の輸出額が5億1000万ドルであったのが、1956年には25億100万ドルと、約4倍になった。鉱工業生産指数は、同時期に100から316に大きく増加した。
実際問題として、日本の経済が大きく回復したのは朝鮮戦争が終わってからです。1954年からの神武景気が大きかったわけで。ウィキペディア先生にも、朝鮮特需に関する疑義が、割と分量を多めにあります。紀伊国屋文左衛門や奈良屋門左衛門のような、官に頼った経済では、大衆全体へのトリクルダウンは、なかなか起きないのかもしれませんね。だってそれ、一種の開発独裁ですから。そこら辺の庶民でもある程度のお金を持っている、それが実は大事のようです。
この年の対日援助の総額が2億ドルであるから、日本の経済は朝鮮特需で回復するどころか、朝鮮の兵站線を支えるために国内の物資の流通を統制してまで軍需生産に追い込まれたのである。このような状況で輸出が伸びるはずもなく、産業はますます特需に依存の度合いを深め、やがては日本そのものが戦争を前提とした産業構造に「特化」する危険さえあった。
朝鮮特需はむしろ、復興の足を引っ張った、という部分もあります。もちろん、儲かった企業もあったでしょうけれども、日本国全体で見るとマイナスだったわけで。もちろんアメリカの工業製品生産のノウハウや、生産品のクオリティ管理などの先進的な方法論が日本にもたらされ、これがその後の経済成長の礎になったという面が大きかったようで。高度経済成長は1955年頃から1973年頃まで。60年安保で退陣した岸信介内閣が、減税や国民皆保険制度、国民年金制度に着手し、1960年からの池田勇人内閣の、所得倍増計画の基礎を作りました。これが大きかった。
■人間の実感ある金融■
個人的には、大衆の耐久消費財の購入によって、江戸時代の経済が発展したという部分には、賛成なのですが。これって要するに、江戸幕府による長期の安定政権によって、大衆社会が発展し、内需で経済が回るようになった、という面があるわけです。ただ、日本には欧州で生まれたような近代資本主義は生まれませんでした。大阪堂島の米市場では、世界初の先物取引やヘッジ・ファンド的な仕組みまで生まれたにも関わらず。
渋沢栄一が偉かったのは、官による開発独裁的な経済は結果的に行き詰まるので、銀行というシステムを導入し、大衆から金を集めてそれを運用する、構造を導入する必要性を見抜いていたことでしょう。信用によって、国の造幣局が紙幣を刷らなくても、市場に必要なマネーを生み出せる近代資本主義の構造は、荻原重秀裏側か閉会中で市場のマネーの総量を増やした手法を、天才的な人間でなくてもできるようにする、非常に画期的なシステムでした。
インターネットの登場によって、昔だったら銀行や信用金庫だったら絶対に出資してくれなかったようなアイデアに対して、クラウドファンディングで数百万円数千万、億に近い金が集まる時代です。銀行のシステムはシステムとして、個人的にはイスラム金融のような手法はこれから案外、借金が雪だるま式に増えていく近代資本主義の問題を埋める形で、これから面白いポジションを作りそうな気がするのです。金を貸す側もリスクを負うという考え方が、自分にはしっくりきますので。
例えば工場を建てるという場合、まずイスラムの銀行が建築資金を肩代わりして工場を建てます。そして、分割払いのかたちでそれを企業に売り払うのです。銀行にとっては建築資金と売却代金の差額分が利益になります。日本の金融業者でいうと、リース業やクレジットカード業などのしくみに似ています。お金を貸すのではなく、モノの代金を肩代わりするやり方です。ただイスラム金融では、取引がイスラム教の教義に反していないかイスラム法学者に認めてもらう必要もあり、手続きはとても複雑です。
イスラム金融に興味がある方は、こちらの本などをおすすめしておきます。
■内需拡大こそが肝要■
さて、話を本題に戻して。重要なのは、鎖国時代の政策ではなく、内需を高めること。何のことはない、貿易不均衡でアメリカが日本に求めた内需拡大が大事。もちろん、アメリカの利益も重要でしたが。それを渋々実行した結果、日本は平成不況やリーマンショックでも、ナントカ持ちこたえられる状態になったのです。もし80年代に内需拡大政策で手を打っていなければ、アジア通貨危機での韓国のようになっていた可能性もあるでしょう。
共産党や野党は、アメリカの利益のために日本の富を差し出したとか、バブル経済が起きたと批判しますが。それは一面的な切り取りでしょう。江戸時代、農民が90%だった日本の産業構造は、明治から戦後の製造業の時代にシフトし。現在の日本はもう、サービス業など三次産業が67.3%を占める内需の国です。作業の構造というのは常に変化し、昔の時代には戻れないのですから。であるならば政府がやるべきは、財政支出なんですよね。
15歳以上就業者数(6151万人)を産業3部門別にみると,第1次産業は315万人(15歳以上就業者数の5.1%),第2次産業は1592万人(同25.9%),第3次産業は4138万人(同67.3%)となっている。
昭和の高度成長というのは、第1次産業が中心だった農村部の人口が、都市部に出て第2次産業にシフトした結果生まれた繁栄でした。頭の固い人たちは、昭和の昔のようにすればまた日本は繁栄すると思っていますが、そんなことはありえません。江戸時代の寛政の改革や天保の改革が失敗したのも、昔のように戻そうとしたからです。時代は常に変化しており、昔には戻れません。このことを絶対的な前提として、未来を考えなければなりません。
■消費税悪玉論の疑義■
景気浮揚策で必ず、消費税減税を言う人たちがいますが。個人的には、疑問です。消費税をゼロにしても、一般的な大衆のプラス分は、れいわ新撰組の甘々の試算でさえも年間22万円ほど。半減の5%ならば、11万円円ぐらい。実際には、8万円ぐらいという指摘も見た記憶が。消費税半減で8万円が手に入りました、「ヨッシャ、景気よく全額使うぞ!」とあなた、思いますか? 思いませんよね。一律給付金の10万円ですら、ほとんどが貯金に回されたという、現実があります。
消費税を半減しようがゼロにしようが、そこで景気よくパッとを使っても、未来ではさらなる収入があるという安心感がなければ、人は金を使いません。現状よりもっとひどくなるかもしれないなら、とりあえず貯金というのが日本人の行動パターン。消費税減税は、財源はなくなるわ、景気の浮揚には役に立たないわ、単なる人気取り政策にしかならないわと、最悪の方策だと自分は思っていますよ。
もちろん、日本の消費税が他の先進国並みに15%から20%あれば、減税は調整弁になりえますが。消費税憎しに凝り固まったマスコミや、竹中平蔵氏が不良債権の処理に公的資金注入を提言した時に、賛同しなかった経済学者とかの言うことを、自分を信じる気にはなりません。財務省の緊縮脳は批判しますが、それは別ですので。中曽根内閣での売り上げ税が、野党とマスコミの公約違反の大合唱で潰された結果、日本の税制は10年……30年は遅れた部分があります。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
