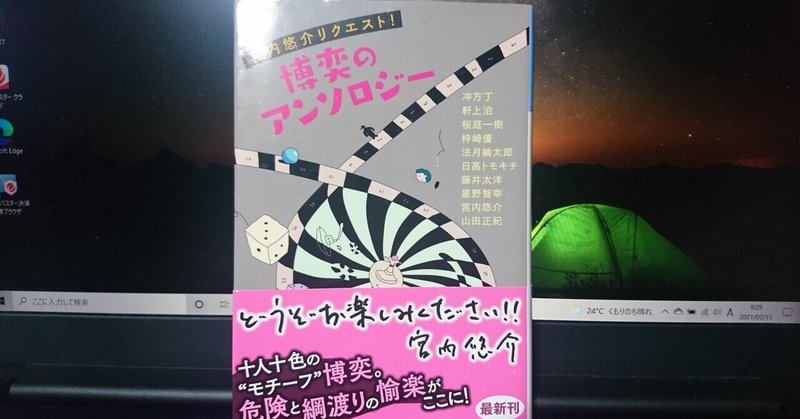
7/4 『博奕のアンソロジー』を読んだ
面白かった。
作家の宮内悠介が自らテーマを決め、自ら希望の作家を選んでそのテーマにまつわる原稿をお願いして書いてもらったという企画。冲方丁がそこに名を連ねていたので買ってみた運びで、ほかの作家は名前は知ってても作品はほとんど読んだことない人ばっかりだったが、新しい出会いを求めるいい機会にもなった。まさに読者たる自分にとっても博奕だったわけだ。結果としては、だいたい勝ち越したと言っていい。
梓崎優「獅子の町の夜」
金持ちの博奕。最初の話だからまずは前菜的にライトな賭け事の話だったのかなと思ったけど、全部読んでから改めて見直してみると、ある意味でこの一編がもっとも異質であったかもしれない。まったくやる必要のない、やっても損しかないような博奕。でも、それがこの婦人にとっては必要だからやる。一発逆転、一獲千金のチャンスだから賭ける、というような類のものではない、賭けるってのはそういうことじゃないんだと、初っ端からかましてきていたのだな。
桜庭一樹「人生ってガチャみたいっすね」
最新の博奕。すなわちガチャ……ただしソシャゲのそれと違って人生におけるガチャは、当人が当人の意思でエイヤッとスイッチを押して回すものではなく、どこかの誰かがいつの間にか押したスイッチの結果が善かれ悪しかれ唐突に襲い来る。あまりに理不尽だが、だからこそ益体もない空想が、どこかで誰かの救いに、いつの間にかなっているのかもしれない。時間も空間も越えて。
山田正紀「開城賭博」
運命の博奕。江戸無血開城をめぐる西郷隆盛と勝海舟の会談という話は冲方丁『麒麟児』でも読んでいたが、そこでも西郷と勝はともに、無用な被害は出さないようにと互いに奮闘していた。どちらも同じ思いを抱いていながら、しかし対立しなければならないという矛盾。多くの人々、多くの組織の思惑が混沌と化して、そのような状況を為さしめる。だがその巨大な混沌を解決する手段として勝が用意したのが、チンチロリンという博奕……すなわちこの世で最小の混沌であった。混沌を混沌で征す、それもまた博奕の一つの効能だ。
宮内悠介「杭に縛られて」
天命の博奕。こちらも前の話と同様、命がかかった状況で命運を博奕に託すというものだが、ひとつ違うのはその博奕に神意、天意というようなものが介在している……と、思われていること。理不尽や混沌と呼んできたものをそう言い換えただけとも、あまり信心深くない人間からすると言えるが。けれど、そこに自らの命運を託す相手を見るかどうかで、思考や判断も変わってくるものだ。
星野智幸「小相撲」
演技の博奕。博奕にイカサマはつきものだが、この話においては、そのイカサマをするのは賭けの対象そのものだという点で特異。上から言われるままに演技するならただの八百長相撲だが、そうではなく小相撲力士自身が客の動向を予想し、こういう展開を期待しているだろうと踏んでそれに対応した演技をする。一体どちらがどちらに賭けてるのかわからなくなる。しかも更に複雑なのは客と力士の間を取り持つ相撲賭博師の存在で、結局力士たちの物語もこの賭博師から聞かされた物語でしかなく、すべては賭博師の掌の上であった可能性も否めない。すっかり混乱してしまった。
藤井太洋「それなんこ?」
遊戯の博奕。人生の転機となる決断だったりあるいは人生そのものだったり、とかく大きなものを賭けてしまいがちな博奕だけど、簡単な遊びとしても博奕は広く親しまれているのであり、そうした遊びに対し本気で突っ込んでしまうとそれはそれでロクなことにならない、という話だろうか。遊戯に対して勝負を挑んでしまった失敗談の話。ただ、デイトレードとかのことがまったくわからないせいでもあるだろうが、最後にトレーディングでマウントとってきたのがどういう意味なのかちょっとわかりかねた。完全な勝負の世界に遊びみたいな博奕をしてる人たち、という逆の構図を示していたのかな。
日高トモキチ「レオノーラの卵」
寓話の博奕。これもちょっと、何か前提となる知識が無いとしっかり楽しめない話だったのかもしれないとちょっと不安になった。ガルシア=マルケスの短編とか。ファンタジックなおはなしとして楽しめばよかったのかしら。それならそれで面白くはあったけども。
軒上泊「人間ごっこ」
再起の博奕。初めて読む作家で、名前も(おそらく)聞いたことのない人だったが、なんだか面白かった。話だけ見るならば冴えない中年男性の空回りの人生の述懐なんだが、妙に洒落た物言いのせいでとてもハードボイルドなもののように見える。再起をかけた最後の博奕も、さてそんなシナリオ通りにいくかどうか定かじゃない。競馬場で見かけた男が実は元妻の今の男だってシナリオもあるんじゃないか。人生というドラマで、今ようやく男は晴れ舞台に立つ……と意気を上げるのもいいが、そうした目論見をあっさり打ち砕くのが博奕でもあるし、期待と不安が同時に押し寄せる終わり方だった。
法月綸太郎「負けた馬がみな貰う」
謎の博奕。通常のルールとは異なるルールで進行する物語、これもギャンブルものではよくある展開ではある。人と人の戦いではなく、ゲームそのものと戦うゲームというか。お話とはちょっと違う文脈になるが、作中に出てきた「暇をもてあました金持ち連中などいませんよ」という台詞に、確かにな、と不意に思ってしまってちょっと面白かった。金持ち連中、暇な時間があったらそれ使ってさらに金を稼いだりするからな。たとえばこういう変なルールのギャンブルを考えたりして。
冲方丁「死争の譜 ~天保の内訌~」
決戦の博奕。お目当てだっただけあってとても面白かったのだけど、しかしふと、あれこれって博奕なのか? と疑問が湧いてしまった。だってやっていることは要するに権威を求めての策謀バトルであり、それに用いられる碁という盤上遊戯は、他の話にあったチンチロリンだとかルーレットなどのゲームとは違い、完全に人の頭脳だけで終始展開されるゲームで、運や偶然性などが入ってくる余地はない。博奕とはなんというかもっと不確かなものので、運とか理不尽とか、神意とか混沌とかが介在してるものだと、これまでの話でさんざん語られてきたのではないのか?
いや……ある。おそらく、それはあるのだ。少なくとも、あそこにいた碁打ちたちは皆、それがあると思っていた筈だ。人智を極め、策謀を巡らし、定石を積み重ねあらゆる混沌を解き明かした先に、なお見通せぬ何かがある。どこからか自然と、「運が良かった/悪かった」としか呼べないような何かが発生し、予想だにしない場所へと連れて行ってしまう。だからこそ人は博奕に熱狂するのだ。
以上、こうして一覧してみると、「博奕」ひとつでタイプの異なる様々な物語があるもので、いいテーマを選んだなあと思う。このテーマを選んだ時点で、アンソロジーとしては「勝ち」だったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
