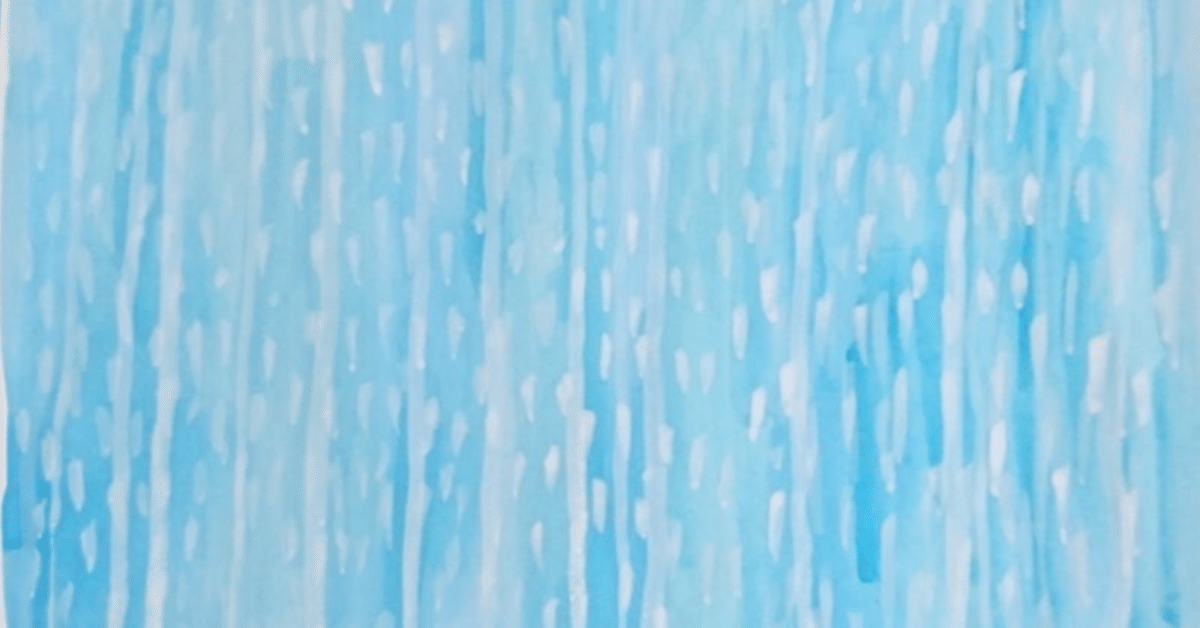
村田沙耶香『生命式』最後の4偏を読んで
『かぜのこいびと』
この小説はカーテンである風太が主体に物語が進んでいくが、実際の主人公は奈緒子である。子どもから思春期を迎えた奈緒子にとって、風太は初恋の存在なのだろう。
ユキオにとっては風太と浮気をしたという軽い冗談を、奈緒子は初恋の人を侮辱されたと捉えてしまった。奈緒子自身が幼かったのか、大人になる前の通過点だったのかはわからないが、まさかユキオ自身、自分の冗談が別れの原因になったとは夢にも思っていなかっただろう。
いくら相手がカーテンだとはいえ、恋愛感情は一言で終わってしまうことが、ままにある。いつまでも恋人のことを一番に考え、相手の気持ちを思いやってみても、ひとつの行き違いがすべてを終わらせてしまうというのは、ある意味恐ろしいし、だからといってすべてを恋人に捧げることなどできない。
奈緒子だって、ユキオだって、これから大人の恋愛を経験する中で、忘れてしまう思い出なのかもしれない。
ただし、それが村田沙耶香の書きたかったことかと聞かれれば、「そんなの知るか。本人に聞いてくれ」としか答えられない。
『パズル』
主人公の早苗が他人の生命体を感じていたい、というのは自分がただの物質であり、生きている実感がないから。
ただ、早苗は自分の感情をしっかり持っている。また、仕事仲間とは外観上だけとはいえ普通の関係を結べている。しかし、それが生きていることと繋がってこない。早苗にとって人間とは分泌液だと考えている。家庭環境について書かれてはいないが、孤独な幼少期だったに違いない。
『パズル』は自分の居場所を探す物語である。それまではビルと同じ箱だったので、嵌る場所はたくさんあったが、そこには生命の息吹が感じられなかった。自分の場所にピタリと嵌るジグソーパズルなんてない。自分を変えることでしか、パズルの1ピースになることはできないのではないだろうか。
早苗は自分のピースを変えるために、そして自分の分泌液を出すために、恵美子からエクササイズのDVDを借りたが、流れ出る汗も、激しく揺れる心臓の鼓動も機械的にしか感じられない。
ある日の飲み会の帰り道、早苗はあるビルの前で立ち止まる。ビルの中では人間たちが動いている。そこで初めて、早苗は自分の体=ビルで、自分の感情=人間なんだと気づく。そして、恵美子たちまわりの友だちも早苗の変化に反応する。
今の若者は友だちと繋がっていないと不安になる。それはやはり、自分が他の人たちとは違うおかしな存在なのだという、恐ろしい考えを払い飛ばしたいからなのかもしれない。そう考えると、早苗も普通の高校生に見えてきた。しかし、ここでも村田沙耶香は最後に切り札を出す 後輩の由佳を自分の胃袋だと思い、ストーカーの男を自分の心臓だと信じてしまう。一度は出来上がったと思ったはずのジグソーパズルの最後の一片を嵌め込むと、想像してもいない絵が出来上がってしまった感じ。
それにしても、村田沙耶香はどうして思春期の女性の多様性をこれほど理解できるのだろうか。
『街を食べる』
自然の味を食したことのない人たちが増えている。何事も効率性ばかりが優先され、農薬が使用され、時短栽培の技術が進んでいく。本物の野菜を食べたことのない人の増加が、更なる効率性を追い求める農業へという悪循環へと繋がっていく。今の若者と食事をすると、あまりにも貧しい食生活に唖然とさせられることがある。
主人公の理奈は田舎で採れたての、美味しい本来の味の野菜を食べた経験が、結果として日々の食生活を不満にしている。これが人により不幸なことなのか、幸せなことなのかは、人々の判断に任せるしかないが、理奈にとって不幸なことは間違いない。
田舎と都会の違いは、叢から取り出された野苺や緑の葉っぱや、雀が木に成っていると勘違いするような自然のたくましい食べ物と、人工の物としての食べ物との違いとなる。
田舎自体が美味しい食べ物であり、都会は食べ物と呼ばれる別の物の集積場に感じてしまう。都会では花壇ですら人工的なものなのだから。
食事は人生の幸せの非常に大きな部分を占めている。コロナウイルスの副反応である味覚障害は想像以上につらいことだろう。その食事に満足できない理奈は不幸だ。
ここまでは、まるで無農薬栽培の宣伝のような感想になってしまったが、ここからまた村田沙耶香独特の世界観が現れて、読者を動揺させる。
理奈は田舎を知ってしまっているから、都会の雑草すら人工的に汚されていたものと思ってしまい、東京のど真ん中である東京駅で取った蒲公英をゴミのように感じてしまい、吐き気がして食べなかった。 同僚の雪に話した祖母との田舎生活を、雪は人間らしい生活と言った。昔だったら当たり前の生活のはずが、都会を場違いに感じて、自分だけが他者から疎外されているように思ってしまう。
そのとき、理奈は東京に来た祖母から、「田舎も東京も大して変わらない」と言われたことを思い出す。 風邪から治った空腹感も手伝って、庭の蒲公英を花から根っこまで食べてしまう。それこそが自然の味、田舎の味だった。都会の見方が変わり、野生化する理奈。
実際、田舎に行かないと出会えないと思っている自然は都会の至るところにある。庭のない敷地一杯の建物にもいくつもの花壇に花は咲いているし、アスファルトのあいだからは蒲公英だって元気よく花開いている。
それに気づけるか、気づけないかで、人生の幅は大きく差がついていくだろう。都会で自然を感じる時間をもつことは、現代人には難しいことなのだろうか。
それでも、理奈は都会人を自然の世界に導くために、まずは同僚の雪に実験を開始し始めた。都会だって自然なんだと知らせるために。
『孵化』
自分とは何かを考える時期は誰にもある。特に思春期の女性に多いのかもしれない。「自分探し」などという言葉も死語とはならず、いまだに生き残っている。
自分には性格がないと主人公のハルカは中学生になって思い始める。相手に合わせて自分を変える演技を自然にしてしまうからだ。自分を人に好かれるためのロボットにさえ感じてしまう。
ハルカは「本当の自分」なんて誰にもないのではないかと悩む。しかし、5つのキャラを使い分けているハルカを親友のアキだけは知っている。アキは「本当の自分」なんて一人ひとりに幾つもあるものだからと、ハルカを慰める。
人間には幾つものペルソナを持っていて、その場その場で使い分けている。仮面を取ったときの自分が「本当の自分」だと思いたいのはわかるが、「本当の自分」というのは、それまで使い、経験したすべての仮面の総和であって、実は仮面の下はのっぺら坊なのではないかと思うときがある。
人にはそれぞれいろいろな性格を持ち、その中には矛盾した性格も含まれている。すべての顔を見せていては疲れてしまい、自分を表現できない。その場しのぎと思われる発言だって、本人の頭の中にない言葉が出るわけがない。
そう考えると、ハルカの悩みはマサシとの結婚で解決するのだろう。そして、幾つもの経験を積み、ペルソナを更に作り上げていくのだろう。それが大人になるということではないのだろうか。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
