
猪木が北半球と苦闘した熱い1年:柳澤健『完本 1976年のアントニオ猪木』
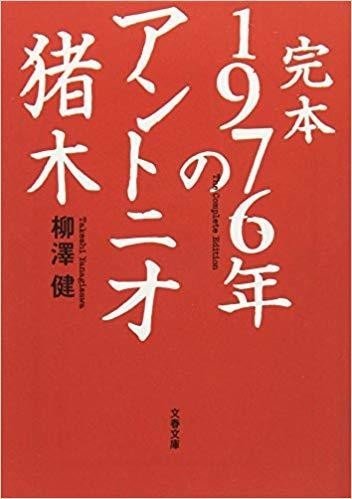
アントニオ猪木のタオルと同じく真っ赤な表紙と、文庫にして500ページ近い束の厚さ。正直なところ、「プロレスは詳しくないが、猪木はなんとなく好き」という知識の自分が、この迫力ある本を読み通せるか自信が無かった。だが、数多の当事者の証言からパキスタンの新聞記事に至るまで圧倒的な取材量で、あっという間に当時のプロレス・格闘技の世界に引き込まれた。
猪木は1976年にウィリエム・ルスカ(オランダ)、モハメド・アリ(アメリカ)、パク・ソンナン(韓国)、アクラム・ペールワン(パキスタン)と4試合外国人レスラーと、それもルスカ戦を除いて、勝敗の決まっていない「リアルファイト」での対決であった。それぞれ日本、オランダ、アメリカ、韓国、パキスタンのプロレス・格闘技事情に大幅にページを割き、猪木との一戦に向かうまでの、対戦相手の背景を事細かに説明している。「猪木の話はまだか~!」ともどかしく思う読者もいるかもしれないが、それぞれの文化と人種の中でプロレスが興隆、衰退していく「プロレスの世界史」は、よりプロレスというスポーツとショーの中間である競技の演劇性を際立たせていたと思う。
あの「猪木‐アリ状態」を生んでしまった、”世紀の凡戦”にも細かく言及し、凡戦になったのはアリ側が雁字搦めのルールを提示したなどの「伝説」を否定している。この本は決して「世界と闘った猪木はスゴイ!」と盲目的に猪木を褒める本ではない。むしろ、ジャイアント馬場を超えるべく、無茶苦茶なマッチメイクをし、高額の借金を背負った猪木に対して冷ややかな語り口である。
それでも1976年に猪木が行った「リアルファイト」こそ、日本を世界一のプロレス好き国家にしたとしている。海外では明確に線引きがなされている、プロレスと総合格闘技のラインをあいまいにし、そのシンボルになったのは猪木なのだ。既存の枠に囚われず、プロレスラーながらボクサーのアリと対決し、国会議員に転身してからも世界各国で「平和の祭典」を執り行い、実業家としてタバスコから永久機関まで手広く手掛けた、猪木の”迷わず行けよ”の精神がいかんなく発揮された最初の1歩が1976年なのかもしれない。それが失敗か成功かは、”行けば分かる”のだろう。
思えば猪木以外の、どの分野の「豪快な昭和の大スター」にも、躓いていた時期はある。巨人を球団史上初の最下位に落としたのは、ほかならぬ長嶋茂雄だし、北野武も初期の映画の評価は散々だった。立川談志にも独立騒動があるし、桑田佳祐にもKUWATA BANDがある。しかし、後年それが評価されることももちろんある。猪木の「リアルファイト」ものちの世界の総合格闘技につながり、「猪木‐アリ状態」から生まれたキックは、アリの選手生命にとどめを刺したというのが現在の定説だ。
猪木がパイオニア過ぎて理解されなかった苦悩と熱さを見事に描き切った渾身の一冊を、迷わず読めよっ!読めばわかるさ!
気になった箇所:
<「猪木ならばホウキと戦っても観客を沸かせることが出来るだろう」>(p150)
カール・ゴッチ門下の兄弟子、ヒロ・マツダの猪木評だ。だがこのホウキと…という言葉はリック・フレアーの発言だとプロレス好きの大学の後輩から聞いた。今調べたら、バンバン・ビガロの言葉という情報も出てきた。初出はどうあれ、プロレスを表現する素敵な言い回しだと思う。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
