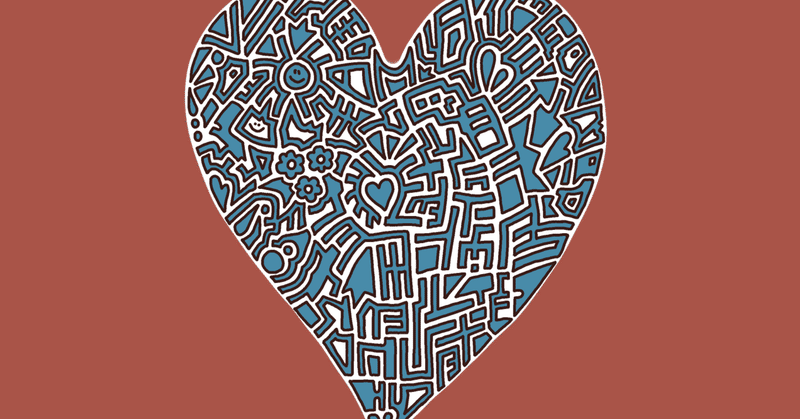
それでも俺はそれが恋であってほしい
初恋は叶わない。
叶わない恋はいつか失われるだけ。
それでも俺はそれが恋であってほしい。
たぶん最初から恋だった
一番古い記憶は泣き顔だ。まだ片手の指で年齢が数えられる頃、保育園の園庭の片隅でしゃがみこんでいるのを見つけた。大切に作って、そこに隠していた泥だんごをわざと壊されたらしい。誰に訴えるでもなく、ただ静かに泣く紬を見て、俺は怒りに震えたのを覚えている。彼女を立ち上がらせると誰にやられたのかと尋ね、相手を聞き出すと、行くぞと手を握り、そいつと対峙した。
後から聞いた話によるとすごい剣幕だったらしい。普段怒らない俺が大きな声で怒鳴ったので、周囲はだいぶ驚いたのだという。今思えば、紬にちょっかいをかけては嫌がられているあいつに、当時の俺は内心穏やかではなかったのだろう。ちょっかいをかける男子の気持ちもなんとなく察してしまったし、紬の周りをちょろちょろする男も気に食わなかったのだろうから。ちなみに、不謹慎にも泣き顔が可愛いと思ったことは今でも誰にも言わないままだ。
以降、俺は事あるごとにこの幼馴染を守らねばと思い続けてきた。
けれど今思えば、紬のためのはずだった言動のほとんどは、この幼馴染が自分のものであるかのように振る舞いたかった自身のためだったような気がする。
勝手に離れていくのは許さない
「紬、大学は県外に出るらしいな。」
保育園時代からの友人が世間話を持ちかけてきた。しかし、俺の顔を見て失敗を悟ったらしい。
「お前知らなかったの?ごめん。」
彼は、なぜか謝ってそそくさと目の前から去っていく。廊下に立ち尽くしたまま、昼休みの終わりを告げるチャイムがなるまでずっと目眩に似た衝撃に耐え、やっとのことで考えついたのはとりあえず本人に確認してみようということだった。
夕方、部活終わりに体育館でいつものようにボールを磨く紬に問いかける。
「紬。」
「ん?」
「進学先、県外に変更したって聞いたんだけど。」
「誰に聞いたの?」
手元のボールから顔を上げた紬はあからさまに困ったという顔をしていた。せっかく秘密にしていたのにバレてしまったというような。それを見て、俺はなおさらムキになって聞く。
「忘れた。本当なの?」
「うん。」
「どこにしたの?」
「落ちたら恥ずかしいから、受かったら教えるね。」
「やりたいことができた?」
「ん〜。なんか家から出たいなと思って。」
「家から出たい」のは嘘ではない。けれども、理由がそれだけではないことはすぐに分かった。紬が意図的にはぐらかすのは、俺には絶対に知られたくないのだという意思表示で、「家から出たい」のは、「俺と離れたい」からなのだと気付いてしまったから、俺はショックでそれ以上の追求は出来ず、そうかとひとこと言うのが精一杯だった。それでもまだ、自分がこんなに傷ついた理由は分からないままだった。
俺たちが生まれ育ったこの土地は交通機関や商業施設などもそこそこに発達して不便ではなかったし、そんな場所を飛び出してまでやりたいことというのもお互いになかったから、俺たちは実家からほど近い大学に揃って進学する予定だった。大学まで一緒かなんて、ついこの前笑い合ったばかりだったのに、これまでのように変わらず一緒にいるものだと疑いもしなかった幼馴染は、知らぬ間に、そして知られないように、ひとりどこかに行こうとしている。それなのに、俺には、紬から進学先を聞き出す理由も、引き留める権利もない。勝手に離れて行こうとしている幼馴染が、何もできない自分が、もどかしくてたまらなかった。
「お前、なんでそんなにイライラしてんの。ただの幼馴染なんだろ?」
友人が声をかけてきた。俺の不機嫌の原因が紬であることに気がついているのは、おそらく紬本人と、俺にうっかり紬の進学先のことを漏らしたこの友人だけだ。
いつかは一緒にいられなくなるって分かってただろと続けた友人の顔をまじまじと見つめて、そして唐突に理解した。友人たちに夫婦と揶揄される、この年頃の男女にしては近すぎる俺たちの関係を、紬はいつも腐れ縁だと言い返し、俺がただの幼馴染から格上げされる日は来ないのだと俺を含む周囲の人間に伝えていた。その事実と向き合うたびにドクドクと嫌な動悸が襲うこの気持ちは、恋と呼ばれるものだ。俺がこれまでに感じてきた不安やイライラは独占欲や嫉妬という類の感情から来るものだとやっと理解できたのである。
これまで混沌としていた心が、感情に名前が付いたことで怒涛のように整理されていく。それを呆然としたまま受け入れながら、縋るように自分を見つめてくる俺に、友人は呆れ果てたように遅いんだよこの鈍感野郎と言い、しっかりしろよとブレザーの俺の背中を強めに叩いた。そして、最近、紬が図書室で勉強していることを教えてくれた。そのときに決まって開かれている赤本と呼ばれる問題集のことも。そして、俺は紬に何も言わずに自身の進路を変更したのだった。
自業自得の恋
あれほどなんでも理解できると思っていた幼馴染は、恋を自覚して以降、厄介なほどに心の読めない相手となった。
どれほど関係の進展を図ろうとしても、近すぎたこれまでの距離が俺の前に大きな壁となって立ちはだかり、打ち砕くどころかヒビひとつ入れられそうにない。
このまま叶わない恋をし続けることは息苦しく、また、紬が自分から離れたがっていると知っていて恋を押し付けるのはあまりに自分勝手だと、そうなのだとしたら自身の心を殺して離れてやることが紬にしてやれることなのかもしれないと、ぐるぐると出口のない迷路を彷徨うように考え続けた。けれども、どんなに考えても玉砕して気まずくなる覚悟も、静かに諦める覚悟もできず、進路を変えられなくなってしまう前にどうしても紬の心が知りたくて恋人ができたのだと嘘をついてみた。これが史上最悪の成功だったと悟ったのは、紬が笑っておめでとうと言う直前に一瞬顔を歪めたことに気が付いてしまったからだ。その反応は、俺に醜い喜びと拭えない罪悪感をもたらし、ネタバラシと一緒に笑って伝えるはずだった言い訳は音にならずに消えた。卑怯な方法で得た希望は、自業自得を嘲笑うかのように苦しい恋心を加速させ、そしてそびえ立つ壁をさらに高いものにした。
結局、俺の恋にはなんの進展もないまま、それでも無事大学生になり、そして、俺の思惑どおり俺たちは大学で再会した。入学生ガイダンスで俺を見た紬は幽霊でも見たかのように固まっていたけれど、俺は何食わぬ顔で奇遇だなと彼女の肩を叩いた。それからも、紬が何か言いたげにするのに気付かぬふりをして、これまでと変わらず過ごし、正月、地元に帰って出席した成人式に揃って出席した。
久しぶりに再会した友人は、俺と少し離れた所に立つ紬を交互に見比べて半眼になる。
「このヘタレ野郎。」
「・・・久しぶりに会った友達に言うセリフがそれかよ。」
「それ以外になんて言うんだよ。いつまでウジウジやってんの?」
「いろいろやってんだよ、これでも。慎重にな。」
「とか言って、どうせまだちゃんとした告白すらしてないんだろ。玉砕しろ。爆発しろ。」
「相変わらず胸に突き刺さること言うな、お前。・・・そうだよ!まだ言えてねえよ!玉砕して爆発するって分かってるから言えねえんだよ!!」
やけくそのように白状する俺に、友人はどうしようもないやつだなとため息をつき、あの日と同じように俺の着慣れないスーツの背中を強く叩いた。
ジンジンと痛む背中を庇いながら、振袖を着て懐かしい顔と笑い合っている紬を眺める。言われなくとも、未だに告白ひとつできない自分はだいぶヘタレだと自覚している。唯一伝える本心は、いつもアルコールに頼ってばかりで本気にしてもらえないどころか、そういうことは好きな人に言えとまで真剣に諌められて、かつて卑怯な嘘をついてまで得た希望はもう欠片も残っていない。勝算がないと分かっているからこそ、いよいよ言えなくなってしまった男心も、同じ男なら友人には理解してほしいと、八つ当たりのように思った。
まだ愛にはできない
幸せをただ願うことができるのが愛というものだといつか読んだ本に書いてあった。見返りを必要としない愛にできればいっそ楽かもしれないと思わないこともないけれど、それでも俺はこの気持ちを恋のままにしておきたい。確かにいつかは愛に変わっていくのかもしれない。紬に幸せでいてほしいけれど、それは俺の隣であってほしいと諦めきれないから、幼馴染でしかない今はまだ、何も伝えられてない今はまだ、この気持ちは恋だ。
俺たちの関係がやっと動き出したのは、大学3年生の冬、就職活動の準備を始める頃だった。いつものように紬の部屋で紬の作ってくれた夕飯を食べているとき、紬は腐れ縁もここまでだねと俺に告げた。大学受験のときとは違い、俺に隠さなかったことからも、真剣な眼差しからも、幼馴染もここでおしまいと、紬が本気そう思っていることが読み取れた。
俺は口に運びかけた味噌汁のお椀を持ったまま固まり、お互い就活がんばろうねと柔らかく笑う幼馴染を見つめた。紬が、またひとりで行ってしまおうとしているのだと理解すると、今まで何度言おうとしてもつっかえて言えなかった言葉は、信じられないほど簡単に口から滑り出た。
「紬、好きだよ。」
「また言ってる。そういうのは好きな人に言わないとだめだっていつも・・・。」
「だから言ってる。俺、紬のこと好きだよ。ずっと。幼馴染じゃなくて、恋愛的な意味で。」
だから、ここでおしまいにされたら困ると続けると、今度は紬の方が時が止まったように動かなくなった。瞬きすらせずにあまりに長い間固まるので、心配になって声をかける。
「紬?」
「翔太、何の話してんの?」
「何って、俺が紬のことが好きだって話。」
一度零れ落ちたらあとは気負いなく言葉が出てくるようになった。今を逃したらたぶんもう次はない。ぬるま湯に湯かるように先延ばしにしてきた恋の決着はここで決めないと、行方知れずになってしまう。
驚きすぎて目が溢れてきそうだと緊張感もなく思っていると、見つめていた紬の瞳からボロボロと涙が溢れ始めた。あまりに急に泣き始めたので、呆然と見ていたがどう考えても泣かせたのが自分しかいないと気が付いて慌てる。
「ど、どうした。」
「〜どうしたじゃないのよ!何を今さらそんなこと言って!」
続きは涙に消えた。しゃくり上げるのを我慢するように肩を震わせる紬に、ごめんと何回も謝りながらティッシュを差し出し、顔を覗き込むようにして聞く。
「ごめん。でも、俺は、俺たちの関係を腐れ縁の幼馴染じゃなくて恋にしたい。紬はそれは嫌?」
あの頃のことを思うと、叶うかも分からない恋のために進路を変更し、その割にいつまでもうじうじぐだぐだとヘタレで、みっともないし、馬鹿みたいだと思わないこともない。散々泣かせたし。ちょっとストーカーっぽいところも黒歴史だ。
けれど後悔はしていない。
馬鹿みたいだったから紬を今日まで離さないでいられたし、みっともなかったからこそ、これからも離さないでいたいと、大事にしたいと、心から思っているからだ。
つい先日、好きだと伝えられたときとは打って変わって、かつてないほど緊張しながらガタガタと震える手で差し出した銀の輪っかは、今は彼女の薬指に納まっている。
「お前らが20年もお互いのこと好きなの、知らなかったのお前らだけだから。」
側から見ててもどかしいったらなかったと、結婚式に招いた友人はそう語って笑った。
なんとか書き上げたこの物語の登場人物にピンと来た方、いつもありがとうございます。
そうです。コレはアレの別視点の続きのような物語です。
もしも、気になるぞと言ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひこの記事をどうぞ。
最初に決めていた結末にはなんとか着地してくれたものの、自分で書いていながら、翔太くんがもだもだし始めたときにはもうダメかと思いました。お陰でどんどん話が長くなりました。
もうさ、翔太くんさ、もどかしいです、とても。お友達が私視点です、もはや。
とりあえず、ふたりのことは書けたから満足なのだけど、こうなったらお友達から見たふたりのことも書きたい今日この頃です。
