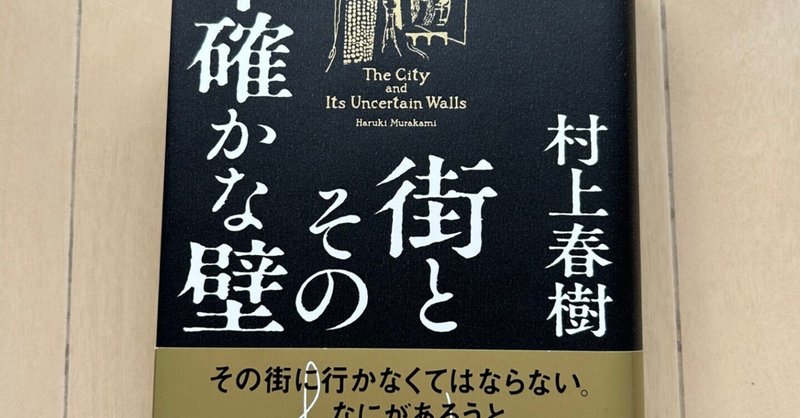
*読了4冊目*『街とその不確かな壁』
『街とその不確かな壁』村上春樹著を読んだ。
村上春樹さんの長編小説は純愛をテーマに描かれていることが多いが、この話もそうである。
なぜ純愛なのか?
おそらく恋が一番私たちの「タガを外させる」ものだからであろう。
この小説の中には、ふたつの純愛が描かれている。
主人公の「ぼく」の純愛と、子易さんの純愛だ。
どちらも愛する女性が人生の途中で去ってしまい、残された彼らは喪失感を抱えたまま生きている。
それを子易さんは、
「いったん混じりけの無い純粋な愛を味わったものは、言うなれば、心の一部が熱く照射されてしまうのです。そのような愛は当人にとって無上の至福であると同時に、ある意味厄介な呪いでもあります」
と表現している。
心に受けた傷があまりにも深かったため、子易さんはスカートを履き、図書館という城に閉じこもった。
一方、主人公の「ぼく」は、自分の意識の中に作り上げた壁の中の街という架空の世界に逃げ込んだ。
しかしその街は架空の街でありながら、もはやどちらが実体でどちらが影かわからなくなるほど、彼にとっては本物の街なのだ。
たとえばソクラテスは『パイドン』の中で、
「美しい恋人への愛とは、神の国を追い求める気持ちを、対象を人間にすり替えて体験しているものなのだ。
よって「美しい者」への愛とは、本来は「美しい神の国」を求める気持ち、つまり「叡知」を求める気持ちへと移行していくものなのだ。
この至高の恋に比べれば、リュシアスの説く、「狂気を伴わぬ恋」など、しょせん「この世だけの正気」、全くケチくさい奴隷根性としか言いようがない」
と喝破している。
つまり「恋とは狂気」であると。
「ぼく」の愛した「きみ」が架空の街の話をしていた頃、彼女は家にも学校にも居場所がなかった。
その苦しい環境の中で、彼女は自分の「本体」が暮しているという別の街の構想をつくりあげたのだろう。
そしてここに居るこの小さい自分は「影」なのだと。
「ぼく」がコーヒーショップでこんな話をするシーンがある。
「ガルシア=マルケス、生者と死者の分け隔てを必要とはしなかったコロンビアの小説家。
何が現実であり、何が現実では無いのか?いや、そもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものは、この世界に実際に存在しているのだろうか?ガルシア=マルケスにとってはごく普通のリアリズムだったんじゃないのか。見える情景を見えるがままに書いていただけじゃないのか」
と。
そこでふと思ってしまったのは、作者にもこういう世界がリアルに見えてるんじゃないかということで、村上春樹って不思議な小説を書くよねって言われているけど、ただ実際に見えたものを淡々と綴ってるだけなんじゃないかと思ってしまって、思わずブルっと震えた。
小説の途中から唐突に出て来るサヴァン症候群の少年は、阿頼耶識(あらやしき)の擬人化ではないか?と思った。
唯識(ゆいしき)という考え方がある。
人間には「1眼識」「2耳識」「3鼻識」「4舌識」「5身識」という五つの識(五感)があり、これを認識するために「6自意識」があり、その奥に「7末那識(潜在意識)」があり、さらにその奥に「8阿頼耶識」という全部で8つの識(しき)があるというものだ。
「8阿頼耶識(あらやしき)」は別名「蔵識(くらしき)」とも言われるように、あらゆる宇宙の叡智が収められている蔵のような場所とされている。
図書館の本をむさぼり読んで、その内容をすべて吸収してしまった少年は、まさに歩く図書館、歩く阿頼耶識のような人だなと思った。
不思議な街の壁は、「6自意識(頭の中の壁)」のように思える。
となると「8阿頼耶識」の境地で生きている少年にとって、そこはいくらでも出入り自由な壁なのだと思う。
というのも、8つの「識(しき)」の階層がある中で、上の階層にいるものは下の階層にスルーパスで入れるに違いないというのは、今ここで勝手に私が思いついた仮説である。
その勝手な仮説によると、少年はスルリと主人公の「ぼく」の自意識の中にも侵入できたことになる。
だから「ぼく」と「きみ」しか知るはずの無かった壁の中の地図を描くことが出来たのではないだろうか。
もっと言えば、誰でも「6自意識」を越えて、「7末那識(まなしき)」「8阿頼耶識(あらやしき)」へと、自分の意識を引き伸ばしていくことが出来れば、この街の壁を越えることが出来るのではないか?
いわば、「ぼく」も子易さんも、自意識の壁を突破してその先に行ってしまった人である。
そのきっかけとして「とてつもない純愛」の体験がある。
結局は、自分の意識が自分の世界を創っているのだと思う。
平凡な毎日が続いていくのは、自分がいつも頭の中で同じことを考えているからで。
だが恋は、ある日突然侵入してきて、暴力的なくらいにすべての平穏を奪い去り、その代償として(?)常識的な頭では中々外れないタガを鮮やかに外してくれるものなのだと思う。
それが外れることが「至福」なのか「呪い」なのかは分からないけれども。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
