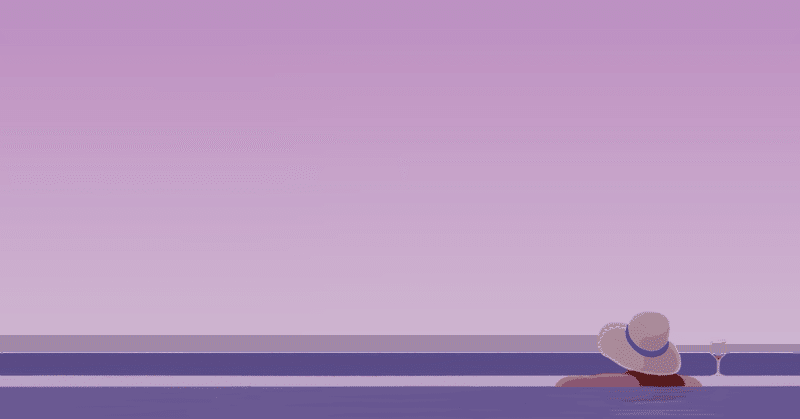
連載小説『五月雨の彼女』(12)
ガラス窓の向こうでは、変わらず雨が降り続いている。
排気ガスを含んだ空気を洗い流すように、他の雑音を掻き消すように、大きな雨粒はとにかく空から地下と全てを押し流していく。
穴場と踏んでいたこの喫茶店も、雨宿りにやって来た人々で賑わい始め、店内には温かいドリンクを飲む人々の体温でほやほやとした蒸気が漂い始めた。
あの若い店員は、ただ事ではない雰囲気を醸し出す私と未知華の席を遠ざけるよう、店の入口に近い席から客を案内していたが、とうとう空席も僅かとなり、未知華の背中側にある隣のテーブル席まで埋まってしまった。
「すんませーん! オレンジジュースとコーヒーフロートお願いしまーす」
未知華のすぐ後ろの席に座った体格の良い男が、他のテーブルにドリンクを届けていた店員に呼びかける。男は、羽織ったカーキ色のMA-1ブルゾンのポケットに両手を突っ込んだままそわそわしており、どうも落ち着きがない。
「マイ、ホントにオレンジジュースだけでいいのか? ほら、チョコレートパフェもあるぞ」
「うん! 今日は、パパに運動会の靴も買ってもらったもん」
「子どもがそんなこと気にすんな。欲しいもん、他にもないのか?」
「パパも無理しないでいいよ。また来月会う時に、一緒にパフェ食べたいな」
背を向けて座る男の向こう側で、女の子の声がする。言葉も声もしっかりしており、小学校五、六年生くらいだろうか。
どうやら、何かの事情で一緒に暮らしていない父娘のようだ。
私と未知華は、暫く黙って親子の会話を聞いていた。私たちの会話は小学生の女の子の前でするにふさわしいものではないし、少しだけふたりの会話が聞いていたいと未知華も思ったのではないだろうか。
「ねえ。おばさん、元気?」
ふいに未知華が口を開いた。
「え? 私の母のこと?」
「そうよ。鞠子さん。私、あんたのことは嫌いだったけど、鞠子さんには感謝してるの。あの人は、幸せに暮らしてる?」
「母は、私が高校三年の時に病気で亡くなったわ。幸せだったかは……、正直分からない。あのマンションから引っ越した後は、いつでも家にいたし、あなたのお母様の他に仲の良かった友人なんて見たことないの」
「そう……。鞠子さんも死んじゃったんだ。あんたは知らないかもしれないけど、私と母さんがマンションを出て生活に困っていた時、時々、あんたの家の裏口に行って、鞠子さんからお金を受け取ってたの。鞠子さん、母さんに実家に帰れとも言わなかったし、いつも嫌な顔ひとつしないでお金を貸してくれてたわ。母さんが仕事を見つけるまで、そのおかげで何とか生活できてた。鞠子さんに……、『ありがと』って言いたかったな」
「もしかして、あなたのお母さんも……?」
母が未知華の母に金を渡していたことにも驚いたが、未知華の「鞠子さん『も』」という言葉の方が気になった。
「うちは、頑張りすぎて潰れちゃったのよ。私が高校卒業して就職するまでは、何とか頑張ってくれたけど、私が稼げるようになって安心しちゃったのね。父さんがいなくなってからずっと気を張り詰めてたけど、ぷつっと糸が切れたみたいに、ひとりで真冬の川に入ってあっち側に行っちゃったわ」
「そう……。悲しいわね」
「悲しい……ことなのかしら。母さんの人生は、きっと良い時期もあったけど、後悔の多い人生だったわ。父さんが出て行ったことも、自分が完璧じゃなかったせいだって、ずっと責めてた。私が何を言っても耳に入らなかったし、苦しみ続けることがいいことだとも私は思わない。母さんの人生は、母さんのものだもの」
「そんなこと……」
私は言いかけて、言葉を止める。
母親に先立たれにも関わらず、どこか冷めた目をした未知華は、辛いことを直視しないよう、敢えて記憶を遠くから眺めるようにして、吐き出した言葉を自分に言い聞かせているように見えた。彼女は、そんな言葉で納得せざるを得なかったのかもしれない。妖しい笑みをしまった冷静で美しい未知華の横顔は、少し痛々しく思えた。
「母さんと違って、鞠子さんは後悔もなく幸せだったはずよ。あの人は、母さんのなりたかった『完璧な妻』で『母親』だったもの。私、完璧な妻の顔を装ってる人間には虫唾が走るけど、あの人だけは違うわ。鞠子さんは、旦那さんを心から愛していたし愛されているの。愛している人の側から離れることも、手放されることもなかったはずよ。私みたいな女が男に与える刺激とは違うけど、ああいう完璧な女は嘘がないから、どうしても側に置いて大事にしたくなるのね、きっと」
未知華は、窓から遠くの景色を眺めるようにうっとりとした顔でそう言ったが、私は内心「本当にそうだろうか」と考えていた。
家族を愛しているから、嫁を嫌悪する義父のいる加賀原の邸宅に、夫について戻る。
夫からの電話にいつでも出られるように、年中、家の敷地の中で過ごす。
家族の予定のために、外の世界と接することも、友人を作ることもせず、時間と労力をいつでも提供する。
傍からみれば、妻として、母として、立派に役割を果たしていたように見えたろう。しかし、本当に母が本心から望んでいたことなのだろうか。必ずしも完璧であることが、本人の幸せと結び着くものでもない。
少なくとも、私からすれば母の生き方は窮屈に思えるし、母が完璧であればあるほど、私の未熟さを際立たせ、「完璧でない罪」が私の心に重くのしかかった。私の苦しさが母の幸せの代償だとしたら、皮肉なことだ。
いくら思いを馳せてみても、母の声は聞こえない。
──ねえ、未知華ちゃん。
私たち、何が善いとか悪いとか、完璧とかそうじゃないとか、形式的なことに未だに囚われている。
こうなりたくないと本心では嫌っている部分が、そのまま鏡みたいに私たちに映し出されている。
苦しくて本当は手放したいのに、その痛みをどうしても手放せなくて、いつまでもしがみついている。
私たち、誰かの愛を手に入れるためには、母親や愛人や先の誰かの真似をし続けないといけないの?
「わ! パパの意地悪! 何で勝手にアイスクリーム、私のオレンジジュースに入れちゃうの!? しかも、コーヒーもちょっと入っちゃったじゃん!」
「マイ、食べてみろって。オレンジフロート、うまいから」
「もお、最悪! パパのもコーヒーフロートじゃなくて、ただのアイスコーヒーになっちゃったし」
「パパのはいいんだよ。マイ、アイス好きだろ?」
隣の席では、どうやら父親がコーヒーフロートのアイスクリームを娘のオレンジジュースに投入したらしく、わいわいと騒ぎ始めた。
「うーん……、味は微妙!」
「そうかー? 絶対うまいと思うんだけどなあ」
「パパ、普段オレンジジュースなんて飲まないでしょ。もお、しょうがないなぁ」
父娘は少し喧嘩をして、最後には顔を見合って笑い合う。
誰かの本当の幸せなんて、私たちには分からない。
幸せの絶対条件なんて、私たちには正解を出せない。
けれど、今、私たちはきっと同じことに気付いている。
もし、私が完璧な娘や妻でなくても、たとえいつか側から離れていってしまうとしても、愛する人とただ向き合って、笑い合う。そんな時間がたくさんあれば、心の中身が違っていたのかもしれないということに。
私たちは、条件なんて関係のないただの「私」でいて、心から笑い合える人を愛し、愛されたかった。
ただ、それだけ。
(つづく)
つづきは、こちらから↓
第一話は、こちらから↓
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
