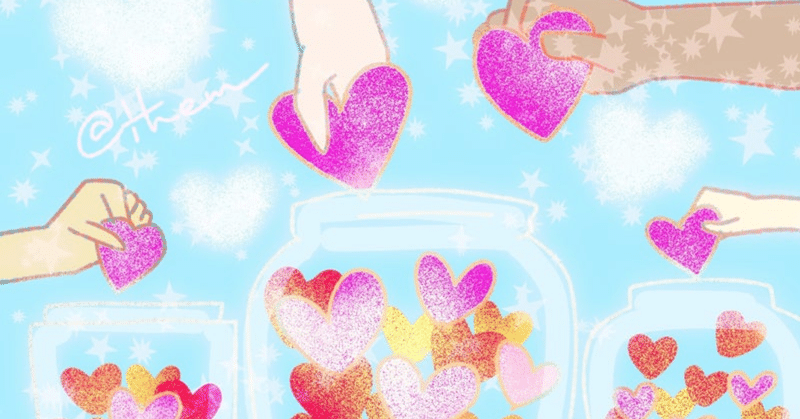
グローバル育児、子供の学校生活のギャップ
こんにちは、7歳と4歳の子供を育てるママです。発達心理学に基づく育児カウンセラーの資格を普段の育児に活かしながら、バイリンガル育児をしています。
今回は、グローバル育児をしていたら、学校でのDonation(寄付、募金)についてギャップを感じたので、書こうと思います。
グローバル育児とは、勝手に名付けましたが、外国の文化や価値観や考え方を育児に取り入れるといった感じです。
現在、子供たちは上の子はイギリス系の学校、下の子はカナダ系の学校に通っています。
学校に通わせて感じたのは、Donationの頻度が高い!ということ。
ついこの間Donationでお金持っていったのにまたいるの?!
と、今まで寄付に慣れていない私はびっくりしました。
また、子供たちが街でDonationを集めることもあります。
この頻度が高くて、最低でも1ヶ月に1度。最低でも。
自分が小学校の頃って赤い羽根募金?くらいしか自分が寄付に携わった覚えがないような・・・
こんなにDonationするものなの?
と思って、よくよくDonationの内容を子供に聞いてみると、
難民のための募金、だとか、
必要な物を買えない子供たちのために日用品やおもちゃを入れたプレゼントボックスを作ったり、
最近では、トルコとシリアの地震を支援するための募金など。
募金先も目的も明確で本当に必要なものばかり。
え、ちょっと待ってよ娘。「難民」という言葉、私が7歳のときには出会ってない。。。
「トルコ」も「シリア」も子供のとき知らなかったよ。。。
このDonationを通して子供たちはとても大事ななにかを感じてくれている気がします。
それは明確にはなんなのか、はっきりとは言えませんが、他の人に優しくすること、困っている人を助ける気持ち、思いやる気持ち、だけではなく、もっとグローバルな視野で世界の現実を具体的に知る勉強にもなっています。
「難民」はどういう状況でどこにいるのか。
自分たちと同じ歳のお友達に、生活に必要な物を買えない子が世界にいるという現実。
「トルコ」と「シリア」はどこで、今何が起きているのか。
本当にお金を必要としている人たちはどんな人達でどこにいるのか。
一つ一つその言葉の意味を勉強しながら、7歳と4歳なりになにかを考え、なにかを感じながらDonationしているようです。
自分の子供の頃は赤い羽根欲しさに理解もせずに募金していただけだったよなんて子供たちには内緒にしときます。
何より、え?こんなにDonationするものなの?なんて浅はかに思った自分に頭突きしたいです。。。
募金は人のために役に立つ行動、という認識は世界統一かもしれませんが、どのようにそれを教育に落とし込んでいくのか、募金という行動で子供たちに理解してほしいことは何なのか。それは国の意向によって違うようです。
こんなところにも密かに国の意向が影響しているとは。
教育現場は政府の意向が大きく影響する場所であって、その価値観や常識が知らないうちに自分の価値観や常識の一部となっています。
そして私のように凝り固まってしまう。
グローバル育児を通してようやく凝り固まってた価値観や常識を少しずつ壊している最中です。いまごろですが、、、
日本という国は世界の中では裕福で豊かな国なので、日本という国を中心に考えては偏った知識、常識、価値観になっていたようです。
子供たちには、マクロな視点で世界中の国の現実を知り、日本とどう違うのかを知ることで、客観的に日本を知り、グローバルで柔軟な価値観と多様な常識を知ってほしいと思って育児しています。
大人になって新しい価値観や常識に出会うと、生まれ変わった気分になります。これって私も少なからず成長できているのかな。そうだといいな。
ここまで読んでくださりありがとうございました!他にも興味のある記事がありましたら是非読んでください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
