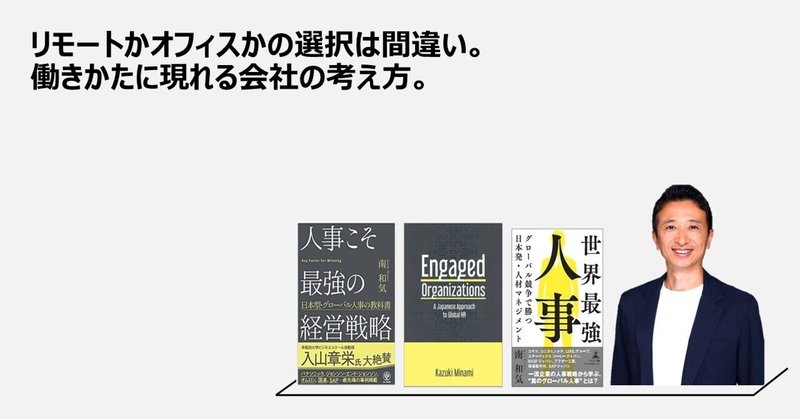
リモートかオフィスかの選択は間違い。働きかたに現れる会社の考え方。
5月8日、新型コロナウイルス感染症の分類が「2類相当」から「5類」に変更となる予定です。いよいよ「感染リスクのためのリモートワーク」を余儀なくされた状況から、本来のあるべき働き方に向けて、各企業が意思決定するタイミングとなってきます。
米国では日本に先駆けて働き方についての変化が始まっており、連日ニュースが報じられています。そこで今回は、米国の動きも解説しながら、これからの日本の働き方の変化について考えていこうと思います。
オフィス勤務へと回帰している米国企業はごく一部
すでに米国では、大手企業を中心にオフィス勤務(出社)の方針を打ち出しています。
▶-----------------------------------------------------
・アマゾン「週3日出社義務化」に従業員5000人超が社内Slackで猛反発。「働く場所を選ぶ権利」求め請願書も
・ディズニーCEO、週4日のオフィス勤務復帰求める-3月1日から
-----------------------------------------------------◀
その他、AppleやMetaといった大手IT企業も、続々とオフィス勤務へと舵が切られている報道が目立ちます。

これらの企業の共通項は何でしょうか?
答えは、「これら日本でニュースになるような企業は、超大手企業であり、極めて高いブランド力と採用マーケティング力を誇る企業である」ということ。
そもそも国土の広い米国においては、コロナ禍になるずいぶん前からリモートワークを採用する企業は珍しくありませんでした。オフィスには立ち寄らずに、自宅と外出先との直行直帰の勤務パターンもよくあります。採用側としてもリモートワークは強みとして押し出せるので、多くの企業ではいまでもリモートワークを導入しています。
しかし、景気の減速傾向が見られる米国においては、「リモートワークだけ」を前提にする働き方にしておくメリットが少なくなってきていることも事実です。そのため前述した大手企業では、リモートワークを完全禁止にするわけではなく、「オフィス勤務の比率を増やす」も出てきているというわけです。
日本でリモートワークのデメリットが声高に語られるのは当然
それでは、日本企業の働き方は新型コロナ「5類引き下げ」によって、どのように変わるのでしょうか。
結論から言うと、「出社とリモートワークの最適なハイブリットを目指すべき」と私は考えています。
日本企業では、コロナ禍の感染対策として一気にリモートワークが進みました。もともと在宅勤務制度を導入していた企業も一部ありましたが、制限があったりする企業が大半だったと思います。しかし、コロナ禍によって社会全体がリモートワークを推奨したことが、各企業の働き方を大きく変えました。
いざリモートワークになってみると、これまで対面でないとできないと思い込んでいた業務が、実はオンラインでもできてしまうことに気づいた3年間だったのではないでしょうか。
また、出社しなくても良いとなると、単純に通勤時間が節約できるだけではなく、これまで時間や場所の制約によって退職せざるをえなかった優秀な社員が辞めなくて済むようになったり、学びのための機会をより多く確保できるようになったり、さらには働く場所にとらわれずに、全国、また世界中から優秀な人材の採用を行えるようになったりと、これまでには得られなかった多くのメリットを得た部分もあったと思います。
一方で、オンラインだけですべての業務が円滑に進むわけではありません。日本より10年以上前からリモートワークを採用していた米国企業でも、最初からうまくいったわけではないのです。以下のような理由からリモートワークに反対する経営者は多くいましたし、私自身、長く海外企業でリモートワークが当たり前だった環境でしたが、当時は弊害を感じる場面も多くありました。
▶-----------------------------------------------------
・仕事の内容が変わっても、業務変更の連絡や意思疎通がすぐにできない”
・新入社員がなかなかチームに溶け込めない
・突発的な仕事に柔軟に対応できない
・多人数で集まってフリーに意見を出し合うことが難しい
-----------------------------------------------------◀
このように、リモートワークは変化の多い仕事や複雑な合意形成、多数でのディスカッションなどの業務には向きません。したがって、こういった業務を行う場合は、オフィスワークのほうが効率的です。
日本は本格的なリモートワークの環境になって3年です。しかもその間は感染対策のためのリモートワークとなり、働き方についていろんな実験ができたわけではありません。リモートワークのストレスに対する反作用で、デメリットの方が取りざたされるのは自然なことだと思います。
リモートかオフィスではない。「集まる仕事」か「集まらなくてもよい仕事」なのか
ただし、働き方の議論は、「リモートワーク」か「オフィスワーク」かという選択肢で考えてはいけません。例えば、オフィスに行ったところで、仕事に関わる同僚はオフィスに来ておらずオフィスでオンラインミーティングをするのであれば、リモートワークと実質何も変わりません。
働き方とは、「どこで仕事をするか」ではなく、「どんな仕事をするか」という基準で考えなければならない問題です。
先述したとおり、リモートワークで生産性が上がらない仕事は、「複数人で集まらないとうまく進まない仕事」です。いろんな意見が同時にでて、あちこちで議論しながら意見を出し合うような仕事や、複数人で内容を確認しあうような仕事は、やはり集まって行う方が圧倒的に効果的です。
また、偶然の会話の中からアイデアが生まれることも確かにあります。そういう意味では、例えばある程度まとまった人数で定期的にオフィスワークの日をつくる。ということも効果的かもしれません。
つまり、仕事内容によってどう働くかを選べる働き方にすることで社員にとっても、会社にとっても働き方によるメリットは最大化することができます。
感染対策が収束したことを理由に、単に「コロナ禍以前に戻る」企業は、結局この3年間何も学ばなかったことになります。
これからみなさんが会社を選ぶことがあれば、働き方はどんな制度になっているのかを確認するだけではなく、「なぜその働き方にしているのか」を質問してください。その回答のなかに、会社が社員の生産性についてどう考えているかということが浮かび上がってきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
