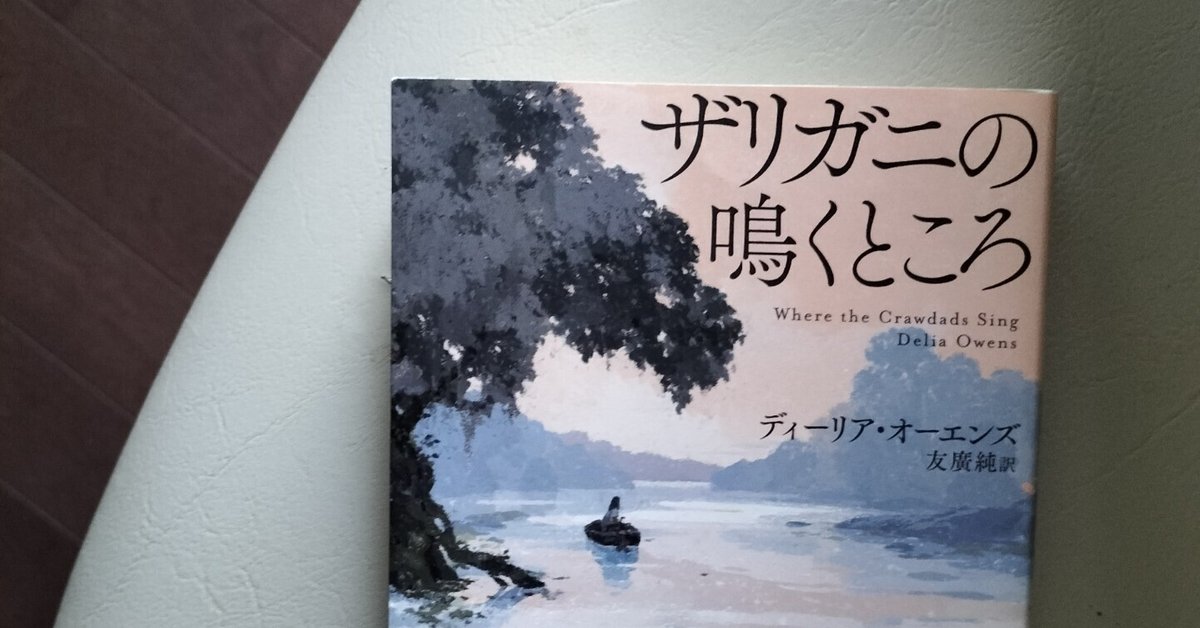
ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』友廣純訳、早川書房
1950年代のアメリカ、ノース・カロライナ。大西洋側の湿地が多い地域が舞台だ。親兄弟に見捨てられ、粗末な家でたったひとりで生きる少女の話。と聞いていたので、さぞ暗くて重い話なのだろうと構えていた。でも読み始めると、とても面白くてスイスイ読んでしまった。(アメリカでベストセラーになる本だから読みにくいわけはないのだ。)
そんな過酷な環境で育ったということは、きっと読み書きも満足にできない、半分野性の少女なのだろうと想像していたが、途中で近所の少年に読み書きを教えてもらい、ついで学校の勉強も教えてもらい、その後は少年から借りた本をどんどん読んで、ついには湿地を観察した独自の成果を本として出版するようになる、というのは非常に意外で面白い展開だった。
電気も水道もない家でたったひとりで暮らす少女カイアは、泥を掘って貝を採り親切な黒人に買ってもらう。料理ももちろんできなかったが、なんとか工夫して母親が作っていたようなものに近い食べ物が作れるようになる。一種のロビンソン・クルーソー的なサバイバル小説の要素もある。(でも女の子だし、少し大きくなってからは、男たちに襲われるのではないかと心配しながら読んでいた。女の子がひとりで生きる話はどうしてもそういう心配をしてしまう…。)
あるとき殺人事件が起きて、カイアが容疑者として逮捕され、裁判になる。誰がどうやって殺したのかという推理小説の要素もあるけれど、読み終わって一番印象に残ったのは、少女の孤独の背景にある、それまでまったくなじみがなかったアメリカ中部の湿地の風景だったかもしれない。その風景の中に生息する様々な生きものが描かれていて、豊かで美しい。
映画化もされ、そちらも評判が良かったのは知っていたけれど、特に見ようとは思わなかった。今回この小説を読んだのは、きたやまおさむ『「むなしさ」の味わい方』に冒頭部分が紹介されていたからだ。人間の心の〈沼〉には、死もあるけれど再生の可能性もあるという著者の説が、冒頭の一節を引用しながら語られていた。
追記:原著だと巻末にカイアの料理のレシピがついているらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
