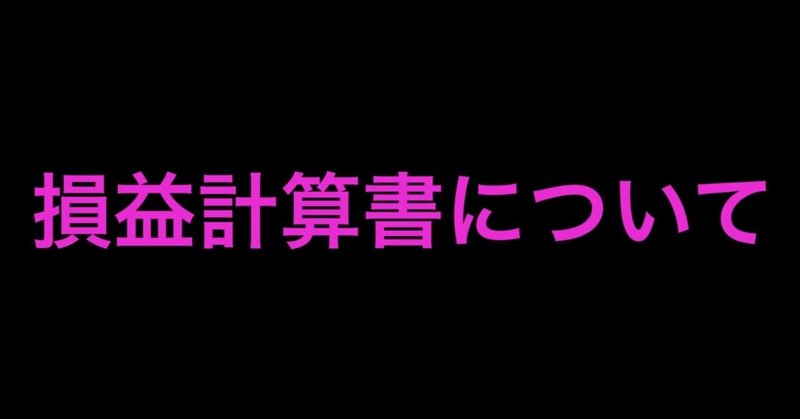
損益計算書について
こんにちは!
今回は損益計算書についてです。これは1年間でどれだけ儲かったか、
または損したかといった経営成績を示す決算書です。イギリスでの
「Profit and Loss statement」という呼び方から日本では「P/L」と
呼ばれています。
では、早速ですが!
損益計算書には5つの段階の利益があります。
「売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期純利益→
(税引後)当期純利益」という順番で企業がどのような利益をどれだけ
出しているかを知ることが出来ます。

この5つの利益の意味について解説していきます。
売上総利益:商品そのものの売却益つまり粗利益
営業利益:本業で得た利益 ※人件費などは通常は販管費となります
経常利益:本業の利益と金融損益
税引前当期純利益:事業の売却など臨時の損益を反映
当期純利益:最終的に株主に帰属する利益
このうちどの利益に注目するかは分析を行う目的によって異なります。
例えば、投資家なら当期純利益、銀行などの債権者は営業利益、経営者は
経常利益といった感じです。
損益計算には、収益と収益獲得のために払った費用を対応させる「収益と
費用の対応」というルールがあります。対応させる方法は2つあり、売上高
と売上原価を対応させるといった「個別対応」と売上高と販管費を
対応させるといった「期間対応」があります。
また、P/Lには収益や費用をそれぞれどのタイミングで計上するかという
問題があります。計上のタイミングは3つあります。
まず、1つ目は発生主義です。特徴はその会計期間の企業活動の成績を
評価できるという点です。そして、処分をすることが可能な利益を最も
正確に計上することが出来ます。しかしその一方で、企業に継続性がある
場合、その企業の評価を十分に行うことが出来ないという弱点があります。発生主義の損益は現金収支の差ではなく、収益と費用の差で損益を
計算します。
2つ目は実現主義です。収益を未実現のものは計上できないという決まりがあります。企業活動のサイクルの中でどの段階で利益を計上できるかという収益認識のタイミングで計上するものが現実主義となります。
3つ目は現金主義です。現金主義の特徴は収益と費用が確定しているもの
しか計上していない点にあります。企業会計における収益・費用は、
現金収入・現金収入とは一致しません。つまり、利益はお金があることを
意味するわけではありません。
現金収支について補足するのが次回説明する「キャッシュフロー計算書」に
なります。
次は、売上原価の計算方法についてです!
ある期間の売上原価を計算するには以下のB/Sの表のように計算します。
表左側の仕入高と期首商品の合計が550、これに表右側の期末商品の40を
引いた510が売上原価となります。

P/Lの情報を利用して比較分析をする方法は2つあります。
競合他社のP/L情報を比較する相互比較と同じ企業の数年分のP/L情報を
比較する期間分析があります。
比較分析を行う上で売上高利益率を比較しますが、3種類の利益率が
あります。
・売上高と売上総利益で算出するものは、売上原価率と併用され、競争力を
示します。
・売上高と営業利益で算出するものは、本業の利益率を示します。
・売上高と経常利益で算出するのものは、企業の正常な収益力を示します。
損益計算書についてについてはこれで終了です!
次回はキャッシュフロー計算書について説明していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
