
【書籍紹介】戦国武将を推理する
今回紹介する本の著者は、直木賞作家でもある、今村翔吾さん。
直木賞受賞作である、「塞王の楯」は500ページ越えなのに、スラスラ読めて一気読みしてしまいました。
今日ご紹介する本ではないのですが、お勧めです!
大人気作家で、連載を7つも抱えつつ、各地で公演を行ったり、本屋を経営したり、、、と大活躍の、今や時の人といえる今村さん。
歴史が大好な今村さん。僕も戦国時代と幕末が大好きなミーハーですが、最近読んだ本が面白かったので紹介させてください。
タイトルは、「戦国武将を推理する」
数多くの歴史上の偉人を詳しく知っている今村さんが、日本人なら誰もが知っている、聞いたことある偉人たちについて、実はこんな人だったのだろう、と事実をもとに性格まで推理し解き明かしていく本です。
推理する戦国武将は?
本書で取り上げる戦国武将は以下の8名
・織田信長
・豊臣秀吉
・徳川家康
・武田信玄
・上杉謙信
・伊達政宗
・松永久秀
・石田三成
名前を聞いただけで、ワクワクしてくる、そんな8人!
どの人も大河ドラマの主役級の武将ばかりです。

意外と事実は違うもの?
読んでいて興味深かったのが、大河ドラマ等で描かれている人物像と、実際の性格は、実は違っていたのではないかという推測が随所に出てくること。
例えば、伊達政宗は母(義姫)が次男である小次郎を寵愛していて、政宗を疎んでいたというのが通説ですが、76歳で亡くなる前に政宗にあてた手紙では、政宗の道中の無事や孫への気遣いを記している等、実は母親からは大切に思われていたと感じる箇所や、
ダークヒーローの代名詞として描かれがちな、松永秀久は、むしろ主家に対して忠義を貫いていた?と思うような記述があったりと、ステレオタイプなイメージに捉えていた人物像と違った一面が垣間見れ、面白かったです。

分からないから楽しい
本書は、書いてあることは、あくまで推理なので、本当のところは分かりません。僕らが、今当たり前と思って知っている事実は、実は昔の人が自分たちに都合よく解釈し、事実を歪曲して書いている物語があったとしてもおかしくはありません。
この事実が分からない、これが実は一番楽しいことなのかもしれません。
織田信長にしても、本能寺の変で何故、明智光秀に討たれたのか。
明智光秀の謀反の理由は?
豊臣秀吉が朝鮮出兵をおこなった本当の理由は?
色々と有力な説はあるものの、何が本当かは今やだれも分かりません。
でも、それが、そのドキドキ感が、人を魅了するのだと思います。

後継者を選ぶ難しさ
現代の経営者が後継者選びに苦労するように、歴史に残る武将たちも、同じく苦労したようです。
特に、本書に出てくる、武田信玄、上杉謙信は後継者をしっかり定めぬまま亡くなったことで、武田家は滅亡。上杉家は大きく領地を失いました。
一方、若いうちに家督をついだ、徳川家康は300年近くにわたる長期政権を築けたことを考えると、家康の凄みを実感します。
そんな家康は、かなりの読書家で、学びの人だったようです。
日本、中国の昔の偉人の話を同じように読み、その失敗から学び、実際に活かす。それがとても上手だった人なのだと思います。
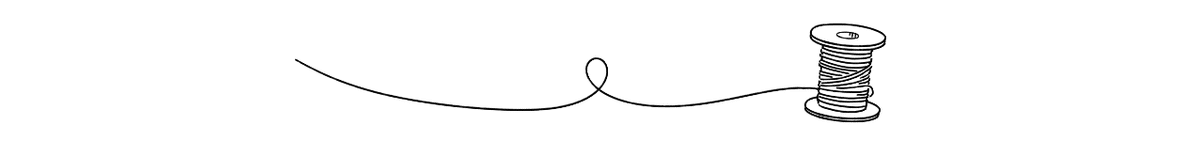
歴史を知ると、街歩きが楽しくなる
歴史は面白い!!
アラフォーになり、つくづく思います。
そして、こんなに魅力的な先人たちを沢山輩出し、長く・濃ゆーい歴史・文化がある日本に生まれたことに感謝してます。
円安で海外に行けなくても、僕らにはこんなにも魅力的な日本国内旅行があります!(笑)
いくら円安だからといっても、こんなに海外の人が日本へ来るというのは、魅力にあふれているから。本当にそう思います。
ブラタモリを見ると、もーーーっと国内色々なところに行きたくなると思うので、ブログも是非読んでください(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
