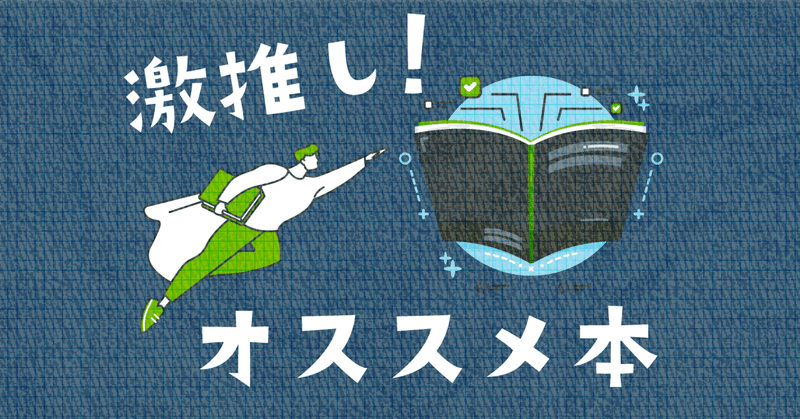
#050【書籍紹介】一流の人に学ぶ自分の磨き方
ゆっくりなペースではありますが、ようやく50記事達成です。今回は最近読んだ本について考えをまとめてみました。GWは家族サービスに時間を使ったこともありほとんど読書をする時間が持てませんでしたが、何とかこの本だけは読み切ることができました。
書籍紹介
今日御紹介する本はこちらです。
冒頭に著者の自己紹介も含めた文章があるのですが、それによると著者は一流と呼ばれる人と二流の人とどう違うのか、について20年以上研究してこられたのだそうです。
本書では一流の人が持っているものは何なのか、信念や情熱といった様々な観点から分析をしています。内容的にすごく励まされるものでもあり、同時に自分の至らなさを痛感させられるものでもありますが、しごとでもプライベートでも何か思い悩んだときに解決の糸口を与えてくれるかもしれません。
今回はこの書籍の中から、特に個人的に多くの学びを得た部分を、自身の経験も含めて御紹介したいと思います。
ジブンが提供できる「価値」の見つけ方
組織の中で「価値」を発揮するときの心構え
コミュニケーションを通じてその「価値」を営業するコツ
について述べたいと思います。
ジブンが提供できる「価値」の見つけ方
一流の人はほんの少しの違いを大切にする
ジブン株式会社マガジンへの投稿をnoteで始めるようになってから、「自分にしか提供できない価値は何だろう?」とずっと考えています。私はクリエイターほど突き抜けたセンスを何か持っているわけではなく、大学で学んだ分野を社会に出て磨いてこられたわけでもありません。
ですがこの言葉に出会って、まずは人とどこが違っているのかについて意識を向けるようになりました。そうすると、業務のオンライン化という文化を定着させようとしていること、不動産について実践を始めたこと、OB会でいろいろともがいていること、等は違いととらえていいのかなと勇気をもらいました。
今後もこの「違い」を大切にし、ジブンの付加価値を高めていきたいと思いました。
組織の中で「価値」を発揮するときの心構え
一流の人は自分を自営業者だと考える
ここで一流と二流との違いについて、二流の人は自分のことを組織の一部と考えるのに対し、一流の人はプロとして良質な労働力を会社に提供していると考える、と紹介されています。ジブン株式会社で時折登場する、会社からただ給料をもらっているというわけではないという話ですね。
私は仕事の中でもとりわけ会計などの定例業務が苦手で、前年同月に作成した資料や前月の資料を当月版に書き換える作業でほぼ毎回どこかが抜け落ちてしまうというエラーを起こします。そのたびに自分の至らなさを実感して軽く凹むのですが、同時に間違いが起こらない仕組みを少しずつ導入するようにしています。1か所に日付さえ入れれば、「○月分」という表記が全て書き換えられるようにしたり、オンラインで入力されたデータを貼り付けるだけでフォーマットに落とし込まれた状態になるようにしたりと、業務の効率化にちょっとずつ貢献できている点では、良質な労働力を提供できていると自負してもいいかもしれません。
ジブンが日々何を組織に提供できているのか、考え続けることが大切ですね。
コミュニケーションを通じてその「価値」を営業するコツ
一流の人は感情にもとづくコミュニケーションを重視する
個人的に一番学びになったのはこの項目です。この項目では感情について記載されているのですが、二流の人との違いについてこう書かれています。
「二流の人は、自分の決定がたいてい論理にもとづいていると思い込んでいる。
一流の人は、人々が感情的に決定を下し、論理的に正当化することを知っている。」
この「感情的に決定を下し、論理的に正当化する」という部分を読んで、多くのことが腑に落ちました。OB会で様々な提案をしても大半が却下されてきたのですが、その背景には「よくわからない=怖い」という感情があったのかもしれません。
でもそれを「怖いから」ということは言わず、「高齢の人は慣れていないから」とか「今までもそれでやってこれた」とか「議論が尽くされていない」とか言って感情を表現してこなかったんですね。これからはこの「怖さ」にもっとフォーカスし、これを解消するためのアプローチに意識を向けていきたいと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。ジブンの価値については、これからも様々な学びと実践を通して高めていこうと思います。これからはそれにくわえて感情にフォーカスしたコミュニケーションを意識し、その価値を組織文化として定着させていくための取組を進めていこうと思います。
同書の最後のほうに「EQ」という言葉が登場していましたので、本書を読み終えてすぐにEQについて書かれた本を読み始めました。次回はこのEQについて書かれた本を御紹介できればと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
