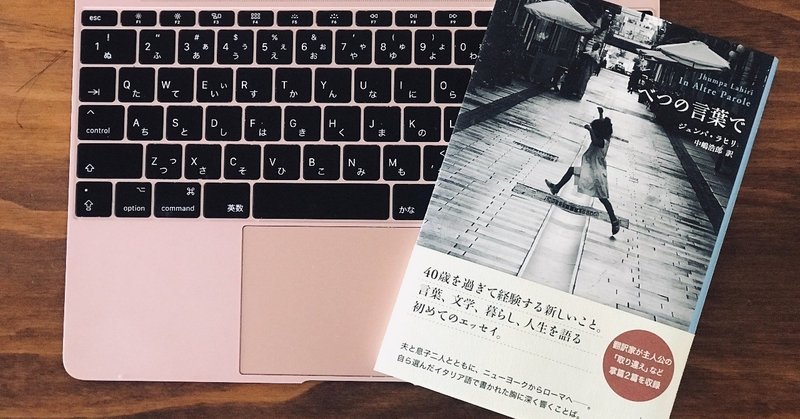
水曜日の本棚#13 べつの言葉で
最近、「言葉」、というか言葉を成立させるもの、言葉ができることやできないことについて考えている。そんななか、本棚の端っこから引っ張り出してきたのがジュンパ・ラヒリの「べつの言葉で」。
3-4年前、同じように「言葉」について考えていた時期があって、それを聞いた友人のひとりが勧めてくれた1冊だ。コルカタ生まれの両親の元に生まれ、アメリカで育ち、ベンガル語と英語という2つの「母語」を常に行ったり来たりしながら生きてきた作家が、その言語的な緊張関係から逃れるようにイタリア語を学び始め、40代でローマに移住。このエッセイ集は、彼女が創作の挑戦、言語的な挑戦として「第3の言語」イタリア語で書いたものだ。
1年ほどローマに滞在し、夏の間をNYで過ごすために帰国していたラヒリの苛立ちと戸惑いがこう書かれている。
いまわたしは二重の危機的状況にあると感じる。ある意味において、わたしとイタリア語の間に大洋があることを実感しているう。もう一方では、わたしと英語との乖離を感じる。
(中略)なぜ、もう英語が親しく感じられないのだろう?それを通じて読んだり書いたりすることを学んだ言語が、どうしてわたしを慰めてくれないのだろう?何が起こっていて、何を意味するのだろう?疎外感と幻滅を感じ、心がかき乱され、動揺する。
自分が決定的な言語もなく、原点もなく、明確な輪郭もない作家だとこれほどまでに感じたことはない。それが有利なことなのか不利なことなのかはわからないけれど。
(「べつの言葉で」ジュンパ・ラヒリ 中嶋浩郎訳)
あるときある言語に恋していて、それにどっぷり浸かっていたいと思う気持ち。こんなに情熱があるのに、絶望的な距離を感じる気持ち。母国語以外を操るときの、不自由で仕方ないけれど、同時に圧倒的に自由だと思う気持ち–。
世界的な作家と自分を同列で語りたいわけじゃないけれど、第一線の創作者がこうして「言葉」に対する挑戦を続けているのだと思うと、少なくとも自分が彼女と同じ競技−それが町の運動会なのかオリンピックなのかの差はあれど−仲間のような気がして密かに嬉しい。
Thank you for reading!
