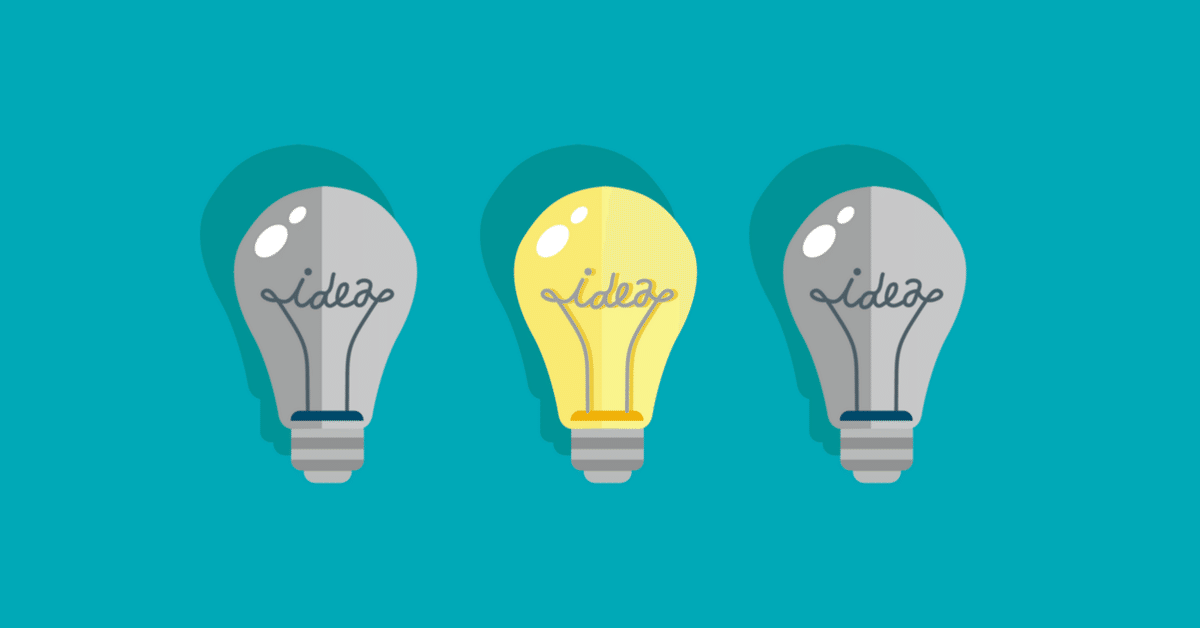
自分の話に定義づけする
英語は日本語より、言語によって意味の定義づけをする言葉です。
そのため、自分の話に定義づけする表現も多いです。
これは一般的な話だという時は、
Generally speaking
それに対して、個人的な時は
Personally
正直な話と定義すると、
Honestly
理論的な話は、
Theoretically
事実は、
In fact
など、文頭に
さあ!こんな話をこれからするぞ!
とばかりに自分の話に定義づけするのです。
これは、英語圏の人の話し方の特徴で最初に言いたいことを言う傾向が強いことにも起因している。
最初に、引き寄せるための表現が使われます。
自分の感情を、表す場合でもそんな表現はある。
悲しい感情は、Sadly
願望を表す場合は、Hopefully
の様に最初に示し分かりやすくする人も珍しくはない。
今、伝えようとしていることはこんな事だよと明確に示す場面が日本よりは多くなるのが英語圏の傾向となっている。
日本で話しをする時は、あまり意識していないかもしれないけど、意外と定義づけして話していないはずだ。
全体の流れから意味をとるという、結構高度な技術がいるのが日本語圏の特徴と感じる。
間違えて文脈をとると、途端に通じなくなるのが日本語のような気もしないでもない。
事実、議論、感想をごちゃごちゃにする。
一般論と個人の願望を混乱して解釈する。
相手の感情を勝手に推測し外す
こんな事を起こしていないだろうか?
定義づけが少ないという事は、それが起こりやすいものだ。本来はその注意信号がいる。
英語は、世界で共通言語として使われている。
そのためだろうか。
最初から、分かりあうのは案外難しいという観点からコミュニケーション論を教え込んでいる場が多いのを私は知った。
これは、どの言語でも参考になる観点だと思う。伝えるのは結構大変だと思っておく気持ちは、分かりやすく伝えるのには必須だろう。
英語圏では、文頭で自分の話に定義づけする表現を使って、最初に言いたいことを言い相手の注意を引き寄せる。
そして、全体を分かりやすくする工夫がある。
時には内容であったり感情であったりを最初に要約してしまうという事。
文頭にパーンとそういう表現を置き、自分の話に定義づけするのは、言わなくても分かるという感覚とは真逆な感じがするなあとも思います。
ー
英語表現についても、書いています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
