
小説『木曜日にはココアを』
川沿いの桜並木がちょうど終わるあたりに佇む喫茶店「マーブル・カフェ」。ここで働く青年は、毎週木曜日に来店する女性に恋をしている。ここを出発点とし、遠くはシドニーまで繋がっていく愛の連鎖。12話から成る連続短編小説。
各話のタイトルには、ブラウン、レッド、イエローなど色が添えられている。物語内に必ず色の要素が組み込まれており、色彩豊かな世界が広がっている。 1話あたりのメイン登場人物は2〜3人で、そのまわりに何人かの脇役がいるというのが基本構成。そこに出てきた準主役または脇役が、次の話では主人公になっている。しりとりのように次から次へと、人々が結ばれていく。登場人物の多くが何かしらの緊張状態にあり、他者との繋がりによってその緊張が解けていく。タイトルの「ココア」から連想するものと同じように、どの話もほっこりあたたかい気持ちになれる。
私が最も好きなのは、7話「カウントダウン[Green/Sydney]」だ。この主人公は、緑色の虜になっている駆け出しの画家。彼女が描く世界は緑色のみ。その執着ぶりにまわりからは異常だと判断され、孤独を感じている。ある日公園で緑色の絵を描いていると、緑色のオーラを纏う青年に出会い……という話。
私はこの主人公・優に、エリック・ロメール監督の映画『緑の光線』を激推ししたい。『緑の光線』も、周りに馴染めない女性が主人公。星占い的に自分のラッキーカラーが緑だと知ってから、やたらと緑色が目に留まるようになる。緑のビラ、緑のトランプ、そしてジュール・ヴェルヌの小説「緑の光線」……。緑の光線(グリーンフラッシュ)とは、空気の澄んだ日に稀に見られる、日没の瞬間に放たれる緑色の太陽光のこと。ヴェルヌの小説では、“緑の光線を見たものは自分と他人の心が分かるようになる”という設定で、その話を偶然耳にした主人公は、自分の目でも緑の光線を見るべく海へ向かう。
ロメールは色彩を巧みに使う。ほとんどの作品で脚本も務めるロメールは、脚本を執筆している段階で色彩について考える。色彩ありきの物語という点で、『木曜日にはココアを』と通ずる部分がある。
しかしやっぱりロメールと違うところは、ロメール作品における登場人物に比べて、『木曜日にはココアを』では多くの人が好感を抱きそうな心地よい登場人物しか出てこないところだろうか。優しくて、一生懸命で、誰かのことを純粋に想っている人たち。ロメールの描く人物は、“身近にいる曲者”ばかりだ(私の場合は“身近”ではなく“自分自身”なのだが)。ロメールは、人によっては腹立たせるほどの曲者たちを俯瞰して描く。それがただの冷たさにはならず、まるっと抱きしめてくれるようなあたたかい眼差しをもって描くのだ。ロメール作品と『木曜日にはココアを』は、着地点は同じようなあたたかさであるが、そこにたどり着くまでのこういった行程が異なる。
ただ、7話「カウントダウン[Green/Sydney]」の優については、緑色に取り憑かれているという点で逸脱した人物である。孤独な彼女がようやく居場所を見つけたような感覚に涙する瞬間、私がこんなにも胸を打たれたのは、やっぱり私は拘りが強すぎるゆえに馴染めずにいる人たちが、この拘りを貫いていいのだと再び信じはじめるのが大好きだからだと思う。
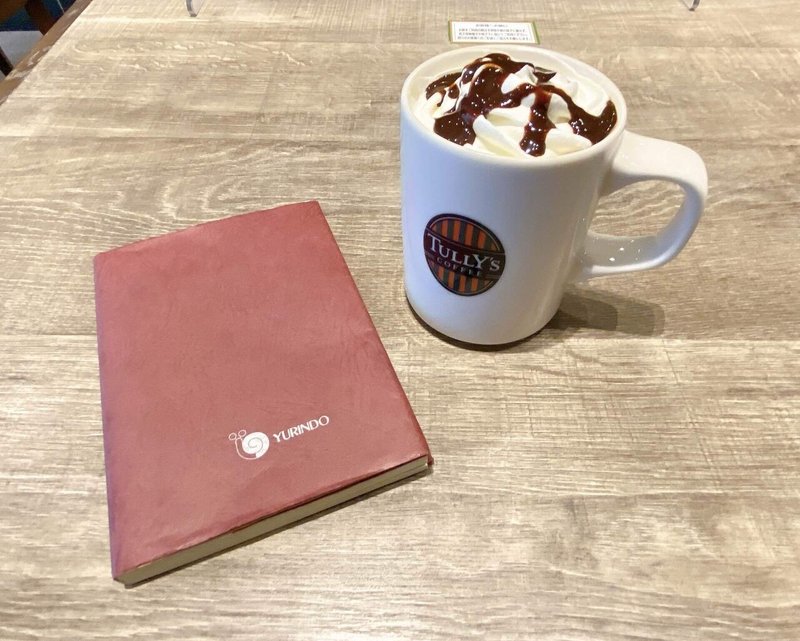
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
