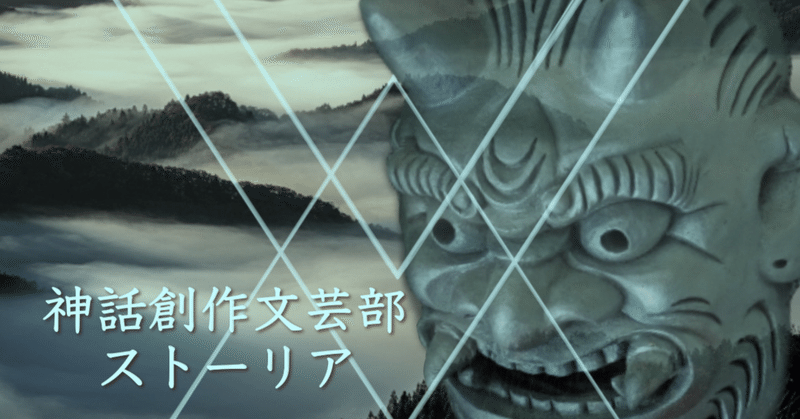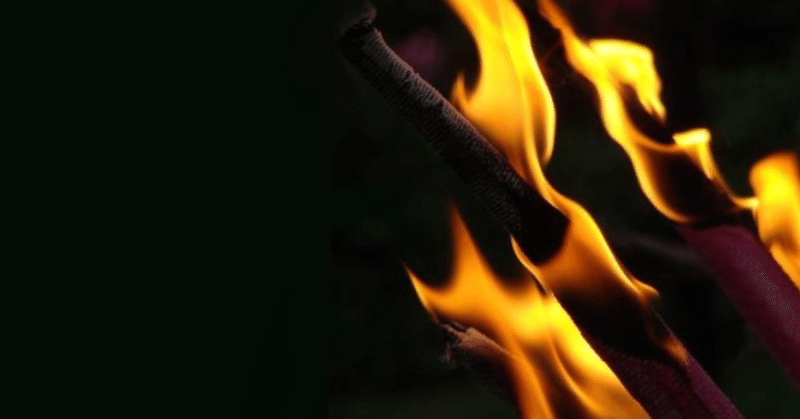#mymyth
天宇受売命という存在 前編
日本神話の中でわたしが最も好きなキャラクターは天宇受売命(アメノウズメ)だ。
彼女の説話から、古い古い時代の素朴な神話の精神を垣間見る事ができるからだ。
さてその上で、後世①かかる説話から彼女の存在を薄めてしまったように感じられる事。②彼女の事を具体的には見出せずとも、強く彼女の存在を感じる事。このふたつの事象について、前後編にわけて書いてみたい。
それによって、わたしの胸中に湧く神話の世界観を、
天宇受売命という存在 後編
前編はコチラ
後編 ② 戯れては笑ひゑらぐ
天と地が分かれ、山河が整い男女が現れ結ばれて子孫を残す。やがて闘争や支配、統治に進む。
これを軸に様々な理に対する説明や、正当性の提示という枝葉を付ける。
時代の経過に伴い、世相思想を反映させ、後の人々の手による解釈や脚色も加わりながら、神話は整ってきたのだろう。(少なくとも日本の神話は)
物語が進むにつれて、人の感情の投影が増え、神々が徐々に人に
空高く生まれ土深く潜る
この冬神話部は三周年を迎えた。このタイミングで神話全体について思う事を少し書いてみたい。
想像するしか無い事を前提とした上で、世界各地の神話についてかねてより感じていた事がある。
全体的な話としてより古く、オリジナルに近くなればなるほど、神話は心のありようや心の作用といった領域については、さほど深入りしていなかったのでは無いか?という印象をわたしは持っているのだ。
後に出てくる、確固とした教説
え、そこで完結ですが
正直、唐突過ぎるのだ。
神話部に寄せるコラムや論考もどきの記事が。
当のわたし自身がそう思っている。それを何とかしてくれているのが神話部の存在だ。
部長の矢口さんが覚え書きを出された。これは神話というモチーフであるがゆえ、非常にデリケートに扱うべきという信念の現れだと思っている。
宗教性や信仰性と切り離す事が難しく、思想の誘導を促しかねないからだ。
エッセイ、コラムの類いを書く時に気を付けてい