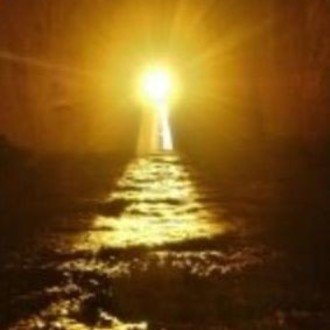英詩の基礎知識(1)
※ 旧「英詩が読めるようになるマガジン」(2016年3月1日—2022年11月30日)の記事の避難先マガジンです。リンク先は順次修正してゆきます。
ふつうの英文を読んでいて、おやっ、これはちょっと違うな。ふつうの散文のような英語の感じと違うな、と思ったら、たいてい、それは英詩です。
「タイム」や「ニューズウィーク」のような雑誌でも、ふつうの英文図書でも、英詩が途中で引用されることは、めずらしいことではありません。それどころか、フランス語の本(ジャック・アタリとかエマニュエル・トッドとか)でも、扉に当然のように英詩が引用されます。
そういうときに、英語話者やフランス語話者の人々は英詩の部分を飛ばすのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。散文と同じように、読みすすめます。詩としてちゃんと読みます。
彼らは英詩の専門家でしょうか。いいえ、ふつうの人々です。では、どうやって読んでいる? と思うでしょうが、彼らがふつうに知っている英詩の常識的な基礎知識(と思われるもの)を以下、簡潔に書いてみます。面倒くさいと思われるかもしれませんが、最低限の知識があるとないとで、詩の理解が大きく変わってくるのです。
1. ピリオドを見つける
簡単なことですが、これは意外に大事です。詩であっても、必ずピリオドがあるはずです(ない詩もありますが、特殊な例外です)。
要点は、ピリオドまでを一文として——1センテンスとして——、ふつうの英文のように捉えるということです。これが出発点です。行のおしまいが意味の切れ目とは限らない、ということが、隠された重要なポイントです。ピリオドは行の途中に来たり、何行も進んだあとに出てきたりして、見つけにくいことがあるのです。ひょっとすると、引用が短すぎて、ピリオドがないケースもあり得ます。その場合は、1センテンスの一部ということになります。
2. 詩形を見つける
これは簡単な場合もありますし、そうでない場合もあります。特に、引用されているのが、ごくわずかな場合は、詩形を見つけることが難しいこともあります。
ですが、大体のところは、勘でわかります。おそらく、多くの読者は、そういう勘をはたらかせているのです。
勘をはたらかせるには、材料が要ります。次の材料のうち、一つでも多く分かれば、それだけ詩形が見つかる可能性が高まります。詩形が分かれば、詩の理解に一歩も二歩も近づきます。
(1) 1行まるまる引用されている場合は、その1行のリズム
(2) 2行以上引用されている場合は、行間の押韻のパタン
(3) 1連が引用されている場合は、その1連の詩的構造
(1) → (3) にすすむに従い、専門度が上がります。でも、心配はいりません。極端なことをいえば、リズムを楽しむことができれば、それでその英詩の楽しみの半分くらいは味わえたも同然です。それは1行以下の引用であっても同じです。
2.1 リズム
英語は強勢でリズムをとります。どこを強く読むか、が分かればリズムが分かります。
どこを強く読むか、には少しだけ専門的なことが入ります。が、おそらく一般の読者はそこまでの知識はないでしょう。短く引用される場合は、だれが読んでも同じところを強く読むだろうということを前提にしているでしょう。
2.1.1 単語の強勢
単語の強勢(語強勢)は簡単に分かります。多くは第1音節に強勢がありますし、そうでない場合も、辞書で調べれば分かります。
この単語の強勢は、辞書に書かれている通りであるか、といえば、詩の場合は必ずしもそうとはいえません。ですが、詩の韻律により単語の強勢に変更が生じる場合は、一般の読者にはおそらく分かりません。それが分かるのは、詩の韻律の知識がある人だけです。ふつうに引用されるような英詩にそのレベルのことはめったに発生しません。
2.1.2 句の強勢は「弱強」
単語と単語とが結びついた句(phrase)の場合、どこに強勢がくるかということは、一定の法則があります。英語話者はその規則そのものは知らないでしょうが、感覚で身についています。このあたりはフランス語話者は分からないかもしれません。
句の強勢(句強勢)は辞書によっては明示してありますが、成句になっていないものについては、法則を応用するしかありません。その法則とは
A B から成る句の場合に強勢は B にくる
ということです。これを言語学の一部門、音韻論では中核強勢規則(NSR)と呼びます。
2.1.3 複合語の強勢は「強弱」
単語と単語が強く結びつき、一語となっている場合——つまり複合語となっている場合——にどこに強勢がおちるか(複合語強勢)、について辞書にはたいがい書いてあります。が、これにも一定の法則があり、それを知っていれば辞書がなくても分かります。その法則とは
AB から成る複合語の場合に強勢は A にくる
ということです。音韻論では複合語強勢規則(CSR)と呼びます。
2.1.4 例
以上の強勢のルールを実例で確かめてみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?