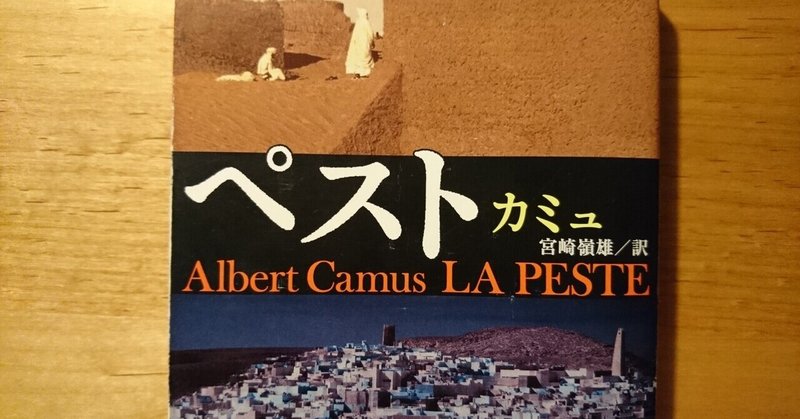
続く異常な日常の中で
カミュ『ペスト』を読んでいる。感染症が蔓延する街で、人々の治療に当たる医師の話。そうまとめてしまえばそれだけだけど、それは日常と化した異常とどう付き合っていくか、改めて考えさせられる内容になっている。
目の前の人は救えるかもしれない、でも蔓延を止めることができない。一瞬の勝利と、終わりなく続く病への敗北が描かれている。
「(…)あなたの勝利は常に一時的なものですね。ただそれだけですよ」
リウーは暗い気持ちになったようであった。
「常にね、それは知っています。それだからって、戦いをやめる理由にはなりません」
「確かに、理由にはなりません。しかし、そうなると僕は考えてみたくなるんですがね、このペストがあなたにとって果してどういうものになるか」
「ええ、そうです」と、リウーはいった。「際限なく続く敗北です」
コロナが流行している今、この本が他人事とは思えない。勝利が一時的なものであったとしても、いつものマスク・手洗い・うがいを止めていいわけではない。負け続けるか、それとももっと大きく負けるか。その二択しか許されていないから、そうなれば前者を選ぶしかない。
すごく自分が無力だと思う。何か医療に貢献できるわけでもないし、政治の決定権も持ってない。ただ単独行動を心掛けて、大切な人とは連絡を取り合う。誰のことも忘れないようにする。
ウィルスとの戦いが消耗戦と化していて、自暴自棄になるのは簡単だ。「手洗いうがいしてきたけど、なんの意味もなかった」と言ってやめるとか、「飲み会はしごしても意外と感染しないから大丈夫」と大人数で食事して盛り上がるとか。いままで「大丈夫」だった人が、羽目を外しているのがチラホラ見かけられる。
おとなしく家にいても、何も変わらなかった。生活が規制されるばかりで、いいことは何もなかった。そういう恨みにも似た気持ちが、人々をヤケクソにする。政府や知事からの、圧力を伴った「お願い」を、もう誰も本気にしていない。マスクをするのは当たり前で、人と会えないのも仕方なくて。
『ペスト』にも、異常事態に慣れていく市民の姿が描かれる。
市民たちは事の成行きに甘んじて歩調を合わせ、世間の言葉を借りれば、みずから適応していったのであるが、それというのも、そのほかにはやりようがなかったからだ。
彼らはまだ当然のことながら、不幸と苦痛との態度をとっていたが、しかしその痛みはもう感じていなかった。
それに、たとえば医師リウーなどはそう考えていたのであるが、まさにそれが不幸というものであり、そして絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである。
……絶望に慣れることは、絶望そのものよりもさらに悪い。
異常を当たり前だと思ってしまうこと。これが異常事態なんだという感覚が薄れていくこと。それは確かにいま起こっている現象で、ペストは他人事じゃなかった、と思う。
だからこそ、本の中に書かれた言葉はどれも、身近なものに聞こえてくる。
「──健康とか無傷とか、なんなら清浄といってもいいが、そういうものは意志の結果で、しかもその意志は決してゆるめてはならないのだ。りっぱな人間、つまりほとんど誰にも病毒を感染させない人間とは、できるだけ気をゆるめない人間のことだ。しかも、そのためには、それこそよっぽどの意志と緊張をもって、決して気をゆるめないようにしていなければならんのだ」
毎日の仕事のなかにこそ、確実なものがある。(…)肝要なことは自分の職務をよく果すことだ。
「人類の救済なんて、大袈裟すぎる言葉ですよ、僕には。僕はそんな大それたことは考えていません。人間の健康ということが、僕の関心の対象なんです。まず第一に健康です」
まず第一に健康です。そうして、日々やるべきことをこなす。気をゆるめないで。本当にそれしかできないし、それができることが、いま一番尊いのだ。際限なく続く敗北の中で、タフな正気を失わない。その粘り強さが、改めて必須だと思う。ペストでもコロナでも変わらずに。
参考文献:カミュ『ペスト』宮崎嶺雄訳、新潮文庫、平成30年
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
