
栄養食事療法№6 糖尿病編 あなたにもできる糖尿病の食事療法
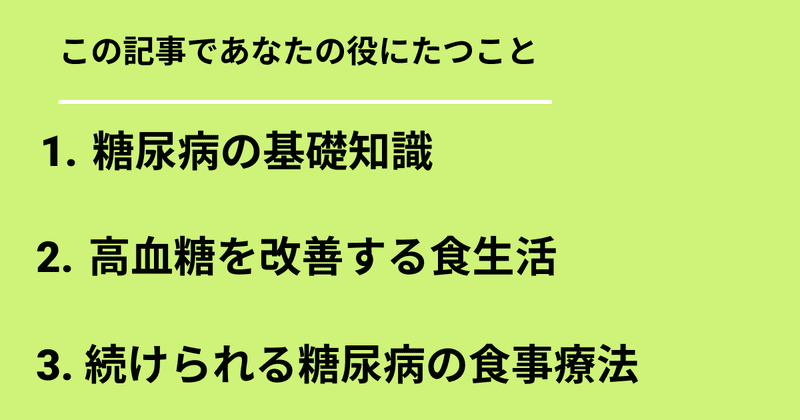
糖尿病という病名のイメージが、食事療法への取り組みを鈍らせるのではないか、と思うことがあります。
糖尿病の三文字には、尿から糖が出る病気?甘いものを食べたり酒を飲んだり過食して肥満になった、という行動が攻められている印象があります。
そうした行動は糖尿病発症の引き金になることもありますが、適切な食生活を送っていても発症する場合もあって、一概に生活行動を非難してはいけないと思っています。
〇糖尿病とその現状
糖尿病は、血糖値を下げるインスリンというホルモンが何らかの原因でうまく機能しなくなり、血糖値が慢性的に高い状態にある病気です。
その成因は、1型といって膵臓のβ細胞の破壊で絶対的にインスリンが欠乏するものと、2型といってインスリン分泌低下やインスリン抵抗性、インスリンの不足による場合があります。その他にも特定疾患によるものがあります。
この病気で恐ろしいのは、高血糖を放置したために血管にダメージを受け、糖尿病腎症や糖尿病網膜症、糖尿病神経障害などの三大合併症や心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化症がおこり、日常生活に支障を生じることです。
日本人の誰でもが発症の可能性があります。早めに治療をする必要があります。
昨年、糖尿病の通院患者数は327万人と過去最多となりました。
また、2018年国民健康・栄養調査の結果(2020年1月厚生労働省発表)をみると、糖尿病が強く疑われる人の割合は20歳以上の男性で18.7%、女性では9.3%と前年度と比較して、男性では0.6%増加し女性では1.2%減少しました。
(この調査では*HbA1cの測定値が6.5%以上(NGSP値)又は糖尿病治療を受けていると「糖尿病が強く疑われる」と判定される)
年齢が高くなるほど強く疑われる比率が上昇し、近年、加齢で血管の老化が糖尿病を引き起こすのではないかとの研究も行われています。
*HbA1cとは
赤血球中のヘモグロビンに糖が結びついて糖化したもので、血糖コントロールの評価に使われる検査値です。赤血球の寿命が約4ケ月なので、HbA1cを測定すると、過去1~2か月の平均的な血糖値を把握できるというものです。
〇糖尿病の判定区分
糖尿病の診断は、個々の状況を考慮しつつ半定基準等に基づいて主治医が行うものです。健康診断等の再検査において、糖代謝を判定する区分ですが、参考までに載せておきます。

糖尿病治療の目的
治療の目的は、長期に渡り血糖、体重、血清脂質、血圧等を良好にコントロールすることで、糖尿病の合併症や動脈硬化を予防し健康を保つことです。食事療法をはじめとした治療が個々に応じて適切に行われれば、糖尿病の発症や進行を遅らせることができます。
「高血糖ですね」と言われたら、自分でできることに先ず取り組んでみましょう。
すでに糖尿病で医療機関に受診している人は、主治医の指示に沿って行ないますが、自分でできることとして「食生活の行動変容」は健康を担保するために大きな意味があります。
血糖コントロールの目標値は(成人に対して)HbA1c(%)を学会では重視し、下記のように目標値を挙げていますので参考までに示します。
なお、65歳以上の高齢者は低栄養状態等を危惧して、別に設定されていますが今回は省きます。
・血糖正常化を目指す際の目標・・・・HbA1c(%)6.0未満
・合併症予防のための目標・・・・・・HbA1c(%)7.0未満
・治療効果が困難な際の目標・・・・・HbA1c(%)8.0未満
*治療目標は年齢、罹患期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを個別に主治医等専門スタッフが設定
日本糖尿病学会2020~2021 糖尿病治療ガイド 参照
〇なぜ食事療法が継続できないのか
薬物治療と違って直ぐには成果が見られないからのようです。長期にわたって高血糖になったのですから、あわてずゆっくりと取り組む必要があります。しかし、情報が多いため混乱して、自身が信頼できる「食事療法の指針」が見い出せずに途中でやめてしまうことが多いようです。

食事療法の手引きとして何らかの指針とバロメーターは欲しいですね!
最近、食べた物を撮影し、自動処理でカロリー計算や栄養バランスを評価してくれるアプリも多く出て便利になりました。それはそれで役立ちますが、「食べてしまったものを多かった少なかったと評価してみてもそれだけでは意味がありません。
これから食べるものを適正に選択できる力こそが必要です。
そのために開発されている「糖尿病食品交換表(日本糖尿病学会編)」があり、私はこの活用をおすすめしています。アナログですみません!
最初は面倒と思う人も少なくありませんが、毎日自分が食べる食材の種類はそれほど多くありませんし、身についてしまえば概算で簡単に行うことができる指南書です。
病院の受診時又は近隣の薬局にいる管理栄養士にご相談いただくと詳しく教えてもらえます。
〇おすすめ「糖尿病食事療法のための食品交換表(日本糖尿病学会編」の活用
この食品交換表は1965年(昭和40年)に初版されて以来、版を重ねて55年余りのロングセラーです。全国の医療機関で標準的に使用されていますので、受診する病院が変わっても共通して使えます。
今、この時代においてなぜこれをおすすめするのか!!
答えは簡単、何もなくても目で見て暗算で計算でき、栄養バランスの良い食べ物の組み合わせをを予測する力が身につくからです。その点で、食品交換表を活用してみる価値はあります。
私がこれまで栄養指導で指導してきた患者さんのほとんどから「最初は大変だったけど最終的に交換表が無くてもカロリーや食品の組み合わせがわかるようになった」「身に着けたら一生の財産になった」等交換表を手引書として使ってよかったという声が聞かれました。
最初はおっくうでも、慣れてくると(平均3か月くらいの使用)おおよそでカロリー計算をして食べるので、長期に無理なく続けられます。
そこで「糖尿病食事療法のための食品交換表」の使い方を説明していきます。1冊1000円弱です。
冊子 糖尿病食事療法のための即品交換表の表紙

食品交換表のつくり
①食品交換表の仕組みと構成
日頃食べている食品を似たような栄養素別に6つの食品グループと調味料に分けて構成されています。食事療法のために指示されたエネルギー量や栄養素をとるために、どのグループの食品からどのくらいの量を組み合わせて食べればよいかを朝食・昼食・夕食へ配分して示したものです。
②食品交換表の食品分類
表1:炭水化物を多く含む食品
穀物・いも・炭水化物の多い野菜と種実・大豆を除く豆
表2:炭水化物を多く含む食品
くだもの
表3:たんぱく質を多く含む食品
魚介・大豆とその製品・卵、チーズ・肉
表4:たんぱく質を多く含む食品
牛乳と乳製品(チーズを除く)
表5:脂質を多く含む食品
油脂・脂質の多い種実・多脂性食品
表6:ビタミン、ミネラルを多く含む食品
野菜(炭水化物の多い一部の野菜を除く)
海藻・きのこ・こんにゃく
調味料:みそ・みりん・砂糖など
日本糖尿病学会編「糖尿病食事療法のための食品交換表(第7版)」参照
③食品80㎉当たりの分量を1単位で表している
食べる量をはかる物差しとして食品80㎉あたりの分量を1単位と呼び、食品の表ごとに1単位当たりの食品重量(g)を表示しています。
同じ表の中であれば、食品80㎉当たりの食品を交換することができ、バランスを崩すことはありません。
例えば、卵1個80㎉と豚肉60g1切れ80㎉は同じ表なので交換できます。しかし、卵1個80㎉の代わりにご飯を茶碗半分に変更するというのは表が異なりバランスを崩す原因となりますのでよろしくありません。
食品交換表を使った食事療法の手順① 食事療法の指針である自分の1日のエネルギー量を知る
年齢、性別、身長、体重、生活の活動量により個々に異なります。受診している人は主治医の指示エネルギー量を守り、そうでない人も活用できます。
【エネルギー(1日)量の算出方法】
先ず、自分のあるべき体重をイメージすることが大切です。目標体重を知り、普段の身体活動量を考慮して1日のエネルギー量を算出します。
1日のエネルギー量(㎉)=*①目標体重×*②身体活動量㎉
*①目標体重とは:身長m×身長m×BMI22
以前は標準体重と言いましたが、柔軟に対応するために目標体重というようになりました。また、65歳以上では、従来BMI22としていたものを22~25として幅を持たせています。
*2身体活動量
軽い活動量(デスクワークなどが多い仕事)25~30㎉/標準体重1㎏
普通の活動量(立って動くことが多い仕事)30~35㎉/標準体重1㎏
重い活動量(力仕事が多い仕事)35~㎉/標準体重1㎏
② 1日のエネルギー量を単位に変換し1日3食に分配して活用する
1日の指示エネルギー量を指示単位に変換して、朝・昼・夕食の量をほぼ均等に配分します。
例えば1日1600㎉の場合は1600㎉÷80㎉=20単位
つまり1個1単位の食品を20個分食べると1600㎉となります。
この20単位を三食に分けると、
朝食6単位(480㎉)、昼食7単位(560㎉)、夕食7単位(560㎉)が各食の単位配分の目安となります。
③栄養のバランスが偏らない組み合わせを決める
交換表を活用して栄養のバランスが偏らないようにします。
毎食、交換表の表1主食(炭水化物)、表3主菜(肉・魚・卵・豆腐等)、表6副菜(野菜・きのこ等)をそろえ、他に表2の果物と表4の牛乳・乳製品と表5の油脂類を加えるとバランスが整います。
〇自分でできる10の食行動
① 外食や総菜は、食べる前に栄養量の表示を確認する
② 油っぽいものを食べ過ぎないようにする。天ぷらやフライ等の揚げ物は、半分はそのまま食べ、残りは衣をはがして食べる
③ 食物繊維の多い野菜を意識してたっぷり食べる。その際、マヨネーズやドレッシングの量が多くならないように注意する
④ 料理は家族で大皿盛りで取り分けず、個別に盛り付けて食べると良い。そして、いつまでもながら食いをしなければ食べる量が決められる
⑤ 料理の味付けは薄味にすると、おかわりがしたくならない
⑥ 菓子や清涼飲料などの砂糖の多い食品は控えることが望ましい
⑦ 1日3食を時間的にも量的にも規則正しく食べる。1日1回や2回食、逆に間食を含めて5回食等では糖尿病が悪化しやすくなる。できるだけ均等に、ゆっくりよく噛んで食べることをこころがける
⑧ 定期的に体重を計測する習慣をつける
⑨飲酒は減量し主治医の指示を仰ぐ
⑩慣れないうちは食品を計量し、食事の内容を記録(自分がわかりやすい記録方法で良い)することで振り返ることができる

〇糖尿病食事療法への私の思い
糖尿病の治療が遅れ、足壊疽による切断、糖尿病腎症による透析、糖尿病網膜症による失明等つらい経験をお持ちの多くの糖尿病患者さんと出会いました。
重症化する前は会社でバリバリに働いていた男性、ご夫婦で旅行が趣味だったご主人、裁縫やスイーツ作りが趣味だった主婦、糖尿病の厳しい合併症によってこれらが奪われてしまったのです。ご本人はもちろんのこと、支えるご家族の人生も大きく変わりました。
糖尿病発症とともに発症後の重篤化は可能な限り予防し、一人でも多くの方が、このような苦しみを経験しないようにできたら・・・と思っています。
繰り返しますが、糖尿病治療の最大の目標は、血糖、血圧、脂質代謝のコントロールと適正体重の維持等を行うことで、糖尿病合併症の発症や進展を阻止して、健康な人と変わらない生活を送ることにあります。
私が病院の第一線で栄養食事療法を行っていた時は、「ダメとか控える」という言葉を連発しながらも「糖尿病重症化予防」に厳しく取り組んできました。一定の成果は見られましたが、治療でありながら、甘いものを食べるな、大食するな、酒は飲むな、脂っこいものはダメ等、ダメダメ尽くしで、人の楽しみを奪い続けてきました。
食事療法を長期的に継続するためには、その人の食習慣を尊重しつつダメだと思う内容を、食生活に少しだけ上手に取り入れる、という柔軟な考え方はとても大事だと思います。
それができるのは「糖尿病食品交換表」をマスターすることで応用が可能になる、と考えています。
糖尿病のコントロールはイコール健康になる取り組みです。
糖尿病でも、健康な人でも、ぜひ糖尿病の食事療法を行って、極端なカロリー制限をせずに、少しだけ自分用に柔軟な応用をして、食事療法を継続してください。
治療しながらも、食生活をぜひ楽しんでもらいたいと強く思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
